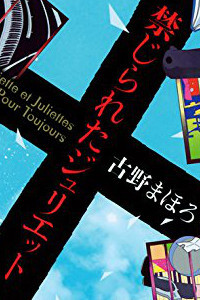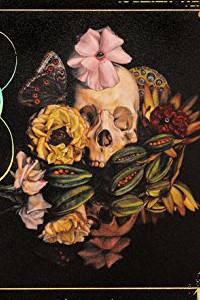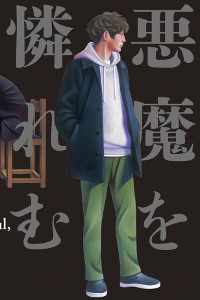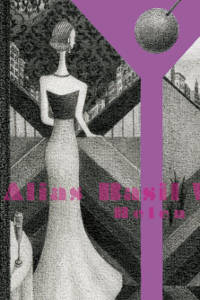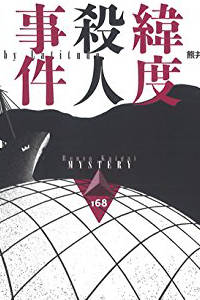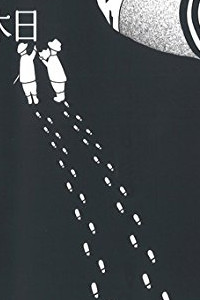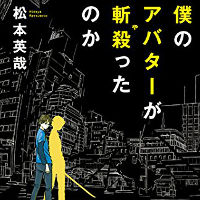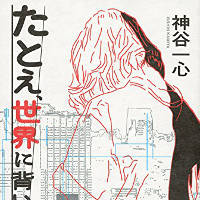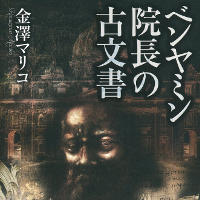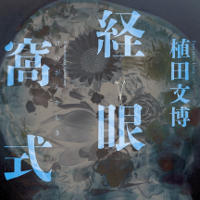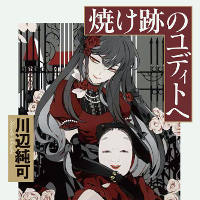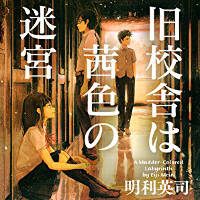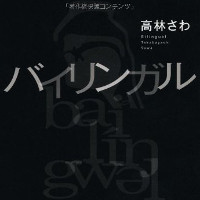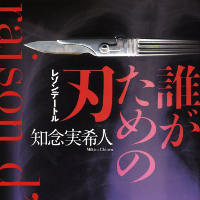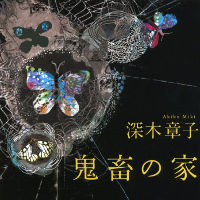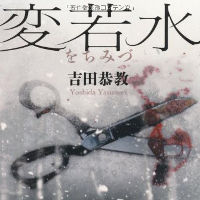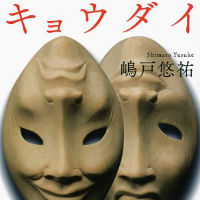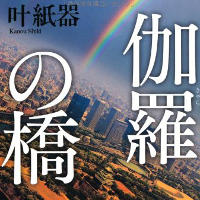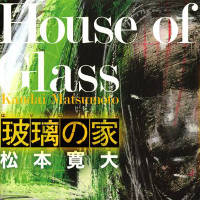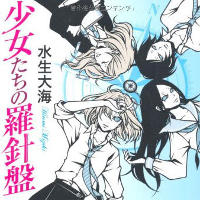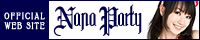北野天満宮の青紅葉と鬼切丸

こんにちわ!
管理人のウイスキーぼんぼんです。
休日を利用して紅葉狩りに行ってきました。
紅葉と言っても「青紅葉」というやつで、初夏の今頃見頃を迎えます。
場所は京都の北野天満宮で、境内西側の御土居が期間限定で開放されています。
京都は秋の紅葉狩りでは観光客でごった返すのですが、この青紅葉狩りのシーズンは(GWを除けば)観光客は控えめです。


刀剣乱舞ONLINE「髭切」
また同時開催のイベントとして「学問の神・驚きの宝刀展」が行われており、宝物殿にて名刀「鬼切丸(髭切)」が展示されていました。
こちらへも足を運んでみることにします。

楼門
三光門
この日は修学旅行生が多く、境内は学生さんでごった返していました。
青紅葉を見に行く前にわたしも学生にならって境内を散策です。

大黒天の燈籠
三光門をくぐる前に右手に折れると、大黒天の燈籠があります。
この大黒様の口に小石をのせて落ちなければ、その小石を財布に入れて祈るとお金に困らないといわれています。
また「落ちない」ことから、昨今は受験生も験を担ぐため、小石を乗っけるようになっているのだとか。
わたしもお金に困らないように欲張ってたくさんぽいぽいっと小石を乗っけてみたのでした。

三光門の「月の彫刻」
三光門の「日の彫刻」
三光門の向こうに本殿があるため、さささっと門をくぐってしまいがちなのですが、この三光門でも足を止めてみることをおすすめします。
門の中で上を見上げると「月の彫刻」と「日の彫刻」を見ることが出来ます。
「三光門」の「三光」というのは、月・日・星のことなのですが、門には月と日の彫刻しかありません。なぜ星の彫刻が施されなかったのかは諸説あるようなのですが、この三光門の北側上空にちょうど北極星が浮かぶためで、あえて門には彫刻を施していないというらしいのです。

本殿
御土居
本殿で手を合わせた後は、もみじ苑へと向かいます。
本殿のある場所から西へ行くとも受付があり、大人一人500円でもみじ苑に入ることが出来ます。
この500円は宝刀展との共通チケットのため、ここでお金を払っておけば境内東側の宝物殿には追加料金無しで入れます。



この御土居には紙屋川という小川が流れていて、そこには鶯橋という朱色の橋がかかっています。
青紅葉の緑色とこの鶯橋の朱色が良い感じで対比になっていて映えています。


生憎の曇天で、小雨もパラパラと降ったり降らなかったりだったのですが、静寂を湛えた雰囲気が増して、晴れた日とはまた違った表示がありました。



一雨来そうだったので、ひとしきり見終わった後は宝物殿のほうへと退避です。
+++++

宝物殿
「学問の神・驚きの宝刀展」は境内東側の宝物殿で行われています。
刀剣乱舞の影響のためか、女性のお客さんが多くいました。

館内に入ってまず注意されたのが、スマホやケータイでの写真撮影はOKだけど、眼レフなどのカメラでの撮影はNGだということです。
なんでも修学旅行生が多いため、彼らのためにスマホやケータイでの撮影は許可しているのだとか。しかし大人の我々でもスマホやケータイでの撮影は可能です。

鬼切丸
ありました!
鬼切丸です!
髭切とも呼ばれていたそうで、罪人の首をはねた際に髭まで断つ切れ味の鋭さからそう呼ばれたのだとか。
恐ろしいです。
と言うか、目の前にある刀が人の首をはねたという事実だけで冷や汗をかくのでした。


この宝刀展ではこの鬼切丸以外にも多くの刀が展示されていました。
菅原道真公の霊験で力を封じようと収められた魔剣や妖刀もあります。
そもそも学問の神様と言われている菅原道真公には「文武」のうちの「文」のイメージが強いのですが、北野天満宮が80振もの刀剣を所蔵していて「武」の側面も持ち合わせていたのには少しびっくりしました。

「宝刀展」記念朱印帳
「鬼切丸」の焼き印入り
小洒落た彫刻
わたしの中で北野天満宮のイメージが変わった!
というわけで、記念に御朱印帳を頂いて帰りました。
この宝刀展限定の御朱印帳で、木でできています。
同じ木でできた御朱印帳で高野山で頂いたものは大変良い香りがしたのですが、こちらのは香りがありませんでした。外国産の木かもしれません。

「宝刀展」記念朱印帳は1,500円、御朱印は300円です。
記念朱印帳は本殿近くの授与所でいただけるほか、宝物殿での販売しているようでした。
青紅葉狩りおよび宝刀展は5月31日まで開催です。もうすぐで終了です。
通常、こういった限定御朱印帳(しかも京都)は、ツイッターなどを見ているとすぐに売り切れてしまうようなのですが、御朱印帳もまだまだ在庫があるようでした。
欲しい方は急ぎましょう。御朱印帳の在庫より、会期に注意したほうが良いかもしれません。
【関連リンク】
 もみじ苑・宝物殿 特別同時公開 | 北野天満宮
もみじ苑・宝物殿 特別同時公開 | 北野天満宮http://kitanotenmangu.or.jp/lp_5.php
≪胡傑「ぼくは漫画大王」 | HOME | 綾辻行人ほか「自薦 THE どんでん返し」≫
コメントの投稿
スポンサードリンク
プロフィール
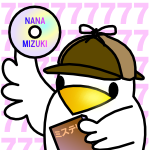
Author:ウイスキーぼんぼん
初めて読んだミステリは『そして扉が閉ざされた』(岡嶋二人)。以来ミステリにどっぷりハマリ中。
「SUPER GENERATION」で水樹奈々さんに興味を持ち「Astrogation」で完全にハマる。水樹奈々オフィシャルファンクラブ「S.C. NANA NET」会員。
◆YouTubeチャンネル(NEW!)
◆Twitter
◆食べログ
◆FC2プロフへ
◆mixi(放置中)
好きな推理作家:島田荘司ゴッド
(嫁本:アトポス)
好きな歌手:水樹奈々ちゃん
(嫁曲:SUPER GENERATION)
誕生日:ヘレン・マクロイとおなじ
体型:金田一耕助とおなじ
本年度のお気に入り(国内)
新本格30周年!
2016年11月~2017年10月発売の熱い本格ミステリ!
本年度のお気に入り(海外)
2015年11月~2016年10月発売の熱い翻訳ミステリ!
御朱印巡り
集めた御朱印です。
(各都道府県参拝した順)
※記事に出来ていない寺社多数です!鋭意執筆中!
※リンクが切れているものは下書き状態です。しばらくしたら公開されます。
(各都道府県参拝した順)
※記事に出来ていない寺社多数です!鋭意執筆中!
※リンクが切れているものは下書き状態です。しばらくしたら公開されます。
【東京】
・靖國神社(その1)
・靖國神社(その2)
・東京大神宮
・浅草寺 御本尊
・浅草寺 浅草名所七福神
・浅草神社
・浅草神社 浅草名所七福神
・今戸神社
・明治神宮(その1)
・明治神宮(その2)
・増上寺
・烏森神社
・神田明神
・乃木神社
・上野東照宮
・波除稲荷神社
・富岡八幡宮
【神奈川】
・鶴岡八幡宮
・建長寺
・高徳院(鎌倉大仏殿)
・長谷寺
【愛知】
・熱田神宮
・一之御前神社、別宮八剣宮
・真清田神社
・大神神社
・大須観音
【大阪】
・大阪天満宮
・豊國神社
・四天王寺
・住吉大社
・坐摩神社
・法善寺
・難波八阪神社
・道明寺天満宮
・一心寺
・安居神社
・生國魂神社
・生國魂神社 干支(申)
・生國魂神社 干支(酉)
・生國魂神社 干支(戌)
・生國魂神社 干支(亥)
・生國魂神社 干支(子)
・生國魂神社 干支(丑)
・三光神社
・玉造稲荷神社
・今宮戎神社
・方違神社
・難波神社
・露天神社(お初天神)
・太融寺
・大鳥大社
・石切劔箭神社
・枚岡神社
・慈眼寺
・久安寺
・多治速比売神社
【京都】
・鈴虫寺(その1)
・鈴虫寺(その2)
・鈴虫寺(その3)
・松尾大社(その1)
・月読神社
・天龍寺
・御髪神社
・常寂光寺
・二尊院
・野宮神社
・下鴨神社(賀茂御祖神社)
・河合神社(下鴨神社摂社)
・盧山寺
・梨木神社
・白雲神社
・護王神社
・御霊神社
・下御霊神社
・平安神宮
・銀閣寺(慈照寺)
・金閣寺(鹿苑寺)
・龍安寺
・八坂神社
・八坂神社 美御前社
・八坂神社 又旅社
・八坂神社 冠者殿社
・八坂神社 青龍
・八坂神社 祇園御霊会
・伏見稲荷大社 本殿
・伏見稲荷大社 奥社奉拝所
・伏見稲荷大社 御膳谷奉拝所
・三十三間堂
・養源院
・東福寺
・建仁寺
・南禅寺(その1)
・南禅寺(その2)
・永観堂(禅林寺)
・北野天満宮
・北野天満宮 宝刀展限定「鬼切丸」
・大将軍八神社
・法輪寺(達磨寺)
・妙心寺
・妙心寺 退蔵院
・仁和寺
・建勲神社
・晴明神社
・御金神社
・八大神社
・豊国神社
・由岐神社
・鞍馬寺
・貴船神社
・六道珍皇寺
・六道珍皇寺 六道まいり
・六波羅蜜寺 都七福神
・安井金比羅宮
・知恩院 徳川家康公四百回忌
・青蓮院門跡
・青蓮院門跡 近畿三十六不動尊霊場
・粟田神社
・鍛冶神社(粟田神社末社)
・東寺
・上賀茂神社(賀茂別雷神社)
・大徳寺 本坊
・大徳寺 高桐院
・今宮神社
・妙顯寺
・三千院 御本尊
・三千院 西国薬師四十九霊場第四十五番
・三千院 聖観音
・実光院
・勝林院
・宝泉院
・寂光院
・宝厳院
・大覚寺
・清涼寺
・祇王寺
・化野念仏寺
・落柿舎
・城南宮
・飛行神社
・石清水八幡宮
・岡崎神社
・長岡天満宮
・平野神社
・法金剛院
・高台寺
・清水寺
・清水寺(西国三十三所草創1300年記念)
・宝蔵寺 阿弥陀如来
・宝蔵寺 伊藤若冲
・勝林寺
・平等院 鳳凰堂
・宇治神社
・宇治上神社
・智恩寺
・元伊勢籠神社
・眞名井神社
・梅宮大社
・錦天満宮
・藤森神社(あじさい祭り限定)
・智積院
・御香宮神社
・神護寺
・西明寺
・高山寺
・大豊神社
・三室戸寺
・吉祥院天満宮
【奈良】
・唐招提寺
・薬師寺 御本尊
・薬師寺 玄奘三蔵
・薬師寺 吉祥天女
・薬師寺 水煙降臨
・東大寺 大仏殿
・東大寺 華厳
・東大寺 二月堂
・春日大社 ノーマル
・春日大社 第六十次式年造替
・興福寺 今興福力
・興福寺 南円堂
・如意輪寺
・吉水神社
・勝手神社
・金峯山寺
・吉野水分神社
・金峯神社
・法隆寺
・法隆寺 西円堂
・中宮寺
・法輪寺
・法起寺
・元興寺
・橿原神宮
・橘寺
・飛鳥寺
・飛鳥坐神社
・般若寺
【和歌山】
・金剛峯寺
・金剛峯寺 六波羅蜜
・高野山 金堂・根本大塔
・高野山 奥之院
・高野山 女人堂
・高野山 徳川家霊台
・高野山 南院(波切不動尊)
・熊野那智大社
・青岸渡寺
・飛瀧神社
・伊太祁曽神社
・國懸神宮
・紀三井寺
【滋賀】
・比叡山延暦寺 文殊楼
・比叡山延暦寺 根本中堂
・比叡山延暦寺 大講堂
・比叡山延暦寺 阿弥陀堂
・比叡山延暦寺 法華総持院東塔
・比叡山延暦寺 釈迦堂
・比叡山延暦寺 横川中堂
・比叡山延暦寺 四季講堂(元三大師堂)
・三尾神社
・三井寺 金堂
・三井寺 黄不動明王
・近江神宮
・滋賀縣護國神社
【兵庫】
・生田神社
・廣田神社
・西宮神社
・湊川神社
・走水神社
・千姫天満宮
・男山八幡宮
・水尾神社
・兵庫縣姫路護國神社
・播磨国総社 射楯兵主神社
・甲子園素盞嗚神社
・北野天満神社
【岡山】
・吉備津神社
・吉備津彦神社
【鳥取】
・白兎神社
・宇倍神社
・聖神社
・鳥取東照宮(樗谿神社)
【広島】
・吉備津神社
・素盞嗚神社
・草戸稲荷神社
・明王院
・出雲大社 福山分社
・沼名前神社(鞆祇園宮)
・福禅寺(対潮楼)
・厳島神社
・大願寺
・千光寺
・艮神社
【徳島】
・大麻比古神社
【福岡】
・太宰府天満宮
・筥崎宮(筥崎八幡宮)
・住吉神社
【沖縄】
・波上宮
■朱印帳■
・京都五社めぐり
・高野山 開創1200年記念霊木朱印帳
・平安神宮 御朱印帳
・全国一の宮御朱印帳
・住吉大社 御朱印帳
・建仁寺 御朱印帳
・今戸神社 御朱印帳
・大将軍八神社 御朱印帳
・晴明神社 御朱印帳
・東寺 御朱印帳
・明治神宮 御朱印帳
・大阪市交通局 オオサカご利益めぐり御朱印帳
・北野天満宮「宝刀展」記念朱印帳
・熊野那智大社 御朱印帳
最新のつぶやき
2016年の水樹奈々さん
ハーイ!ハーイ!
ハイ!ハイ!ハイ!ハイ!
ばらのまち福山ミステリー文学新人賞
本格ファンよ瞠目せよ。
これがばらのまち福山ミステリー文学新人賞だ!
これがばらのまち福山ミステリー文学新人賞だ!
神との邂逅
参加した水樹奈々さんのライブのレポ
(※工事中)
09/08 NMLE19静岡公演2日目追加。
(※工事中)
09/08 NMLE19静岡公演2日目追加。

2010.02.10
NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010
新居浜公演

2011.01.23
NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-
(2日目)

2011.06.25
NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011
愛媛公演

2011.10.15
アカガネマリン・ミュージックフェスティバル

2011.12.03
NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011
QUEEN'S NIGHT

2012.06.24
NANA MIZUKI LIVE UNION 2012
島根公演

2012.07.15
NANA MIZUKI LIVE UNION 2012
大阪公演(1日目)

2012.08.11
NANA MIZUKI LIVE UNION 2012
長崎公演
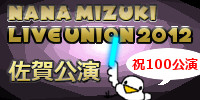
2012.08.12
NANA MIZUKI LIVE UNION 2012
佐賀公演
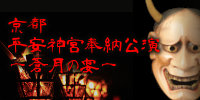
2012.09.23
平安神宮奉納公演
~蒼月の宴~

2013.01.19
NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013
-OPUS Ⅱ-
(1日目)

2013.07.07
NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013
愛媛公演

2013.07.14
NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013
大阪公演(1日目)

2013.11.23
NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013 +
台湾公演(1日目)
→ファンクラブツアー11月22日編
→ライブ1日目編

2013.11.24
NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013 +
台湾公演(2日目)
ライブビューイング
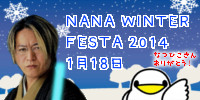
2014.01.18
NANA WINTER FESTA 2014

2014.04.26
『SUPERNAL LIBERTY』
発売記念握手会

2014.06.21
NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014
福岡公演(1日目)

2014.06.22
NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014
福岡公演(2日目)

2014.07.11
NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014
大阪公演(1日目)

2014.07.12
NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014
大阪公演(2日目)

2014.07.20
NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014
香川公演

2014.09.27
NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014 +
シンガポール公演
ライブビューイング

2014.10.04
NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014 +
台湾公演(1日目)
→渡台編
→ライブ編
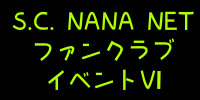
2015.04.25
ファンクラブイベントVI

2015.07.11
NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
大阪公演(1日目)
→物販・衣装展編
→ライブ編

2015.07.12
NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
大阪公演(2日目)
→物販編
→ライブ編

2015.08.23
NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
滋賀公演(※物販のみ)

2015.09.05
NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
鳥取公演

2015.09.12
NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
徳島公演

2016.09.22
NANA MIZUKI LIVE PARK 2016
阪神甲子園球場
→物販・衣装展編
→ライブ編

2017.01.07
NANA MIZUKI LIVE ZIPANGU 2017
愛知公演(1日目)

2017.01.08
NANA MIZUKI LIVE ZIPANGU 2017
愛知公演(2日目)

2017.01.21
NANA MIZUKI LIVE ZIPANGU 2017
大阪公演(1日目)

2017.03.04
NANA MIZUKI LIVE ZIPANGU 2017
沖縄公演

2017.08.15
ミュージカル「ビューティフル」

2018.01.20
NANA MIZUKI LIVE GATE 2018
6日目

2018.01.21
NANA MIZUKI LIVE GATE 2018
7日目
ライブビューイング

2018.07.07
NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018
大阪公演(1日目)

2018.07.08
NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018
大阪公演(2日目)
※工事中

2018.07.21
NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018
広島公演

2019.01.19
NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019
-OPUS Ⅲ-
(1日目)

2019.03.23
NANA MUSIC LABORATORY 2019
~ナナラボ~
夜の部

2019.05.05
水樹奈々大いに唄う 伍
(ライブビューイング)

2019.07.21
NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019
京都公演(2日目)
(※物販のみ)

2019.08.03
NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019
香川公演

2019.08.24
NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019
静岡公演(1日目)

2019.08.25
NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019
静岡公演(2日目)

2020.11.07
NANA ACOUSTIC ONLINE
ブログ内検索
私的年間ベスト5
これは原書房『本格ミステリ・ベスト10』ほか、各誌のネット読者ランキングへ投票したものです。各年度のお気に入りは大体こんな感じ。
※予想ではありません
※予想ではありません
2013本格ミステリ・ベスト10
1「誰がための刃 レゾンデートル」2「アルカトラズ幻想」
3「聴き屋の芸術学部祭」
4「体育館の殺人」
5「江神二郎の洞察」
(→詳しくはこちら)
2012本格ミステリ・ベスト10
1「進々堂世界一周 追憶のカシュガル」2「鬼畜の家」
3「キョウダイ」
4「檻の中の少女」
5「変若水」
(→詳しくはこちら)
2011本格ミステリ・ベスト10
1「METAL GEAR SOLID PEACE WALKER」2「伽羅の橋」
3「貴族探偵」
4「写楽 閉じた国の幻」
5「探偵小説のためのゴシック「火剋金」」
(→詳しくはこちら)
2010本格ミステリ・ベスト10
1「玻璃の家」2「少女たちの羅針盤」
3「六つの手掛り」
4「密室殺人ゲーム2.0」
5「智天使の不思議」
(→詳しくはこちら)
2009本格ミステリ・ベスト10
1「青銅の悲劇 瀕死の王」2「ラットマン」
3「完全恋愛」
4「パラダイス・クローズド」
5「犯罪ホロスコープⅠ」
(→詳しくはこちら)
2008本格ミステリ・ベスト10
1「天帝のつかわせる御矢」2「首無の如き祟るもの」
3「女王国の城」
4「密室キングダム」
5「密室殺人ゲーム王手飛車取り」
(→詳しくはこちら)
このミス あなたが選ぶベスト・オブ・ベスト
1「二の悲劇」国内 2「翼ある闇」 3「双頭の悪魔」 4「絡新婦の理」 5「人狼城の恐怖 第四部完結編」 6「ミステリーズ」 海外
1「ある詩人への挽歌」2「第二の銃声」 3「ジャンピング・ジェニイ」 4「猿来たりなば」 5「衣装戸棚の女」 6「歌うダイアモンド」 『このミス』の刊行20周年を記念して行われた、過去19年間のランキング。 |
2007本格ミステリ・ベスト10
1「厭魅の如き憑くもの」2「邪魅の雫」
3「骸の爪」
4「翼とざして」
5「九杯目には早すぎる」
(→詳しくはこちら)
オールベストランキング
1「紅楼夢の殺人」2「ミステリ・オペラ」 3「イニシエーション・ラブ」 4「絡新婦の理」 5「メルカトルと美袋のための殺人」 (→詳しくはこちら) 『本格ミステリ・ベスト10』の刊行10周年を記念して行われた、過去10年間のランキング |
2006本格ミステリ・ベスト10
1「モーダルな事象」2「ゴーレムの檻」
3「ニッポン硬貨の謎」
4「痙攣的」
5「誰のための綾織」
(→詳しくはこちら)
2005本格ミステリ・ベスト10
1「紅楼夢の殺人」2「螢」
3「龍臥亭幻想」
4「星の牢獄」
5「大相撲殺人事件」
2004本格ミステリ・ベスト10
1「林真紅郎と五つの謎」2「スイス時計の謎」
3「ミステリアス学園」
4「『アリス・ミラー城』殺人事件」
5「葉桜の季節に君を想うということ」
2003本格ミステリ・ベスト10
1「オイディプス症候群」2「鏡の中は日曜日」
3「法月綸太郎の功績」
4「世界の終わり、あるいは始まり」
5「クビキリサイクル」
スポンサードリンク
月別アーカイブ
リンク
RSSフィード
Powered By FC2ブログ