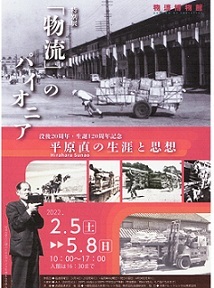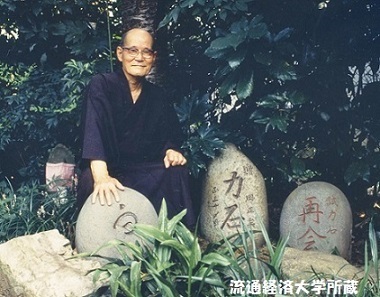傷の上に傷 …㉞
田畑修一郎2
術後7日目。
膀胱に差しこまれたままだったバルーンカテーテルが取り除かれた。
すごい身軽になった。
便座に座って自力でおしっこを出すのが嬉しくてたまらない。
「人間らしさ」って、誰の手も借りずに一人でおしっこが出来ることだって、
そのとき思った。
その日私は医師から、術後の私の本当の姿を告げられた。
「手術で膀胱を支える神経や筋肉を切ったので、
これからは意識的におしっこを出してください」
そんなことは聞いていなかった。
膀胱はお腹の中でぶらぶらしている状態だから、
尿意も残尿感も感じなくなるのだと医者は言い、
「これからは時間を計って尿量を記録してください」と。
自分の膀胱がお腹の中で、宙ぶらりんになってしまうなんて。
それに意識的におしっこを出すって、どういうことなの?
私は無残な気持ちになった。

斎藤氏撮影
手術の傷は思っていた以上に大きかった。
傷はへその脇から一番下まで一直線に刻まれ、のちにケロイドになった。
後年、初めて参加した旧街道を歩くグループと宿に泊まった時のこと。
風呂から上がって部屋へ入った時、さっきまで洗い場で隣りにいたおばさんが、
「ねえねえ、今ねぇ、隣りにお腹にすごい傷がある人がいてサア」
と、大ニュースのように仲間たちに大声で知らせていた。
「それ、私ですが…」と言うと、
部屋にいたみんなが気まずい顔でそっぽを向いた。
それまで私は自分が手術をしたことを忘れていたし、
傷も恥ずかしくはなかったから、どこでも普通に振る舞っていた。
だが、世間はそうではないことをこの一件で悟った。

斎藤氏撮影
あのときの街道歩きの人たちは60,70という中高齢者ばかりだった。
それでもいじめに走る。
いじめは翌朝にも発生した。
朝起きたら、
洗面所に置いていた洗面用具や化粧品が私のものだけ消えていた。
「誰がやったんですか!」と思わず大声を出したら、みんな一斉に俯いた。
わずか5、6人しかいないのに知らないわけがない。
「なんでこんなことを」と詰問したら、その中の一人がしぶしぶ、
「これ使ってください」と、予備に持ってきたという歯ブラシを差し出した。
その日、宿にはこのグループの男女しかいなかったし、
第一、洗面所は部屋の中にあったから、
あきらかに共謀しての新参者いじめだったのだろう。
とうとう私の洗面用具は出てこなかったから、どこかへ捨てたのだろう。
いろんなグループに参加したが、こんな陰湿な会は初めてだった。
翌日、ほかの仲間とは年の離れた若い女性がすきを見て声をかけてきた。
「夕べのお風呂場の件、あの人、わざとあなたの隣りに座ったんですよ」
そのうちいじめの原因がわかってきた。

斎藤氏撮影
昭和53年4月、
静岡県体育文化協会が一般公募した高校生を含む素人約30名を、
職員が一人で、ザイルもアイゼンも持たず雪の八ヶ岳へ連れて行き、
27歳の女性を滑落死させる遭難事故を起こした。
参加者のほとんどはハイキング経験しかない軽装だったという。
「リーダーは何をしていたか」の著者・本田勝一は、本の中でこう書いている。
「運転免許を持たない運転手が事故を起こした」
それから20数年後に私が参加したこのグループが、
まさにその職員と関係者たちだったのだ。
遺族が起こした裁判で、職員は「自己責任」を主張したが、
市岳連が「無謀登山」と断罪。勝訴に導いた。
その市岳連傘下の山岳会に私が所属していたことで、恨みがぶり返し、
さらに、私が登山の本を書きテレビや新聞に出ていたことや、
新聞社で働いていることで、先手を打っていやがらせを仕掛けてきたのだという。
初対面のあと、グループの女性の一人が私を陰に呼んで、
「あんた、体文協のこと、どれだけ知ってる?」
と探りを入れてきたのは、何かを警戒してのことだったのだろう。
このときも、このリーダーは道に迷った。
なんと、地図が読めなかった。
「驚かれたでしょう? この会はよく道に迷うのよ」と、
今朝、お風呂場の一件を告げた女性がこっそり耳打ちしてきた。

斎藤氏撮影
受難はその後も続いた。
街道歩きから帰って間もなく、
友人と入ったパスタ屋で大はしゃぎの一団を見て、私は目を疑った。
その一団はあの街道歩きのおばさんたちで、
その中に見知った顔があったからだ。
それは私と同じ住宅地に住む老年の女性で、この会へ参加を申し込んだとき、
「あなたと同じところにこういう人がいますよ」と知らされたので挨拶したら、
鋭い目つきで、
「私は関係ありません。入ってすぐ退会したから知り合いもいません」と。
そう言ったその人が
輪の中心にいて、いじめの報告を聞いて手を叩いて笑っていたのだ。
いじめの発案者はこの人だったのだろうか。
私には初対面の老女だったが、この人は私を知っていた。
同じ山歩きをする者なのに、目立つ動きをする私が気に食わなかったのだろう。
高山のガレ場にひっそりと逞しく咲く「こまくさ」

嫌がらせはその後もしつこく続いた。
この会の会費は半年分前払いというので支払った。
一回で懲りて退会したのに、半年後、次の会費を払えと矢の催促。
どういうグループかも調べないまま参加した私のミスかもしれない。
しかし事故から20数年後も、名前を変えて活動しているとは思いもしなかった。
信奉するリーダーを中心にほんの10人余りが、何かの秘密結社のように固まって。
それなのになぜ、公募などしていたのだろう。
あの若い女性が「新しく入ってもみんなすぐやめてしまう」と言っていたから、
いじめは私だけではなかったのだが、
私は傷の上にさらに傷を負わされた。
人の心の醜さにゾッとした。

にほんブログ村

膀胱に差しこまれたままだったバルーンカテーテルが取り除かれた。
すごい身軽になった。
便座に座って自力でおしっこを出すのが嬉しくてたまらない。
「人間らしさ」って、誰の手も借りずに一人でおしっこが出来ることだって、
そのとき思った。
その日私は医師から、術後の私の本当の姿を告げられた。
「手術で膀胱を支える神経や筋肉を切ったので、
これからは意識的におしっこを出してください」
そんなことは聞いていなかった。
膀胱はお腹の中でぶらぶらしている状態だから、
尿意も残尿感も感じなくなるのだと医者は言い、
「これからは時間を計って尿量を記録してください」と。
自分の膀胱がお腹の中で、宙ぶらりんになってしまうなんて。
それに意識的におしっこを出すって、どういうことなの?
私は無残な気持ちになった。

斎藤氏撮影
手術の傷は思っていた以上に大きかった。
傷はへその脇から一番下まで一直線に刻まれ、のちにケロイドになった。
後年、初めて参加した旧街道を歩くグループと宿に泊まった時のこと。
風呂から上がって部屋へ入った時、さっきまで洗い場で隣りにいたおばさんが、
「ねえねえ、今ねぇ、隣りにお腹にすごい傷がある人がいてサア」
と、大ニュースのように仲間たちに大声で知らせていた。
「それ、私ですが…」と言うと、
部屋にいたみんなが気まずい顔でそっぽを向いた。
それまで私は自分が手術をしたことを忘れていたし、
傷も恥ずかしくはなかったから、どこでも普通に振る舞っていた。
だが、世間はそうではないことをこの一件で悟った。

斎藤氏撮影
あのときの街道歩きの人たちは60,70という中高齢者ばかりだった。
それでもいじめに走る。
いじめは翌朝にも発生した。
朝起きたら、
洗面所に置いていた洗面用具や化粧品が私のものだけ消えていた。
「誰がやったんですか!」と思わず大声を出したら、みんな一斉に俯いた。
わずか5、6人しかいないのに知らないわけがない。
「なんでこんなことを」と詰問したら、その中の一人がしぶしぶ、
「これ使ってください」と、予備に持ってきたという歯ブラシを差し出した。
その日、宿にはこのグループの男女しかいなかったし、
第一、洗面所は部屋の中にあったから、
あきらかに共謀しての新参者いじめだったのだろう。
とうとう私の洗面用具は出てこなかったから、どこかへ捨てたのだろう。
いろんなグループに参加したが、こんな陰湿な会は初めてだった。
翌日、ほかの仲間とは年の離れた若い女性がすきを見て声をかけてきた。
「夕べのお風呂場の件、あの人、わざとあなたの隣りに座ったんですよ」
そのうちいじめの原因がわかってきた。

斎藤氏撮影
昭和53年4月、
静岡県体育文化協会が一般公募した高校生を含む素人約30名を、
職員が一人で、ザイルもアイゼンも持たず雪の八ヶ岳へ連れて行き、
27歳の女性を滑落死させる遭難事故を起こした。
参加者のほとんどはハイキング経験しかない軽装だったという。
「リーダーは何をしていたか」の著者・本田勝一は、本の中でこう書いている。
「運転免許を持たない運転手が事故を起こした」
それから20数年後に私が参加したこのグループが、
まさにその職員と関係者たちだったのだ。
遺族が起こした裁判で、職員は「自己責任」を主張したが、
市岳連が「無謀登山」と断罪。勝訴に導いた。
その市岳連傘下の山岳会に私が所属していたことで、恨みがぶり返し、
さらに、私が登山の本を書きテレビや新聞に出ていたことや、
新聞社で働いていることで、先手を打っていやがらせを仕掛けてきたのだという。
初対面のあと、グループの女性の一人が私を陰に呼んで、
「あんた、体文協のこと、どれだけ知ってる?」
と探りを入れてきたのは、何かを警戒してのことだったのだろう。
このときも、このリーダーは道に迷った。
なんと、地図が読めなかった。
「驚かれたでしょう? この会はよく道に迷うのよ」と、
今朝、お風呂場の一件を告げた女性がこっそり耳打ちしてきた。

斎藤氏撮影
受難はその後も続いた。
街道歩きから帰って間もなく、
友人と入ったパスタ屋で大はしゃぎの一団を見て、私は目を疑った。
その一団はあの街道歩きのおばさんたちで、
その中に見知った顔があったからだ。
それは私と同じ住宅地に住む老年の女性で、この会へ参加を申し込んだとき、
「あなたと同じところにこういう人がいますよ」と知らされたので挨拶したら、
鋭い目つきで、
「私は関係ありません。入ってすぐ退会したから知り合いもいません」と。
そう言ったその人が
輪の中心にいて、いじめの報告を聞いて手を叩いて笑っていたのだ。
いじめの発案者はこの人だったのだろうか。
私には初対面の老女だったが、この人は私を知っていた。
同じ山歩きをする者なのに、目立つ動きをする私が気に食わなかったのだろう。
高山のガレ場にひっそりと逞しく咲く「こまくさ」

嫌がらせはその後もしつこく続いた。
この会の会費は半年分前払いというので支払った。
一回で懲りて退会したのに、半年後、次の会費を払えと矢の催促。
どういうグループかも調べないまま参加した私のミスかもしれない。
しかし事故から20数年後も、名前を変えて活動しているとは思いもしなかった。
信奉するリーダーを中心にほんの10人余りが、何かの秘密結社のように固まって。
それなのになぜ、公募などしていたのだろう。
あの若い女性が「新しく入ってもみんなすぐやめてしまう」と言っていたから、
いじめは私だけではなかったのだが、
私は傷の上にさらに傷を負わされた。
人の心の醜さにゾッとした。
にほんブログ村











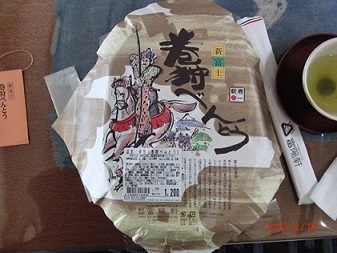









 ーーーーー
ーーーーー