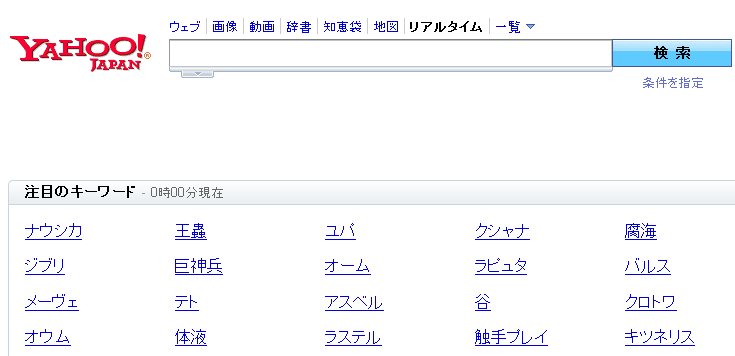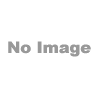市場で値踏みされるのは労働者の側だけではない
若い世代でネガティブな労働観が増えている! - ダイヤモンド・オンライン
「会社」や「労働」はそれの持つ内容を表さない。一言で「会社」「労働」と言っても、其々にとってのそれらとの関係や内容は、全て異なる。もし仮に「会社嫌い」や「労働嫌い」が多くの者に広がっているとすれば、それは労働市場において多くの者に忌み嫌われるような会社及び労働条件が溢れかえっていることを意味する。「労働というのは、ストレスと時間とをお金に換えている」と考えるのは、思想のせいではない。実際にその者が携わっている労働との関係が、取引でストレスを金に代えること以外に意義を見出すことができないような内容を持っているからだ。藤野 私は、明治大学でベンチャー・ファイナンスの授業をやっています。そこで感じることなんですが、日本の大学生は最近、すごく保守的になっていて、海外に出ていくどころか、ベンチャー企業や小さい企業よりも大企業に就職したい、さらには地方公務員になりたいという志向が強まっています。
その背景には、「会社嫌い」、さらには「労働嫌い」の思想が広まっていると思うんです。「働くことによる社会的な充足感」をすごく否定する雰囲気が広がっている。なるべく働かない方がいいという……。(中略)
僕が言っているのは、一所懸命働くことを是とする会社を、一律に「ブラック企業」とか呼ぶ風潮に対する疑問です。それは、「労働というのは、ストレスと時間とをお金に換えている」というような考え方であって、今、こうした労働に対するすごくネガティブな価値観が急速に広がっている気がするんです。
これって、ものすごく古びたマルクス主義じゃないですか。資本者家がいて、労働者を搾取しているという価値観。働くということは、時間とストレスの代償としてお金をもらうことだから、なるべく労働時間は少ないほうがいいし、残業はない方がいい。でも、そうした考えの人は、働くことの充足感があまりないんです。
逆に言えば、「会社嫌い」や「労働嫌い」の思想を持っている人間でも、それらが持つ内容が内容であれば、それに好印象を抱く可能性もある。よって、「会社嫌い」や「労働嫌い」を口にする者は、会社や労働という概念そのものを嫌っていると言うより、自らが関わってきたそれらや、今現在における趨勢としてのそれらの在り様に嫌悪感を抱いていると考えた方が妥当だろう。
このことを理解できていないからこういう発言が出てくる。其々にとって「働くこと」は其々別の内容を持っている。そして「充足感」はあくまでそこから導き出された個人の感覚でしかない。だからそれを他人に伝達することはできない。そして、彼らは変に理論武装していて、こちらが働くことの充足感を伝えようとすると、「資本主義をうまく働かせるために、そういう幻想を振りまこうとしているんだ」と反論してくる。
其々にとっての会社や労働の価値判断は、それらがその者の人生の中でどのような位置を占めているかという背景によっても変わってくる。そういう留意点はあるにせよ、基本的に「働くことの充足感」を教えるには、其々にとってそれを感じさせるような労働環境を提供することでしか叶わない。よって、より多くの人間に「働くことの充足感」を感じてもらうためには、市場にそういった労働環境がより多く出回るようにするしかない。それを思想の押し付けで達成しようとするのは無理がある。
それに、この論者は学生の理論による反論に不平不満を漏らしているが、自然科学の授業ではないのだから、お互いの理論をぶつけ合ってこそ大学の授業と言えるのではないか。理論での反論を否定し、自身の個人的感覚に正当性を依拠した思想を一方的に押し付けるのは、講師が大学でやるべき仕事ではないはずだ。
▼自由市場への称揚と非難のダブスタから生まれる自意識批判
しかしこの記事でなされている何より大きな勘違いは、会社は労働者側を一方的に値踏みする側だと錯誤していることだ。終身雇用が崩壊した現在において、会社は労働者にとって単なる取引相手でしかない。そこでは会社が労働者を値踏みするように、会社もまた労働者から値踏みされる。市場とはそういうものだ。そして、多くの日本人、取り分け経営者達は、自由市場を機軸とした資本主義を称揚し、市場をより自由化すべきであると唱え続けてきたのではないか。
だが、「ベンチャー企業や小さい企業よりも大企業に就職したい、さらには地方公務員になりたいという志向が強まってい」るとすれば、それもまた市場によって導き出された一つの評価であると言える。この人物が言うところの「一所懸命働くことを是とする会社」が何故ブラック企業と言われるかと言えば、それはそれらがなるべくなら忌避したい、粗悪な取引相手だと市場で判断されているからだ。
人は労働のために労働をするのではない。多くの者はただ単に自身の社会的ポジションを維持するためにそれをしているにすぎない。労働にそれ以上の特別な意味を見出すか否かは、信仰の領域での話しだ。よって、(信仰の自由を重んじるなら)自身のそれを他人に押し付けたり、他人のそれを否定したりすべきではない。消費者のニーズや評価に関係なく、独善的に一所懸命に技術開発に打ち込んで、自己満足な高技術テレビを実現すればそれでいいと思ってるんだろうかと驚きました。
そして今、市場において多くの会社が「“労働者”のニーズや評価に関係なく、独善的に一所懸命に“自身の自己実現の押し付け”に打ち込んで、自己満足な“会社運営”を実現すればそれでいいと思ってるんだろうか」と煙たがられているわけだ。そういった市場の動向に対し、この者達は不満を漏らしている。だが自由市場であるなら、会社が労働者側から値踏みされることは避けられない。
つまり、この記事でなされているそれは、自由市場を機軸とする資本主義そのものへの不満なのだ。しかし一方で、「より自由な市場」を大儀として持ち出すことで得られるであろう政治的効果は手放したくない。その結果その不満は、労働者(及び潜在的なそれ)に対する自意識批判という歪んだ形で表れることになる。それがこの手の言説の正体だろう。
REAPER:センドで共有したリバーブ直前でのパートごと調整
-------------------------------
- リバーブの送り元となるトラックの一番後ろに調整に必要なプラグインを挿し、以下のように設定する。これによって、このプラグインを経た音は当該トラックから――「JS: IX/Mixer_8xS-1xS」のような特殊なプラグインを挿さない限り――直接マスターに送られることはなくなる。

ここでは1/2チャンネルから入力して3/4チャンネルに出力する設定にしているが、出力チャンネルは空いているチャンネルなら別になんでもよい。尚、プラグインを挿す位置は「一番後ろ」としているが、これは音作りを全て済ませた後の音を調整してリバーブに送る場合の設定であり、最終的な音作りの前の段階の音を調整してリバーブに送りたい場合は、分岐させたい場所にプラグインを挿す。また、必要なら同じ設定をしたプラグインを複数挿すこともできる。
- 次に、リバーブ・トラックの側で、レシーブ設定を(この例の場合)3/4チャンネルで受け取って1/2チャンネルで出力するよう設定する(※送り元のトラックを一端ステムなどで書き出したりすると、再びレシーブ側のチャンネル設定をし直さなければならなくなるので注意)。

これでリバーブ・トラックは、先ほど設定を済ませたプラグインの効果が反映されたサウンドを受け取るようになるので、後はそれで音を調節するだけ。パソコンがショボかったりして共有リバーブを使わざるを得ない場合でも、この方法を用いればかなりサウンド・バリエーションを広げることができるように思う。
「死にたい」は問題解決への希求×字義上の意味と感覚上の意味
----------------------------------------------
しかし、殆どの人間はそれを文字通りそのままの意味で捉える。すると、じゃあ死ねば?ということにしかならない。このように、そこで想定された文脈が読めず、言葉を文字通りそのまま受け取ってしまう者のことを巷ではアスペなどと言ったりするわけだが、この問題の場合、実に殆どの人間がアスペになってしまう。
これは、そのような問題に直面している者が極めて少数である――過去にそれに直面していた者ですら、問題が解決してしまうとそれを忘れてしまったりする――が故の現象だが、このことは、文字が持っている文脈というのは、それだけ個々人の感覚や経験に大きく依存して成り立っていることを表している。
そして、こういった感覚的趨勢からはずれた言説が内包する問題は、特に注意を促されたり深く考えたりでもしない限り、常に文脈をはずれて解釈され、時義上の意味で握りつぶされたり、面白おかしく曲解されたまま世間に流通し続けることになる。
REAPER:パラメータ・モジュレーションで内部サイドチェインを使う方法
以前、Pモジュレーションでヴォリュームを自動的に上げ下げさせ、コンプ代わりに使う方法を紹介したが、ちょっとした工夫で、Pモジュレーションにもこの内部サイドチェイン機能を持たせることができる。
- まず、何でもいいからトリガーとなるシグナルを扱うための適当なEQを挿して、以下のように設定する。

ここでは1/2チャンネルから入力して3/4チャンネルに出力する設定にしているが、出力チャンネルは空いているチャンネルなら別になんでもよい。
- 次に、各種設定(上記リンク先参照)を済ませたFreeGなどのプラグインをその後に挿し、parameter modulation画面でTrack audio channelを先ほどEQ側で設定した出力チャンネルに合わせる。これによって、当該プラグインはこのチャンネルのシグナルをトリガーとして動作することになる。

- 後は先ほど設定を済ませたEQで、反応させたくない帯域をカットするだけ。
 j
j