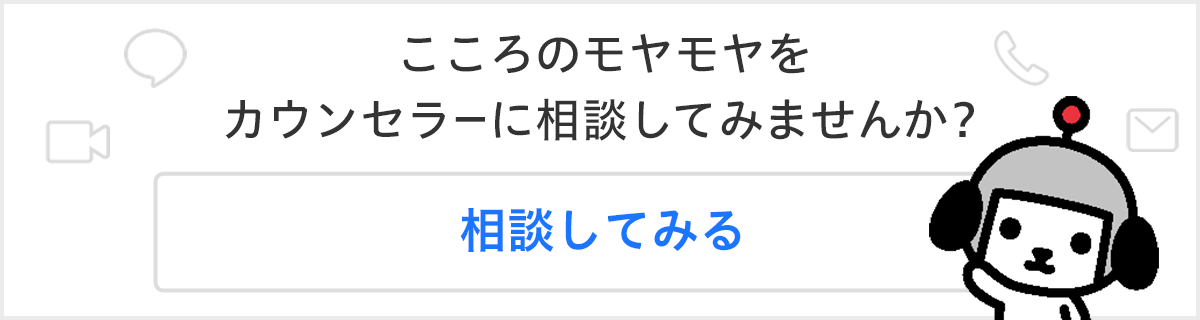回答受付終了まであと7日
回答(8件)
一般庶民じゃない、すごいお嬢様だって、みんなもちろんわかってますって。 しかし、金がどれだけあろうと、身分としては平民なんです。 日本もそうでしたが、どこの国の王室・皇室も、相手の身分にこだわるのが普通です。 相手もロイヤルか貴族でなければいけなくて、貴族であっても格を規定していて「プリンセスの称号を持たない、伯爵家の子女なんぞと結婚してはいけない」とする国もありました。 そういうのが標準だったので、いかにお嬢様であっても平民を選ばれたことに、びっくらこいたんです。 イギリスのキャサリン妃も同じです。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
大正7年(1918)、原敬が総理大臣に就任すると「平民宰相」として国民的な人気を博すことになりました。爵位をもたない、つまり華族という特権階級でない人物の総理就任は憲政史上はじめてのことで、大正デモクラシーを象徴する出来事でした。 とはいえ、原敬は盛岡藩の家老を務めた家柄の出で、じゅうぶん上流階級であったといえます。 美智子上皇后もおなじことです。ご実家は裕福ですが、華族の家柄ではありません。 そもそも明治17年に家族制度が創設されるにあたり、華族には2つの役割が与えられました。 1つは、近い将来開設される国会において、選挙で選ばれる衆議院に対抗するための貴族院の構成員、もう1つは皇室の藩屏、つまり自らが盾となって皇室を守るという約目です。 旧皇室典範には「皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅旨ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル」、つまり皇族は同族(宮家)もしくは天皇の許しを得た華族としか結婚ができませんでした。 べつに皇室典範に規定されなくとも、日本の歴史において宮家、摂家、将軍家以外の出自の皇后などいません。 ですから、裕福であるといっても公家でも大名家でもない家の娘が天皇家に嫁入りするなどというのは、歴史上はじめての、驚天動地の出来事だったのです。
当時、平民とは なかば差別用語でした。 上皇夫妻が結婚した1960年代の日本には、いまだに、皇族、華族、士族といった身分制度を意識する人々が多く、実家にオカネがあっても、これらに属さない「平民」からお妃が 選ばれたことがショックだったのです。 天皇家ともなると、「いくつかの世代を遡れば、共通の先祖があるというある意味、貴族階級内同士の婚姻でなければいけない」という「常識」が、当時の世間には存在しました。だから、日清製粉のオーナーという裕福な階層であっても「粉屋の娘が皇太子の妃になる」ことへの嫌悪が話題になったのです。 現実に、上皇の弟宮さんの相手は 平民の出身ではなくなりました。 子孫を作る相手は、別に「妃でなくてもよい」という意識がまだありました。明治天皇からして・・・・ 婚姻相手の出自階層や職業をいえば、今上天皇、きょうだいの ほうが問題になるでしょうが、90年代になるとそんな声は聞こえません。 だから皇族の婚姻相手は、どんどん広がります。 この次は、外国人でもいいのでは煮でしょうか?