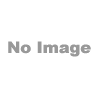2020/10/31
ホント、「空母いぶき」でも「この手の現実見えない奴が色々足を引っ張っていた」ものでして、〇〇につける薬が・・(;´д`)トホホそれこそ
「自衛隊が戦えるためにの必要な防衛装備品導入を法制整備と並行して断行」可能な
「自主防衛なくして同盟なし&同盟とは相互扶助」&
「令和の大攘夷体制」の履行&構築がまったなし…(思案)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
香港弾圧を「控えめ」にする中国共産党の「本音」
10/31(土) 12:20配信 Wedge
10月8日付の英Economist誌が、「これまでのところ、香港の新しい国家安全法は控えめに適用されている。しかし民主化運動家は安心してはいけない」との解説記事を掲載し、国家安全法施行後の香港の情勢を報じている。
エコノミスト誌の解説記事は国家安全法施行後の香港の状況をよく描写している。国家安全法の適用が控えめであるということは事実そうである。しかし、必要になればこの厳しい法律で広範な弾圧措置に中国共産党が出てくることは明らかであって、香港の民主活動家は安心していてはいけないとの記事の題名はその通りであろう。
国家安全法が「一国二制度」の香港を打ち砕いた可能性があるとこの記事は書いているが、認識が甘すぎるだろう。打ち砕いた可能性があるのではなく、打ち砕いたのである。共産党はレーニンの教えに従い、1歩前進、2歩後退というように戦術的に柔軟に対応する。香港のメディア王で民主化運動の指導者であり、外国との共謀罪で告発されたJimmy Laiが言うように、北京は政治的都合にあうように彼の取り扱いも決めるということであり、法による保護はないということである。
共産党には三権分立が良いものだという考えはない。三権分立の考え方は、フランスの哲学者モンテスキューなどが提起したが、要するに人間性悪説というかキリスト教の原罪論に基づくというか、権力者は悪いことをしかねないから、チェック・アンド・バランスを統治機構の中に組み込んでおくべしという考えである。アクトン卿の「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」との考えも同じ系譜にある。
他方、共産党は人民のために良いことをする権力であり、これに制約を加えるなど、とんでもないという考えが共産主義者にはある。
エコノミスト誌の記事の最後に、司法の独立が保たれれば少しは希望がある、というような記述があるが、共産党が主導する限り、そういうことにはならないだろう。それに、法律が悪ければ、司法判断は法の適用であるから、悪いものにならざるを得ない。
今のところ国家安全法の適用が思ったよりも穏健だということで、物事の本質を見損なうことは避けるべきであると考える。香港のケースは、中国が国際法をあからさまに無視する国であることを示したものであり、それを踏まえてしっかり対応しないといけない。今回の香港は、ヒトラーのラインランド進駐と同じようなものとみられている。(
Yahoo!より抜粋)
海上自衛隊が中国海軍の封じ込め本格化…!憲法の縛りもない「ヤバい実態」
10/31(土) 7:01配信 現代ビジネス
海上自衛隊が中国海軍の封じ込めを本格化させている。海域は主に南シナ海。中国が台湾、フィリピンに沿って引いた九段線(第1列島線)の内側で中国海軍を牽制し、行動の自由を奪おうというのだ。
日本は専守防衛が国是だが、安全保障関連法の制定により、他国軍との共同行動が世界規模に広がり、海上自衛隊は日本から遠く離れたインド洋や南シナ海での軍事行動を常態化させている。もはや、憲法の縛りなどないも同然だ。
本来、自衛隊による警戒・監視の南限は、尖閣諸島を含む東シナ海まで。訓練も日本やその周辺で行われ、他国に脅威を与えることがないよう抑制的に振る舞ってきた。
しかし、2016年8月、当時の安倍晋三首相はケニアで開かれたアフリカ開発会議(TICAD)で「自由で開かれたインド太平洋」を打ち出し、中国の習近平国家主席が掲げる巨大経済圏構想「一帯一路」に対抗する狙いを鮮明にした。
これを受けて、海上自衛隊は翌17年、米国とインドの共同訓練「マラバール」に継続して参加することを表明。日米印の3カ国共同訓練に格上げされた「マラバール2017」には海上自衛隊最大の空母型護衛艦「いずも」と汎用護衛艦「さざなみ」が参加し、インド東方海域で対潜水艦戦(対潜戦)訓練などが大々的に実施された。
隠密行動を旨とする潜水艦は、艦船にとって最大の脅威。この潜水艦を排除するのが対潜戦である。
中国に圧力を掛ける
護衛艦「いかずち」に着艦するオーストラリア海軍の対潜ヘリコプター=海上自衛隊のHPより
中国海軍の潜水艦はインド洋を航行している様子が確認されており、パキスタンやスリランカにも寄港している。「マラバール2017」が中国の潜水艦への対処を意識したのは明らかだ。
マラバールは18年にはグアム沖、19年は佐世保沖で実施された。グアムや佐世保は「一帯一路」のうち、海のシルクロードとされる「一路」には入らない。そこで海上自衛隊は18年度、19年度とも「インド太平洋派遣訓練部隊」を編成し、南シナ海に汎用護衛艦と「いずも」型の2番艦「かが」と「いずも」を交互に派遣した。
そして今年の「令和2年度インド太平洋方面派遣部隊」は「かが」と汎用護衛艦「いかづち」の2隻を9月7日から10月17日までインド洋と南シナ海に送り込んだ。2隻はスリランカ、インドネシア、ベトナムに寄港して各国海軍との信頼醸成に務めたが、もちろん派遣の主目的が友好親善などであるはずがない。
本来の目的は、米国、オーストラリア、インド各国の海軍と共同訓練を行うことにより、日米豪印4カ国の結束を見せつけ、南シナ海の環礁を埋め立てて軍事基地化を進める中国に圧力を掛けることにある。
派遣部隊の「かが」「いかづち」は、9月13日から17日までオーストラリア海軍の駆逐艦「ホバート」と南シナ海で、同26日から28日までインド海軍の駆逐艦「チェンナイ」、フリゲート艦「タルカシュ」や航空機とインド西方沖で、10月12日には米海軍の駆逐艦「ジョン・S・マケイン」と南シナ海で、それぞれ共同訓練を行った。
訓練内容について、海上自衛隊は「各種戦術訓練」とのみ発表し、具体的な訓練の中身を明らかにしていない。しかし、駆逐艦や航空機が参加したことから、敵航空機から艦隊を守る防空戦、また敵艦艇から守る対水上艦戦の共同訓練を実施した可能性が高い。
共同訓練は「グレーゾーン」
これまでの政府見解では、日本が他国から侵略された場合、日米安全保障条約を根拠に来援する米軍を自衛隊が防護することは専守防衛の一環とされ、合憲としてきた。一方、平時に米軍や他国軍を自衛隊が防護すれば、集団的自衛権の行使となり、違憲との見解を示していた。
だが、現在は違う。安全保障関連法の施行により、平時であっても自衛隊と共同訓練中の米軍や他国軍の艦艇や航空機を防護することが可能となっている(自衛隊法95条の2、合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)。
では、南シナ海で自衛隊は米軍やオーストラリア軍を防護しているのだろうか。筆者の問い合わせに、海上幕僚監部広報室は「明らかにできない」と回答した。中身を公表できないのは、安倍前政権が定めた特定秘密保護法に触れるからだ。
自衛隊法95条の2にもとづく、米軍などの防護は毎年2月に件数のみが公表される。2017年は2件、18年は18件、19年は14件が実施された。ただし、いつ、どこで、どのように防護をしたのかは非公表だ。
米軍などの防護は、前年に実施した分がまとめて防衛省から国家安全保障会議に報告される。同会議で得られた結論は、漏洩すると懲役10年以下の厳罰に処せられる特定秘密となるため、あえて同会議にかけることで米軍防護を特定秘密とし、公表できないようにする仕掛けとなっている。
では、自衛隊と共同訓練を行っている最中に米軍やオーストラリア軍が万一、中国軍から攻撃された場合、自衛隊はどう対処するのか。近くにいる自衛隊も攻撃されることを想定し、武器使用に踏み切る公算が大きい。
結局、南シナ海やインド洋での共同訓練は、自衛隊が他国軍の艦艇を防護する場面があり得るというグレーゾーンの中で行われているのではないだろうか。安全保障関連法が成立する以前なら、集団的自衛権の行使として到底、認められなかった訓練を日常的に行っていると考えるほかない。
米海軍との関係が大変化した
日印共同訓練で並走する駆逐艦「チェンナイ」(手前)と護衛艦「かが」=海上自衛隊のHP より
話をもとに戻そう。
海上自衛隊は9月15日、「令和2年度インド太平洋方面派遣部隊」に潜水艦部隊が合流すると発表し、10月9日、南シナ海で「かが」「いかづち」が潜水艦「しょうりゅう」とともに対潜戦訓練を実施したと発表している。
「インド太平洋派遣訓練部隊」の訓練に潜水艦が参加したのは2018年の「くろしお」以来、2回目。18年の「くろしお」も、今回の「しょうりゅう」も「他国(おそらくは中国)」の潜水艦を模擬した「敵」となり、護衛艦と対潜ヘリコプターが探知して攻撃する模擬戦闘を実施した。
「いずも」「かが」は、対潜戦に特化して建造された艦艇である。もちろん汎用護衛艦も対潜戦は得意技のひとつだ。これらの艦艇が毎年、1カ月以上にわたって南シナ海に派遣されている。また米海軍も「航行の自由作戦」と称して、1年を通して駆逐艦を南シナ海に派遣している。
中国海軍は、南シナ海に面した海南島に南海艦隊の潜水艦基地を持つ。基地には弾道ミサイル搭載原潜や攻撃型原潜、通常動力型潜水艦が配備されており、日米による戦闘艦艇の南シナ海派遣は、こうした中国の潜水艦の行動を牽制する狙いがある。
また海南島の潜水艦は太平洋やインド洋に出るには、必ず南シナ海を通過しなければならず、その海で日本の潜水艦が潜んでいる可能性があれば、中国海軍は対潜戦に備える必要が出てくる。海南島近海に米海軍の原子力潜水艦が潜んでいるのは公然の秘密なので、中国海軍は対米だけでなく、対日の対潜戦にも追われることになる。
米軍は駆逐艦だけでなく、潜水艦を探知する音響測定艦、潜水艦を発見する哨戒機も恒常的に派遣し、中国海軍の封じ込めに全力を挙げている。
今年7月には空母「ロナルド・レーガン」と空母「ニミッツ」が巡洋艦、駆逐艦を伴って南シナ海に入り、2回にわたって米軍同士の共同訓練を実施した。2隻に搭載された100機以上の戦闘攻撃機は実戦を想定して何度も離発着を繰り返した。
中国にとって、これほどの脅威はない。これに対抗するように中国軍は8月26日、中国東部の浙江省から射程1500キロメートルで「空母キラー」と呼ばれる対艦弾道ミサイル「DF21D」を2発発射、また内陸部の青海省から射程4000キロメートルで「グアムキラー」の異名を持つ「DF26」を2発、発射した。それぞれ南シナ海の海南島と西沙諸島の間の海域に着弾した。
中国軍は、昨年7月にも本土から南シナ海に向けた対艦弾道ミサイル6発を発射した。このときは中国国防部が「いかなる国や特定の目標も対象にしていない」との見解を示したが、今回はそうした説明が一切ない。米国への牽制であることは明らかだ。
米中対立がかつてないほど緊迫する南シナ海。11月3日に投票が行われる米大統領選挙でバイデン元副大統領が勝っても米国の対中政策に大きな変化ないだろう。
そんな米中対立の海に、海上自衛隊は護衛艦や潜水艦を恒常的に派遣している。売られてもいないけんかを買って出るのに等しい行為ではないか。
もともと「密」だった米海軍との関係が安全保障関連法により、「濃密」に変化した。この大変化は国内ではほとんど知られていない。わが国は政治が軍事を統制する「シビリアン・コントロール」を採用している。国会の場で、南シナ海やインド洋で実施している海上自衛隊の訓練について議論する必要があるだろう。(
Yahoo!より抜粋)
もし北朝鮮軍と自衛隊が戦闘することになったら… 自衛隊を知り尽くした漫画家、元特殊部隊員が明かす「国防」のリアル
10/31(土) 10:59配信 デイリー新潮
30年以上にわたって海上自衛隊を描き続けてきた漫画家・かわぐちかいじ氏と、自衛隊初の“特殊部隊”創設に携わった経験に基づくノンフィクション・ノベルが5万部に届こうという伊藤祐靖氏。二人が語った“戦争体験”、米軍と自衛隊の本質的な違い、そして「現場のリアル」と「フィクションの想像力」とは――。
***
かわぐちかいじ氏
か 自衛隊の存在意義や国を守ることについて、伊藤さんは入隊後も考え続けていた。前作の『自衛隊失格』を読み、お父上との関係が大きいんだろうと思いました。
伊 はい。あの本では、自衛隊での経験を中心に、本気の度が過ぎていつもルールを逸脱してしまう自分の半生を書きました。その過程で“ああなっちゃいけない”対象として父を見て育ったので、ずっと否定してきましたが、やはり父親の影響が大きいです。現代ではありえない「軍人」の意識というのか、任務遂行への責任感です。
か お父上は陸軍中野学校のご出身で、終戦間際に受けた蒋介石暗殺の任務が、戦後もずっと解けていなかった。いつ頃そう聞いたんですか。
伊 私が小学校に入る前、5歳ぐらいのとき、父は毎週日曜日にエアーポンプ式のライフルで廃墟で練習していたんです。1969年です。
か 戦後24年経っても、蒋介石を狙っていたわけですね。
伊 蒋介石は、私が小学校4年生の頃に台湾で亡くなったんです。父はそこでやっと暗殺のための練習をやめましたが、それまでは「いつかは」と狙っていたようです。
か 息子の蒋経国も亡くなりましたね。
伊 はい、今でも覚えていますけど、狙う理由を聞いたら、「昔な、暗殺しろって言われて、やるって言ったからな」「今日電話がかかってきて、明日行けって言われたら困るだろう」と。だから練習も欠かさない。何を言ってんだ、戦争なんて自分が生まれるずっと前に終わっているのに。そう思っても、まだ真剣に任務を遂行しようという父が目の前にいました。
インドネシアの独立戦争に勧誘
かわぐち作品を現役の頃から愛読していた伊藤氏
伊 72(昭和47)年に横井庄一さん(グアム島で日本の無条件降伏を知らないままゲリラ戦を展開していた)が帰国したときは驚きましたが、その2年後に、小野田寛郎さん(陸軍中野学校出身で、終戦後も任務解除の報が届かず、在比米軍に対してジャングルでゲリラ戦を展開)がフィリピンのルバング島から帰って来た際のことです。周囲が驚嘆する中、父だけは、「いや、別にすごくもなんともない、普通のことだ」とつぶやいていた。何が普通なのかと今考えると、蒋介石が台湾で生きている間は、いつでも現地へ行けるよう「自分もまだ準備を続けていたから」なんです。
か 今のお話で、『空母いぶき』とその前の作品(『兵馬の旗』)で監修を担当してくれた、小学校の同級生で軍事ジャーナリストの惠谷治君――残念ながら一昨年亡くなりましたが――、彼のことを思い出しました。
小学校の頃に惠谷君は、その当時流行っていたテレビドラマ「快傑ハリマオ」(欧米諸国の植民地だったマレー半島を舞台に「民衆の敵」と戦う実在の日本人をモデルにした冒険活劇)が好きで、ハリマオになりきってよく遊んでいました。中高生ぐらいになって、なんであんなにハリマオに傾倒していたのかと聞いたら、「実は、おやじが陸軍解散後、インドネシアのオランダからの独立戦争に関わる動きをしていたらしいんだ」と話していた覚えがあるんです。だからハリマオという作品で、自分のおやじをイメージしていると。確証はないにしても、身近にそんな話があったわけで、戦争は「終戦しました」では簡単には終わらないものなんですね。「アジアの独立を助ける日本軍」という役割を果たせていない、そんな思いを抱えながら日本に戻った人が数多くいた。正しいかどうかは別として、そういう思いを抱えている自分の親世代は、かなりいました。
伊 私の父もインドネシアの独立戦争に行かないかと誘われたそうです。
か お父さんもですか。
伊 はい。でも暑いから嫌だと断った。高地で標高が高いから涼しいと言われたそうだけれど、蒋介石暗殺任務がありましたし。本当に、おっしゃるような無念を抱えた人は多かったと思います。
戦争時代への「こりごり感」
『空母いぶき』のワンシーン(©かわぐちかいじ・惠谷治/小学館)
伊藤 陸軍中野学校出身の陸軍軍人だった私の父の話で思いがけず盛り上がってしまいました。ところで、かわぐちさんのお父上も海軍の軍人だったんですよね。
かわぐち はい。いちおう海軍でして、広島の大竹海兵団で一番下っ端からスタートし、最後は兵曹長になりました。掃海艇で瀬戸内海から日本海から、あちこちを回っていたようです。海軍といっても外洋で米軍なり英軍と戦ったのではなく、地味な機雷処理での国内治安維持です。そんなに戦争当時を語りにくいという感じではなく、結構明るく話していました。
例えば、島根県の港で機雷をボンと爆破させたら魚がいっぱい浮いて、その魚を配って大喜びされたとか、イメージしやすい明るい話が多かった。ですが、ことさら明るく話している感じもどこかにあったし、あの時代はもう嫌だという「こりごり感」がこちらにも伝わってきました。
父親世代は、戦争経験によって語ること語れないことというのを、みんな抱えていました。立場違わず、みんなそれぞれに。それを全部含めて、自分の中では、あの時代は嫌だったんだろうと感じていました。僕の子どもの世代はわかりませんが、僕ら団塊の世代までは、父親世代の戦争体験を重いものとして受け取っているんですよね。
『亡国のイージス』の作家、福井晴敏さんと対談した際に、戦争の扱い方が世代によって違うという話になりました。彼は51歳、戦争の話を素材として書くときに、反戦だけでは書かずに、ある種のゲーム感覚をそこに落とし込むことができる。僕らの世代は、反戦、ないしはそこに向かう何かしらのベクトルがないと、戦争を描いてはいけないという気持ちがどこかにあって。
僕らより年下の年代の人は、反戦という感覚から自由になって戦争を扱うことができる世代なんですよね。世代によって、先の大戦についての表現のベクトルが少しずつ違ってきます。
伊 そうでしょうね。切実感、距離感が違う。逆に、そこは意識的に描かれているんですか?
か その世代だからということは念頭にはないんですが、結果的にそうなるとは言えます。「戦意高揚」をしたくはないんです。カッコいいだけの漫画で、戦闘意欲を刺激するというようなことにはしたくない。
とはいえ、ちゃんと派手に描きます。戦闘場面は丁寧に描いていますが、結果的にそれだけを読みとってほしくないという気持ちは常にあります。
伊 戦争にならないことが肝要です。だからこそ、読みたくなるんですね。
今の自衛官が戦争を体験
北朝鮮でクーデター勃発。拉致被害者を救出せよ! そのとき、国はどう対峙する?『邦人奪還』伊藤祐靖[著]新潮社
伊 かわぐちさんの『ジパング』も好きです。21世紀の海自のイージス艦が、ミッドウェー海戦直前の1942年6月の太平洋上にタイムスリップして話が始まりますね。主人公たちに救助された旧日本海軍の将校が、イージス艦内の資料室に入るシーンがありますが、3日ぐらい出てこない。涙をこぼしながら未来の日本に関する資料を読むシーン、あの重みや深みは、私より下の世代には描けないと思います。
か 原爆の資料に触れる場面ですね。
伊 タイムスリップしてきた未来の資料室で、原爆の惨禍を知る。日本はこうなるのかと涙をこぼす……。
か 『ジパング』はずっと描きたかった作品でした。僕より若い、先の大戦を全然知らない今の自衛官の世代が、戦争を体験する。その様子を描くにはどうしたらいいか。護衛艦ごとタイムスリップするのが一番手っ取り早かった。よくあるパターンだと言われてもいいから、ストレートにぱっと描こうと思いました。
伊 未来からきた自衛隊員たちが、その時代の日本海軍の少佐を助けて未来を教えたがために、いろいろ問題が出てきますね。描きたい「問題」が浮き彫りになっていきます。
「月」でタイムスリップに気づく仕掛け
か 『ジパング』で「やったぞ」と思ったのは、タイムスリップしたことに本人たちが気付くシーンです。横須賀から出てハワイの手前辺りに来たら、夏なのに雪が降る。わっと甲板に出たら後ろに戦艦「大和」が来ていて、最初はみんな「大和」の方が今の時代に来たと当然思う。まさか自分たちがあの時代にタイムスリップしたとは思わない。そこで時代を思い知らせるのが「月齢」なんです。月が違う。きのう見た月と今日の月は違う。あの辺はタイムスリップものを描く醍醐味でした。
伊 あのシーンはよく覚えています。よく船乗りのことをご存じだなと思ったんです。月齢が幾つか、普通の人にはわからないけど船乗りには絶対にわかる。月は大事で、みんな実用的に見ていますから。
か その結果、みんな愕然として、自分たちが「大和」の時代に来たんだとわかる。これはまずいことになったぞ、と。あれを描いたときに、なにより、自分がわくわくして(笑)。
伊 船乗りとしてもわくわくしました(笑)。海を描かれるのはお好きなんですか。
か 家業がもともとは海運業だったんです。戦争で駄目になった後、おやじが帰ってきて、船の給油会社に就職して、そこで顔なじみが増えたので、独立して会社を興したんです。
船の給油船を尾道では「タンク船」と呼びます。10トン未満、長さでいうと7~8メートルぐらいの小さい船ですが、船長と機関長が2人乗らなきゃいけない。おやじは1人でやっていて、海上保安庁に見つかると注意され何回かで罰金ですが、子どもが1人でも乗っていればいいから、自分と双子の弟を代わりばんこに乗せていました。
伊 子どもの機関長ですか(笑)。
か 楽しかったですよ。岸壁や給油する船に結ぶ綱を取る役もして、小型の船舶には実感として慣れたし、船のどこが面白いか、どこが怖いかという知識は皮膚感覚としてあったんですね。おやじは映画が好きで、よく一緒に連れ立って観る映画もだいたい海軍もの。生い立ちも含めて、海や海軍の話が描きやすかったかもしれません。
アメリカ空母に乗船してみると…
伊 日常的に船の上にいると、これ以上はないという美しい海の風景を見ることがあります。
か 故郷の瀬戸内海は漁船が多いのですが、内海の漁船の作りは外洋とは全く違うんですよね。例えば、かみさんが青森の八戸なんですが、八戸のイカ釣り漁船の作りは全然違う。見ただけで出かけて行く海の違いがわかります。『邦人奪還』の潜水艦の記述にも、これは外洋だな、とひしひしと痛感させられました。
伊 瀬戸内海の風景は格別ですよね。
『空母いぶき』では、「尖閣諸島中国人上陸事件」が発生し、その1年後に海自初の空母「いぶき」が完成。その艦長に、航空自衛隊の戦闘機パイロットとして名を馳せた秋津竜太1佐が着任しますね。その演習航海中に、中国軍が与那国島や尖閣諸島を占拠するところから、史上初の防衛出動にまで至る――その細部が非常にリアルで、迫力があります。そもそも、アメリカでは空母の艦長はパイロット出身が多いということはご存じだったんですか?
か この話を描こうと調べ始めてから知りました。戦後日本では空母の運用例がないので、米海軍の慣習に従った方がいいかと考えました。
伊 私は米空母「キティホーク」に乗ったことがあるんです。乗ってびっくりしました、パイロットが艦長なのかと。旧日本海軍の空母の多くは船乗りが艦長でしたが、アメリカではパイロットなんです。
けちな自衛隊、食べ放題の米軍
か 米空母にはどこで乗られたんですか。ハワイですか。
伊 ハワイからサンディエゴまで、1カ月ぐらい乗っていました。キティホークは、後に横須賀が母港になりますが、乗った頃はまだサンディエゴを母港にしていました。艦長がパイロットですから、船の運航は副長に任せていましたね。戦闘機を運ぶ空母はStrike Group(打撃群)、要するに戦闘機部隊のもの。飛行場としか思っていないから、トップの指揮官はパイロット、しかも戦闘機パイロットなんです。それを思い出しながら『空母いぶき』を読みました。
あと、海自初の空母、その艦長を「航空自衛隊ごときにやらせたくない」と、副長以下船乗りたちが空自出身の主人公について噂しますよね。
か 海自としてはそのままにしておけません。
伊 ああいう感情はあるだろうなと思いますね。そこまで反映されているんだなと、冒頭から驚きました。ところで、キティホークは非原子力型の空母ですが、乗員は5千人ほどもいるんです。
か 5千人というと、ホテル、いや、もはや高層ビルですね。
伊 サラダでもなんでも、食堂が食べ放題なんです。自衛隊なんて「コロッケ×3」と書いてあって、キャベツに隠して4つ取ろうもんなら大変なことになる。なにしろ、最後の人のところでコロッケが2つしかないと「誰か余分に1個取ったな」と犯人捜しです。そういうけちくさい習慣があるわけです。米軍の空母なんて取りたい放題で、「すごいな。カッコいいな」と思ったんです。
でも、それがそうでもありませんでした。毎日、船の後部から残飯を捨てていて、その量ときたら……。「この人たちはやっぱり間違っている」と。5千人が食べたいだけ食べられる分量を必ずつくるから、残飯の量はたぶん、日本の護衛艦の食料1日分です。自衛隊はコロッケ3つでいまだにやっていると思います。アメリカはなんでも贅沢にやっていますよね。
リアルを知ると描きにくい?
か 自分の話で恐縮ですが、最初に『沈黙の艦隊』があってその後『ジパング』と、同じように自衛隊の話を素材にして描きながらも、少しずつ違って来た実感があるんです。
伊 スタンスが変わったということですか?
か 『沈黙の艦隊』の頃は、自衛隊のことをあまりよく知らないで描いている箇所もあり、荒唐無稽でも、お話として自衛隊を使っていくところがあった。ですが、『ジパング』を経て『空母いぶき』に来て、だんだんリアルになってきたんです。設定も、中のドラマも、よりリアルに読んでほしいという気持ちがどんどん高まってきて。
それは監修として協力してくれた故・惠谷治君(軍事ジャーナリスト)が自衛隊のことに詳しくて「これはないよ」と指摘してくれるようになったからです。「これはないよ」をある程度クリアにした設定にしながら描いていますから、だんだん表現がリアルになっていき、それを面白がる自分もいました。一方で、漫画表現として、読者が面白がるなら多少の誇張は許されるという気持ちもどこかにあって、むしろ実際を本当に知っていると妄想の世界に入れないからなかなか描きづらくなるんです。
伊 読んでいて全然気にならないです。
か そうですか。
伊 はい。それこそ前回お話ししたように、『沈黙の艦隊』で主人公が原子力潜水艦の船体にナイフで「やまと」という艦名を彫る場面も、現実にはあり得ないシーンであっても、今でも気にならないです。
北朝鮮との戦争を“想像”
か 伊藤さんは実際の現場をすごく知っている。知っているからこそ、その素材を使ってフィクションとして書くとき、難しいだろうなとも思います。ノンフィクションとしてそれを表現する際には、体験しているということがある種の強みではあるんですけど、妄想を膨らませて面白い展開を紡ぎ出す場合は、難しいのではと思うんですよね。
伊 例えば、北朝鮮での戦闘シーンです。北朝鮮とは当然、私は戦ったことがないんですが、想像はつくんです。それこそ、想定訓練も組んでいるので。だから、どちらかというと思い出しながら書いている感じです。逆に、かわぐちさんは実際にはどれくらい取材をされるんですか?
か 海上自衛隊の観艦式に1度行ったぐらいです。他に飛行甲板を備える護衛艦「いずも」には乗せていただき、艦内を取材したことはあります。観艦式のときに、機会をいただき潜水艦の艦長とお会いしました。その艦長が「なんでも聞いてください」と仰るので、「90度の倒立ってありますか」と聞きました。潜水艦は急速浮上や急速潜航する際にかなりの急角度になるのですが、垂直になることもあり得るのか。あり得るなら漫画に描こうと思ったんです。でもその艦長は「なんとも言えませんね」と。「ただ言えるのは、潜水艦はそういう90度の倒立のためには造られてはいません」と仰いました。
伊 もう少し答えようがありそうなものですね(笑)。
か いや、感心しました。予測のもとには絶対に話をしない、それを現場が守っているという事実は取材になりました。
伊 その言えない部分が、かわぐちさんの作品にはあるんですね。今も時々読み返しています。
か 私も連載が行き詰まったときは、『沈黙の艦隊』や『ジパング』を読み返すのですが、自分で描いていてなんですけど、結構面白いですよね(笑)。
伊 はい、とても面白いです(笑)。『空母いぶき』の続編シリーズ(『空母いぶき GREAT GAME』)もまだ序章ですが、非常に引き込まれますね。「いぶき」の次期艦長候補率いる護衛艦「しらぬい」が、北極海に調査航海に出て民間の調査船を救助する。そして……続きは、ぜひコミックスを読んでください。第2巻は10月30日発売とか(笑)。
か ありがとうございます(笑)。(
Yahoo!より抜粋)
日本の安全を支える知られざる最先端装備の世界
10/31(土) 6:01配信 JBpress
(数多 久遠:小説家・軍事評論家)
10月21日から23日にかけて「テロ対策特殊装備展(SEECAT)」と「危機管理産業展(RISCON)」が開催されました。会場は、ともにビッグサイト(東京都・有明)です。
テロ対策特殊装備展(SEECAT)は、官公庁やインフラ関係者、それにテロの標的になりかねない大規模施設関係者を対象とした展示会で、来場者にも事前に審査が行われるクローズド展示会です。2007年から開催されており、今年(2020年)で14回目の開催でした。
もう一方の危機管理産業展(RISCON)は、一般企業の危機管理担当者などを対象とした、一般向け展示会です。2005年から開催されており、今回で16回目の開催となります。コロナの影響が大きな本年は、感染症対策や避難所設営に力点をおいて実施されました。
東京オリンピックが延期されましたが、引き続き警戒が必要な状況です。その意味で今年は注目度が高いはずの展示会と思われましたが、やはりコロナの影響か、来場者数は例年の半数強という数に留まったようです。
筆者が実際に会場を訪れたところ、なかなか興味深い展示品を見ることができました。特にテロ対策特殊装備展(SEECAT)の方は、「一般の方お断り」の、まさに特殊なものが多い内容でしたので、そちらを中心に紹介したいと思います。
■ テロ対策特殊装備展(SEECAT)
テロ対策特殊装備展(SEECAT)は、その名の通り、テロ対策を目的にした展示会です。ビッグサイトで実施される展示会としては少々異質と言えるでしょう。今でこそ、ビッグサイトで、こうしたしっかりした展示会形式で実施されていますが、かつては自衛隊基地の体育館などで、ひっそりと行われていました。
【ドローン(UAV)】
SEECATに出されている製品のなかで、この十数年で最も著しい進歩を遂げたのがドローンでしょう。
現在も戦闘が続くナゴルノ・カラバフでの紛争でも相当数が使用され、成果を上げていることがネットの動画などで見ることができます。そのため注目度は抜群で、展示も多く見られました。ただし、ナゴルノで使用されているような純粋に攻撃用のドローンおよび装備は、ユーザーが防衛省しかないためか両展示会には出展されていません。
形態としては、ホビー用のドローンをそのまま大型化、高性能化したような製品の他、軍・治安機関向けと思われる固定翼タイプやヘリコプターに類似した形状のものなど、多種多様なものが展示されていました。
【本記事は多数の写真を掲載していますが、配信先では表示されていない場合がありますので、JBpressのサイト(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/62704)にてご覧ください。】
特殊なドローンとしては、有線でつながれ、固定点で運用される上空からの監視用ドローンも見られました。また、ドローン搭載用のシステムも展示されていました。カメラと映像処理システムを組み合わせ、車両などの移動物体検知や人工物を自動でピックアップしてくれるものなどです。ナゴルノ・カラバフでの紛争でも、同種のものが多数使用されているようです。
【水上ドローン(USV)、水中ドローン(UUV)】
水上ドローン(USV)は、用途が港湾監視などに限られるためか、出展数はあまり多くありません。そのなかで下の写真の「EMILY」という製品はなかなか興味深い製品です。溺者救助用のラジコンボートなのですが、応用が利きそうです。開発はHydronalix社で、日本海洋が展示していました。
艦艇や船舶に装備される救命索発射銃(浮き輪を発射できるものもある)は、射程が100メートル程度しかない上、遠距離では正確に撃つことが困難です。しかし、これなら数百メートル先にも正確に到達させられます。また、固定翼の救難機から投下し、無線機や水食料を要救難者に届けることも可能でしょう。
一方、人間に代わって潜水することができる水中ドローン(UUV)については、サイズ、形態、スペックの点で、空中ドローンに負けず劣らず多数の出展が見られました。
自衛隊の掃海部隊が使用する機雷掃討用の水中ドローンに近いような高度なものは、効果があって当然ですが、安価でありながら有用そうな小型製品もありました。また、あるブースでは、「あまり紹介しないでほしい」と言われたのですが、溺死者の遺体捜索、引き揚げで実績を上げているというお話も聞けました。確かに、冷たい川で何度も潜るよりは、水中ドローンを活用するほうが有効でしょう。
なお、陸上(UGV)ドローンも、サイズ、用途などさまざまなものが展示されていました。
【対ドローン製品】
ドローンは、テロの手段としても使われる可能性が高いため、対ドローン製品も多数の出展がありました。対ドローンの方式として、最も多く見られたのは、ドローンをコントロールするための信号を検知し、ソフトキル、つまりジャミングなどによってコントロールを阻害するものです。網をかぶせたり、他のドローンをぶつけると言ったハードキルの製品は、ほとんど見られませんでした。やはり、あまり現実的ではないのだと思われます。
これに関連して、本コラム「過去最大・防衛省概算要求、何の予算が足りないのか」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/62478)でも触れた、高出力マイクロ波(HPM)発生装置の研究が、防衛装備庁による展示で示されていました。電波によって、回路を焼き切るなどするハードキル手段ですが、まだ現状では、かなり限られた対象、状況でしか効果があるとは言えないようです。
また、電波を使用する対ドローン製品の中では、コントロール用の信号の検知ができていなくとも、実効性を発揮できそうな高度な製品も展示されていました。ただし、お話を伺うと、まだ総務省の対応が不十分のようです。来年にはオリンピックが開催される見込みですが、このままでは、政府の準備不足が原因で、モノはありながら対処できなかったという事態も起こり得そうです。
【毒物等検知】
ドローンと並び、この十数年で進歩の著しい分野が毒物などの検知です。
化学兵器に対して、十数年前は研究者が実験室で扱うような器材でなければ、まともな検知はできませんでした。とくにハンディの製品は、検知確率を高くすると排気ガスや化粧品にも反応してしまうほど誤警報確率が高くなってしまい、とても実用に使えるものではなかったのです。
現在の検知器材は、高い検知確率と低い誤警報確率を両立させるだけでなく、使用された化学剤の判別も正確かつ迅速に行えるものが出ています。たとえば、本年8月に、ロシアの反体制派であるアレクセイ・ナワリヌイ氏の毒殺未遂事件でも使用されたロシア製化学兵器「ノビチョク」についても、その細部タイプ(A-232等)まで判別可能な製品が展示されていました。
用途別にも様々な製品が出ており、個人携行用小型製品から、大規模施設の警戒用まで展示されていました。
個人携行用の小型製品や中隊規模用の検知器材については、米軍では既に相当数が導入され、化学戦の専門部隊だけでなく、一般の歩兵中隊でも化学剤の検知がかなり迅速に行える体制になりつつあるようです。
私が特に注目したのは、レーザー光を使用し、化学剤ごとに異なる吸収スペクトルから検知・警報を出せるものです。空港のような大型施設で化学剤が使用された場合でも、多数のセンサーを設置することなく、1つの器材とレーザー反射用のミラーを使うことで、その間の空間中に存在する化学剤の検知ができるそうです。オリンピックの会場を警戒するにも効果的でしょう。
上記の製品は、米Block Engineering社の製品をエス・ティ・ジャパンが扱っているそうですが、軍事向けとしては、ハウジングなどを装備しパッケージ化したものをロッキードマーチンが扱っているそうです。防衛省が導入する場合、FMS(Foreign Military Sales:有償援助)などでロッキードマーチンから買う可能性が高いですが、アフターサービスが不十分なFMSよりも、こうしたルートで買った方が良さそうです。
生物兵器に対する検知では、使用されたウイルス等の特定までできる製品が出てきているようです。ただし、残念ながら、まだ十数年前の化学剤検知のレベルのようで、相当な専門家が、複数の装置を組み合わせて使わないと検知が難しいようです。恐らく、生物兵器に対しては、あと十数年経過してもそれほど状況は変わらないのではないでしょうか。
放射性物質に対しては、昔からガイガーカウンターなどがあるように、検知自体は容易です。ですが、なかなか興味深い製品が展示されていました。フジトクのガンマカメラH420は、カメラ画像を組み合わせることで、微量の放射性物質でも、どこにどのような種類の放射性物質があるのかを迅速に把握することができるとのことです。テロはもちろん、医療現場など放射性物質を扱う場所での事故の際にも、汚染の状況が容易に把握できるようです。ロシアからイギリスに亡命したアレクサンドル・リトビネンコ氏が、放射性物質によって毒殺された事件がありましたが、こうした器材があれば、迅速に毒物の把握ができたかもしれません。
【訓練用シミュレータ】
市販のゲームから派生した軍事訓練用のシミュレータが複数展示されていました。下の写真は、ArmAシリーズが元となったBohemia Interactive Simulations社の製品VBS4です。同社は、日本支社も作っているようで、相当力を入れているようです。
自衛官の戦術判断トレーニングにも有効でしょうし、指揮所演習(CPX)での状況現示用としても良いと思われます。各国に比べ、自衛隊はこうしたものを取り入れるのが遅れていますが、訓練のコストを下げると共に効率的に訓練を実施できるため、もっと取り入れるべきだと思います。
【ソフトウェア】
東洋テクニカが展示していたSeaErra社の可視光水中映像の処理ソフトは、水中映像を非常に鮮明にすることができるようで驚きました。リアルタイム処理も可能なソフトウェアなので、あらゆる水中ドローンで活用することができるそうです。海自の掃海部隊などに良さそうだと思いましたが、やはりそうした方面の方が興味を持っているとのことでした(参考:https://www.youtube.com/watch? v=hL7EiN704MA)。
もう1つ、これも東洋テクニカの扱いのソフトウェアですが、洋上での可視光、IR捜索を支援するものがありました。陸上と違って遮蔽がないものの、波が常に変化するため、洋上での捜索は以外と大変です。専用の捜索器材でなくとも、発見率を上げられそうです(参考:https://www.youtube.com/watch? v=amEF3MFRBjU)。
【その他】
金庫で有名なクマヒラは、原発の放射線遮蔽扉や特殊な防護扉を作っています。最近頻発する水害のせいで、一般のマンションなどに水密扉が売れているというお話を伺うことができました。非常用発動発電機を備えたマンションも数多くありますが、福島原発と同様に沈んでしまえば意味がないため、こうした需要も増える傾向のようです。
消火器など防災機器メーカーのヤマトプロテックは、爆発の威力を減殺するシールドフォームという製品を展示していました。
不審物を発見した際に、もし爆発しても被害を極限するための製品です。以前から同じ目的で防爆マットというものが以前からありますが、こちらは不審物に上からかぶせるのではなく、泡消化剤のような製品です。爆風を相当程度弱める効果があるようです。
破片の飛散を止める能力はないようなので、防爆マットより効果は劣るようですが、不審物は防爆マットをかぶせることが困難な場所に置かれているケースが多いため、そうした場所での使用に向きそうです。また、防爆マットをかぶせても、どうしても隙間が発生するので、その隙間を埋めるために補助的に使用するのも良いかもしれません。
価格は防爆マットの数分の1で済むようです。ただし、その代わりとして、メンテなしに使用できる期間は2年ほどに留まるようです。オリンピックの期間だけ準備しておくという考えもアリかもしれません。
以前、ユーチューブで見かけ、これはいいなと思っていた製品が、日本に上陸していました。Wrap Technologiesが開発しエイコラボが展示していた「BOLA WRAP」です。
昔から世界各地に狩猟用具、投擲武器として存在しているボーラ(ロープの先端に球状のおもりを取り付けた道具)を、現代の拘束具として即応性、安全性を高めた製品です。離れた場所から、暴漢の手足を拘束することができます。おもり部分に石などを使った古来のボーラは殺傷力も高かったのですが、こちらはおもりを釘程度のものにしたことで、軽い怪我で済むようになっています。ただし、投射に火薬を使用しているため、日本では銃刀法の規制対象になるそうです。そのため、販売先は、公官庁に限るとのこと。こういったものは、銃刀法に特例規定を作ることで、学校や警備業で使えるようにするべきではないかと思います。
この他にテロ対策特殊装備展(SEECAT)では、不審物検査用の製品、侵入阻止製品、個人用装具などが展示されていました。以前のものと比較すると利便性は向上しているようですが、とくに目を引く画期的な製品は見られませんでした。
■ 危機管理産業展(RISCON)
続いて、「危機管理産業展(RISCON)」の展示を紹介します。危機管理産業展は、冒頭でも触れたように感染症対策や、そうした配慮が必要とされる避難所設営用の資機材が多く展示されていました。
【感染症対策製品】
感染症対策製品としては、エアテントを利用して隔離病室や除染所を作ることのできるシステムや、病院内で応急使用するための隔離システムなど、コロナによって急速に需要が高まった製品群が見られました。エアテントは、細部仕様は異なるものの、基本的には陸上自衛隊の対特殊武器衛生隊でも使用されているものと同じものでした。
【避難所設営製品】
下の写真にあるような段ボール製のパーティションや仮設トイレ用の資材が多く展示されていました。
【特殊車両】
川崎重工のブースには、陸自の水陸機動団に納入されたATV(全地形対応車)、MULE(多用途四輪車)が展示されていました。MULEは、オスプレイに搭載可能な車両として導入されています。MULEは人気のようで、会場にもう1台ありました。モリタの小型オフロード車「Red Ladybug」です(参考:https://www.youtube.com/watch? v=MlzCCMXxEqk&feature=youtu.be)。
東京消防庁はこれらとは別の米国製ポラリス・インダストリーズの「POLARIS RTE87」を全地形活動車として採用し、会場に置いていました。
こちらも、オスプレイに乗せられるという点が特徴の車ですが、日本での防災用としてどれだけ効果があるかは、少々疑問です。
また、消防庁は、この手の車両としては有名なベンツのウニモグをベースとした高機動救助車も展示していました。
【その他】
特殊車両の製造を行っているコーワテックから出展されていたのは、普通の建設機械を遠隔操縦するためのキットです(参考:https://www.kowatech.co.jp/products/sam/)。SAMというこの製品は、建機の操縦席に置く操作用のロボットとカメラなどからできており、大抵の車両をドローン(UGV)化することのできるものです。既に、陸上自衛隊などで採用され、有人での作業が危険な場所で使用されているようです。
自衛隊でも多数の製品を使用している火口品メーカーの細谷火工のブースには、黒色の煙が出る発煙筒が展示されていました。救難用などでは、彩度の高い赤や黄色の発煙筒が使われることが多いので、なぜ黒なのか伺ったところ、訓練での火災の模擬に使うとのことでした。
【公官庁の出展】
最後に、官公庁の出展についても触れておきます。
一番の変わり種は、公安調査庁でした。ブースも大きく、配布している資料の分厚さからも力を入れていることが分かります。
意外だったのは内閣官房です。国民保護訓練などが担当になるため、広報を意図しての出展だということでした。
個人的に感心したのは、東京都の下水道局です。注目されることは少ない役所だと思いますが、液状化の際に浮き上がらないマンホールを開発したり、地震でも下水道が破損しないようにするといった見えない努力を重ねているようです。
官公庁の出展は基本的に広報活動の一環のようですが、積極的に売り込みをかけていたのが航空自衛隊です。防災や危機管理担当者として、退職する自衛官を売り込んでいました。ブースにいた方も、そうした再就職の斡旋を行う空幕の援護業務室の方々でした。自衛隊への災害派遣の要請時に、自衛隊の動きを熟知し調整が容易という理由で、元自衛官を自治体の防災担当に採用する動きが進んでいます。企業でも、防災や危機管理の視座が広がっているため、より積極的に売り込みを図っているようです。
以上、テロ対策特殊装備展(SEECAT)、危機管理産業展(RISCON)のレポートをお届けしました。東京オリンピックが無事に開催され、自然災害もなく、また来年、同じように開催されれば、また見に行きたいと思います。(
Yahoo!より抜粋)