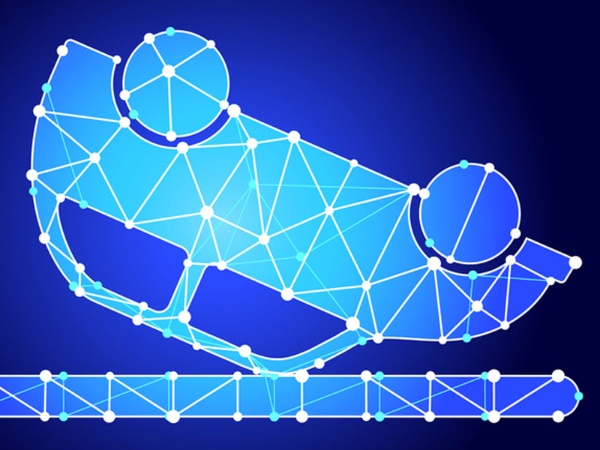形あるものはいずれ終わりを迎える。人の人生も星の一生も始まりがあれば終わりがあるのは世の理であって、この宿命から逃れることはできない。高齢社会と一口に言っても、人が亡くなることは自明として、人がどう終末を迎えるのか、周りがどう送るのかが高齢社会問題に対するひとつの視点だ。幸せを感じて安寧のうちに幕を閉じることができる人を増やせる社会が望ましいことは言うまでもない。人が人として生きていくにあたって、その最期にあたっては人として尊厳ある終わり方を迎えたいと願うのもまた、意識という恵みを持つ存在であるが故の理であろう。
本稿では認知症が引き起こす社会問題について、主に都市政策にまつわる視点から取り上げる。いままでも、高齢社会を考えるにあたって重要なパートであった認知症を患う高齢者は重要だという認識は強かったが、九州大学久山町研究を通じて2025年に日本で認知症が700万人を超える推計が発表[1]され、概ねその進捗通りの認知症を患う高齢者の増加が確認されるようになると、対策の遅れや不徹底が改めて浮き彫りになる面も出てくるようになってきた。
医療、地域、家庭でどう受け止めるか
とりわけ、日本社会における認知症の破壊的な増加は、一口に高齢化社会現象と片付けることのできない強いインパクトを持つ。それは、高齢に差し掛かった一個人が生産をやめ社会に富を生み出さなくなることだけでなく、それを支える医療や地域、家族のリソースを消費し続けることになるからだ。介護も終末期医療の問題も、突き詰めれば「人間としての社会性を失いゆく高齢者をどのように社会は受け止めるべきか」という深淵な事実に向かい合わなければならない。
その立脚点として、少なくとも2012年(平成23年)の段階ですでに自律的な生活に支障をきたしている認知症有病者が日本に462万人存在する[1]。このうち、精神科など医療機関に入院して治療を受けている人数は22万人ほどで、その過半は入院後一か月ないし半年しないうちに退院して家庭や地域に舞い戻ることになる以上、不便を感じながら自宅で家族や施設で暮らしている高齢者がそれだけいるということになる。つまり、だれか健常者の手を借りながら暮らしている認知症患者が生きていくためには、生活力や所得の乏しい本人だけでなく、本来であれば働きに出るなどして生産的な活動をしていたかもしれない誰かを巻き込んで暮らしている可能性がある。
調査結果によって推計値や結論に差はあるが、厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成25年)では認知症高齢者の家族との同居は61.6%(うち、子供や子供の配偶者の合計は33.0%)、事業者は14.8%である。自立した生活を送れている認知症患者の割合は少ない。老齢に差し掛かって伴侶・配偶者からの支援(26.2%)以外の人の手を借りて暮らしている高齢者は、年金など社会保障の収入とは別にそれだけの生産可能人口からの支援を受けながら生活していることになる。逆算すると、2012年すでに300万人ほどの日本人が認知症患者の生活支援を何らか行いながら暮らしており、2025年にはそれが500万人以上になるのであって、人口のおよそ4.6%が認知症患者を家族に持ち生産性を発揮せずに患者本人が亡くなるまで暮らしていく構図が浮かんでくる。
一連の調査において、特に認知症との関わり合いの深い疾患として糖尿病が挙げられている。認知症有病率が2012年以降一定であると仮定した場合、推定認知症患者数は2025年に675万人とされる一方、将来糖尿病の頻度が2012年以降20%上昇すると仮定した場合、将来の認知症患者数は2025年には730万人に達すると推計されている[2]。また、主たる認知症の症状であるアルツハイマー病の患者数は、各年齢層の認知症有病率が一定と仮定した場合は2025年466万人と推計され、将来の認知症患者の過半がアルツハイマー病となる予測になり、認知症予防や治療にあたっては、このアルツハイマー病由来の認知症状を緩和したり、何らかの改善を促す施策を積極的に取らなければ大量に発生する認知症患者由来の高齢者問題が続発してしまうことになる。まさに認知症対策の策定と実施は高齢化する日本社会の急務と言えよう。
また、軽度認知障害(MCI)を認知症予備軍として見込む調査も多い一方、かかりつけ医や物忘れ外来など軽度認知障害である所見がないまま、何となく家族が高齢者の物忘れに認知したころには相当程度の認知症状の進展が起きているケースも無視できない割合存在する。特に若年性認知症では本人の自覚もないうちに急速に進む症例は多数報告されており、効果的に把握したり、症状を認識して防ぐ治療を行うということがなかなかむつかしい。
もっとも重要な政策の骨子は、2015年(平成27年)に取りまとめられた「認知症施策推進総合戦略」、通称「新・オレンジプラン」だ[1]。ここでは「認知症高齢者等にやさしい地域の実現には、国を挙げた取組みが必要」としたうえで、国家が策定する認知症対策の7つの柱に沿った政策パッケージを構成しているのが特徴であり、全体としては認知症に対する理解を促す普及・啓蒙と、認知症の事前・事後の治療など医療に関する政策支援、そして認知症患者を家族に持つ人たちに対するケアという色分けがなされる。本稿で前回述べた通り、認知症を発症後、本人が意図せず犯罪を犯してしまうケースが後を絶たないことも踏まえて、医療、地域、家庭で高齢者を受け止める中で認知症問題が一際クローズアップされざるを得ない。
生まれたばかりの赤ちゃんがいきなりは社会性を備えないのと同じように、これから寿命を全うしようとする高齢者も死に向けて様々な機能を失いながら生活している。何らか保護者の世話を受けなければ生活が立ち行かない。認知症の進行の程度によっては社会性を完全に失うような状況にも容易に陥るうえ、本人の自覚症状の有無にかかわらず認知症患者が家族にいるだけで相当な家計的負担を強いる。
子供の発育状況に個人差があるように、認知症の原因や経緯も様々であって、認知症患者を保護する家族の受け入れ度合いや症状の進行スピードも異なるため、認知症患者がいるからといって介護事業のようにどこまで踏み込んでよいかの線引きが極めてむつかしい。それゆえに、認知症対策には介護問題とは別の体制が必要とされる。2015年(平成27年度)予算案から盛り込まれている内容から見ると、医療・介護専門職による認知症初期集中支援チームの配置、医療・介護連携のコーディネーター(認知症地域支援推進員)の配置等、早期診断を行う認知症疾患医療センターの整備と、生活支援コーディネーターの配置等に予算が大きく振り分けられている[4]。家族のいない認知症患者に対するケアを行うためにも民生委員やコーディネーター、認知症サポーターといった制度に従事する人たちを増やすことは急務だが、そのほとんどは薄給か無報酬でのボランティアに近い状態であって、人数的な充足も、一人当たりの活動時間の確保も、認知症その他に対るケアのスキルや知識も、爆発的に増加する認知症患者の前には追い付かない状況に陥りかねない。
「to be」と「can be」をいかにすり合わせるか
認知症対策を考える上で、特に問題となるのは認知症がもたらす生活上の機能低下がどのレベルで発生するかである。まさに政策上の「to be」(おこなうべきこと)と「can be」(起きるであろうこと)のすり合わせが求められる局面であるが、日常生活動作(ADL)レベルと要介護認定のレベルで調査する場合、脳卒中などの疾病の後遺症やがん治療中の患者などと並行してスパイラルな機能低下を起こした高齢者が不可逆に症状を悪化させ、高次脳機能障害を引き起こす状況が多数報告されている[3]。現状では、厚生労働省が介護度レベルを決定するための「1分間タイムスタディデータ」が基準となっており、根拠となっているのは高齢者約3,500人を対象として48時間にどのような介護サービスがどれ位の時間をかけて行われたかを調べて算出したデータが中心である。
しかしながら、臨床例でしばしば報告されるのは「認知症の具体的な進行度合いと、介護保険で認定されるスタディデータが必ずしも一致しない」ことにある。簡便な例では、判定員という見知らぬ人物からヒヤリングされる痴呆症高齢者が、外部の刺激を受けることでその受け答えや動作テストのときだけ「シャキッとして、普段できないこともできてしまう」ことや、日常で困っていることが口頭では「できる」と説明してしまい要介護認定のレベルが下がる傾向にある。それ故に、要介護認定のレベルで認知症問題という人間の内面、脳の機能を調査しようと思っても、なかなか実態にたどり着かないという問題を引き起こす。
認知症の進捗度を示す日常生活自立度と、介護保険を受ける上で必要な要介護認定のレベル判定とで差がある以上、本来であれば心・知覚能力と身体・生活能力とを分けて高齢者を判断し対策を打ってきた従来の政策方針を微修正する必要が出てきているのだ。
それ故に、厚生労働省が策定した「新・オレンジプラン」の中では、日常生活自立度のランクに基づいて認知症の進行度合いを示すアプローチを「発症予防」「発症初期」「急性増悪時」「中期」「人生の最終段階」としたうえで、医療、地域、家庭の役割を明確にしながら対策を立てるとしている[4]。認知症の早期鑑別の重要性についてはかねてから指摘がなされており、とりわけ「物忘れ外来」で対応されることの多いBPSD(認知症の行動・心理症状)については、入院の95.2%が患者本人での対応が困難で生活に支障をきたすため診療即日入院とする措置が取られる。
一方で、入院経過に伴い認知症症状が快癒するケースも少なくなく、入院1ヶ月時点でBPSDはほぼ改善し、BPSDの治療に要する期間は約1ヶ月が妥当と考えられるため、入院後すみやかに退院に向けてサービス調整を行う必要がある[5]。妄想や幻覚、強い抑うつ症状と不快感などNPIスコア(Neuro Psychiatric Inventory)の改善は入院後、適切な投薬治療が行われれば83%から87%程度の患者の精神状態は快方に向かう。その人たちは改善が見られれば退院してくるものの、処方される薬を飲み続けなければ再び深刻な認知症状に陥ることになるため、退院後も誰かがケアしてあげなければならない。すなわち、認知症を社会的に受け止めるためにはどうしても医療機関だけでなく家庭や地域の受け皿が必要になるのだ。
【初割・2カ月無料】お申し込みで…
- 専門記者によるオリジナルコンテンツが読み放題
- 著名経営者や有識者による動画、ウェビナーが見放題
- 日経ビジネス最新号12年分のバックナンバーが読み放題