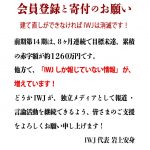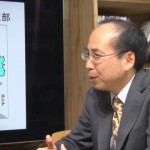- 日時 2014年3月23日(日)
- 場所 大阪大学豊中キャンパス ドイツ文学研究室(大阪府豊中市)
ロシア帝国によるユダヤ人政策
18世紀末のポーランド分割をきっかけとして、ロシアは西側に支配地域を拡張する。それまでほとんどユダヤ人が居住していなかったロシアは、一気に数十万ものユダヤ人を抱え込み、ユダヤ人対策を迫られる。「そこで代々のツァーリたちは、色々と知恵を絞り、ユダヤ人をロシア帝国にとって有用な人民に鍛えあげようとする」。
エカチェリーナ2世(1729-1796)は、「聖なるロシア」とも呼ばれる大ロシア地域へのユダヤ人の流入を食い止め、「ユダヤ人定住区域」へ封じ込めようとした。この区域は広大ではあったものの、ユダヤ人に対する差別的な扱いは増していき、「これまでポーランド貴族のもとで得ていた特権がなくなっていく」。
一方、アレクサンドル1世の統治下(1801-1825)では、ユダヤ人に対して一定の「文化的自治」を認めながら「統合」していこうとする改革が行われたが、大きな成果は見られなかった。
続くニコライ1世の治世(1825-1855)は、ユダヤ人にとって「暗黒の時代」となった。ユダヤ人に対して不寛容な内容の「600近い対ユダヤ特別法」が制定された。さらに長期間の徴兵や、カハルと呼ばれる共同体の廃止など、「半強制的にユダヤ人を臣民化しようとする政策」が押し進められたという。
ロシアはウクライナ人に対しても抑圧的な支配を行い、1876年に施行された「エムス法」によりウクライナ語の学習が事実上の禁止となった。また、ロシアへ積極的に統合しようとする一部のユダヤ人インテリと、ウクライナ人ナショナリストとの間に軋轢が生じることにもなったと赤尾氏は語る。
ユダヤ人は「資本家」かつ「社会主義者」という矛盾したイメージ
19世紀末から20世紀初頭にかけ、ロシアの支配地域ではポグロム(ユダヤ人虐殺)が頻発。背景には、ユダヤ人につきまとった「資本家でかつ社会主義者であるという矛盾したイメージ」があった、と赤尾氏は解説した。19世紀後半に進展した産業の資本主義化が、社会階層の分化を招く一方で、ユダヤ人のごく一部にも経済的に成功する者があらわれた。同時に、当時は危険思想とみなされていた社会主義の信奉者や革命家にユダヤ人が多いという認識が広まっていた。
また当時、ロシアの民衆には依然として、「『キリスト殺し』の濡れ衣や、『血の中傷』(キリスト教徒の赤子をさらって殺害し、その血をユダヤ教の儀礼に使用するといった俗説)といった中世的な流言」に影響されやすい傾向もあったという。
このような中、社会不安の責任をユダヤ人に負わせ、ユダヤ人攻撃の正当性を獲得した上で、徒党を組み行動に出る者たちが現れる。「当時、反動勢力のロシア帝政に忠誠を誓うような雑多な階層から黒百人組という極右と、不満分子の町人とが結託し、ある種の自警団を結成していた」。こうして「諸悪の根源はユダヤ人」と理由づけることで、ユダヤ人がスケープゴートとして位置づけられていった。
反ユダヤ主義へと傾斜するロシアから、多くのユダヤ人は離れることを余儀なくされる。「ロシアからアメリカなどに1880年代から1924年の間に、おおよそ150万から200万人近くがアメリカに移民として流れていく」。膨大な数のユダヤ人移民は「知的な流出」でもあったと赤尾氏は強調する。「文化、経済、あらゆる面で、ロシアの近代化を支えてもおかしくなかったような人たちを叩きだしてしまった」。
陰謀論の主役の座
世界を裏側から操る陰謀論の主役としてのユダヤ人イメージは、『シオンの長老の議定書』なる捏造書により流布された。また、ロシア革命後の内戦でボリシェヴィキ(赤軍)と対立した白軍は「革命家はみんなユダヤ人だ」という宣伝のために盛んに反ユダヤ的なパンフレットを作成。そこで拡散された歪んだユダヤ人イメージは後に西側へと伝播し、ユダヤ人迫害に突き進むナチ・ドイツの利用するところとなった。
ユダヤ人に対するこうした陰謀論や中傷は、日本も無関係ではない。「シベリア出兵で白軍のロシア兵と日本兵が極東で接触し、パンフレットが日本にも伝わる」。現在でも、誇張されたユダヤ人観が特にインターネットを通じて広まっていると赤尾氏は述べ、「『シオンの長老の議定書』をそのまま載せたり、それに絡んでアンネの日記の捏造論が持ち出されたり。完全にナチのプロパガンダと同じです」と懸念を語った。
ロシア革命とウクライナでの反ユダヤ感情
<ここから特別公開中>
ロシア革命後、ウクライナ・ナショナリストらは内戦の最中にウクライナの独立を賭けて闘ったが、その際、反革命の白衛軍とともに、帝政ロシア時代をはるかに上回る規模の残虐なポグロムを引き起こした。しかし、両軍ともに、最終的にはボリシェヴィキに敗れ、ウクライナの大部分の地域がソ連に編入された。
1920年代を通じて、ソ連領内のウクライナでは「ウクライナ化」政策が推し進められたが、スターリンの台頭とともにウクライナ化の推進者らはことごとく粛清され、30年代前半には富農撲滅キャンペーンとともに、ソ連幹部による人為的介入も引き金となった大飢饉で、ウクライナの民衆は未曽有の受難を被った。
そうした中、「30年代末ぐらいにはいろいろな形でウクライナ人の反ソ連感情、反ボリシェヴィキ感情が反ユダヤ感情とつながってくるところがある」と赤尾氏は述べた。その背景について赤尾氏は「ロシア革命がウクライナ人にとって意味したことと、ユダヤ人にとって意味したことが相当違う」と話し、「帝政時代にはウクライナ人もユダヤ人も等しく抑圧されていましたが、ロシア革命によって、少なくとも独ソ戦までは、ユダヤ人は色々な場所に進出していけた」と続けた。
教育の門戸が開かれ、大学へ進学するユダヤ人が増加。1920年代末のキエフ大学の学生のうち35%がユダヤ人だった。また、ロシアにおいてはユダヤ人とロシア人が婚姻関係を結ぶ頻度が高いのに対し、ウクライナではそのような傾向は低かった。さらに、ロシア語を母語とするウクライナのユダヤ人も急増する。
帝政ロシア時代のウクライナ人にとってユダヤ人とは、自分たち以上に抑圧された存在でもあった。それが革命を経たソ連では、ユダヤ人の「羽振りがいい」姿が目立つようになり、嫉妬心を呼ぶこともあったのだろうと赤尾氏は述べた。
ユダヤ反ファシズム委員会の活動
ナチによるユダヤ人迫害は凄惨さを極めた。一方、ナチと対決するソ連では、ユダヤ反ファシズム委員会が創設される。「主な仕事は、プロパガンダ、そして戦費調達。ロンドンやニューヨークなどの西側の都市に行き、戦費を調達してくること」。ユダヤ反ファシズム委員会は、アメリカに居住するユダヤ人富豪や文化人に接触し、莫大な資金の調達に成功した。
「この資金をスターリンはソ連軍に投じるわけですよ」。ソ連にとり、ユダヤ反ファシズム委員会の活動は、対ドイツ戦争を進める上での正当性を国際的に主張する意味で重要だった。「独ソ戦時は、ユダヤ教の復活や、正教の復活を通じ、民族文化を尊重していると西側にアピールする」。
この独ソ戦の最中、ユダヤ反ファシズム委員会を中心に、疎開していたユダヤ人の帰還先としてクリミアに「ユダヤ自治州」を建設するという構想が持ち上がる。スターリンの側近の一人であったモロトフの支持も得たこの構想によれば、ユダヤ人迫害の嵐から落ち延びたウクライナ・ユダヤ人には、帰還先として、強制退去によりタタール人のいなくなったクリミア半島が指定されるはずであった。
「西側に通じる」ユダヤ人
独ソ戦終結後の束の間、スターリンはユダヤ人の「解放者」となる。しかし、すぐさまスターリンは「西側に通じた」ユダヤ人に猜疑の目を向ける。「1949年にコスモポリタン批判が始まる。外国文化に跪拝(跪いて拝む)ということでパージされましたが、当然、対象となるのはユダヤ人が多かった。ユダヤ人は西側と通じているとされ、一番手っ取り早いスケープゴートだった」。
こうした状況下で、クリミアの「ユダヤ自治州」の構想は、アメリカとユダヤ反ファシズム委員会が結託してクリミア半島を「乗っ取る」反ソ的企てだとして、ユダヤ文化人を粛清するための口実に使われることになる。反ファシズム委員会の委員長ミホエルスが、スターリン直々の命により、1948年に自動車事故に見せかけて殺害されたことは、「分かる人には分かるシグナル」であったと赤尾氏は語る。
ただし、ここでソ連は「地政学的にイスラエルは重要だとしていた」と赤尾氏は指摘した。「ソ連、スターリンはいち早くイスラエル独立を承認しただけではなくて、チェコを通じて武器をイスラエル独立軍に送っている」。
他方、ソ連国内のユダヤ人の運命は悲惨なものとなった。「49年にイディッシュ文化の優れた作家、詩人、俳優などが、ほとんど捕まり、52年に銃殺されています」。
「反ソ連的シオニスト」の烙印:戦後のロシア・ユダヤ人の運命
赤尾氏はスターリン没後のソ連のユダヤ人が置かれた境遇を次のように語る。「身の危険まではさすがに感じなくなりましたが、フルシチョフ時代、ブレジネフ時代、ペレストロイカまでは、ユダヤ人は個人として差別される。パスポートに『ユダヤ人』というスタンプがあると、それだけで職場差別がある」。
また、ユダヤ教やユダヤ文化を自由に発展させることもままならなかった。「ヘブライ語を勉強してはいけない。違反すれば、反ソ的、シオニストとされた」。
同時期に、ホロコーストやスターリン時代以降のソ連の反ユダヤ主義の高まりに直面し、民族意識に目覚めたユダヤ人のあいだで、ソ連からの出国を望む声が高まった。ソ連当局はユダヤ人の出国に制限をかけたが、その理由について赤尾氏は、ユダヤ人が「出て行けばソ連批判をして、西側の反ソ勢力を強めるだけであるとみなされた」し、そもそも出国する者が後を絶たなくなればソ連という国家の失敗を印象づけることになるからだろうと述べた。
ウクライナ人とユダヤ人の連帯意識
赤尾氏によれば、ユダヤ人とウクライナ人の連帯意識を語るときに知識人の間で象徴的に語られてきた事象の一つが「バービイ・ヤール」だという。
「バービイ・ヤールというのは、キエフ近郊にあるユダヤ人の虐殺現場。ここで10万人近くのソ連市民が殺され、うち4万人近くがユダヤ人でした」
バービイ・ヤールでのユダヤ人虐殺を、ソ連当局は歴史から消し去ろうとした。「キエフ解放後、ワシーリー・グロスマンとイリヤ・エレンブルクが独ソ戦当時のウクライナ地域でユダヤ人が置かれた状況に関して取材し、『黒書』としてまとめますが、これがお蔵入りになってしまう」。赤尾氏は続ける。
「なぜなら、ウクライナ人などのコラボレーターの、ナチに加担したソ連市民の記述があまりに多すぎた。さらに、独ソ戦でユダヤ人だけが受難したということは、絶対にソ連当局は認めようとしなかった」。つまりソ連の公式の見解では、大祖国戦争で諸民族はみな苦しんだということになっていた。この見解に『黒書』の内容は反するので、ソ連国内で発表することは不可能だったのだ。
そんな状況の中、ウクライナの詩人・エフトゥシェンコは「バービイ・ヤールに記念碑はない」「私は、ユダヤ人のように感じる」とうたう詩を書く。この「バービイ・ヤール」という詩はショスタコーヴィチの交響曲第13番の重要なモチーフとなったことで有名だ。さらに、バービイ・ヤール近辺で生まれ育った作家・クズネツォフは、実体験をもとに小説『バービイ・ヤール』を書く。
この3人はいずれもユダヤ人ではないことを赤尾氏は指摘し、「ユダヤ人の受難を祈念する最大の功績者が、ウクライナ人であり、ロシア人であった」と述べた。
一方、前出のユダヤ系作家のグロスマンには、ウクライナ人にとっての「受難」であるウクライナ大飢饉を扱った作品がある。「『万物は流転する』という中編小説では、密告の問題など、ソ連の圧政をレーニンまでさかのぼり徹底的に糾弾した。生前には発表されませんでしたが、この小説の中でウクライナの大飢饉の問題を克明に描いている」と赤尾氏は解説。「知識人レベルでは非常に良い関係もあるのですね」と語った。