ヴィッキー・ウミペグさんは、妊娠22週の早産で、体重わずか1.4キログラムで生まれました。保育器内の高濃度の酸素が原因で視神経が損傷し、完全に視力を失いました。彼女は視覚はまったくなく、光も認識できまないまま生きてきました。
22歳のとき、シアトルで交通事故に遭い、車外に投げ出されました。その事故で頭蓋骨の骨折や脳震盪、首、背中、脚に重傷を負いました。救命処置を受けている間、彼女は自分が天井の方へ浮かび上がっていく感覚を味わいました。
そのとき、彼女は360度の視界を持ち、金属製の手術台に横たわる女性の体を目にしました。男性と女性の医療スタッフがその女性を救おうとしていました。そして、その女性の手に付けている特徴的な結婚指輪に気づいた瞬間、それが自分の指輪であると理解し、手術台の上の女性が自分自身であることを認識しました。
生まれてから一度も目が見えなかった彼女にとって、この臨死体験は初めて自分の指輪や身体を見る機会となりました。
このヴィッキーさんの体験は、ケンタッキー州で放射線腫瘍医を務めるジェフリー・ロング博士によって研究されました。ロング博士は25年以上にわたり臨死体験を研究し、4千件以上のユニークな事例を調査して、Near-Death Experience Research Foundation(臨死体験研究財団)のウェブサイトで公開しています。
ロング博士は、これらの研究から臨死体験に共通する体験を次のようにまとめています。このリストは「臨死体験の父」と呼ばれるレイモンド・ムーディ博士の研究結果とも一致しています。
- 体外離脱(自分の体を外から見る体験)
- 痛みが完全になくなる感覚
- トンネルを通って明るい光に向かう体験
- 亡くなった愛する人に会う
- 自分の人生を詳細に振り返る
- 圧倒的な愛や平和を感じる
ヴィッキーさんの体験は、この中でも典型的な「体外離脱」に分類されます。特に360度の視界という現象は、多くの臨死体験者が共有する特徴でもあります。
360度の視界
エポック・タイムズとの最近の対談で、ロング博士は視覚障害を持つ女性との会話を振り返りました。
「彼女は臨死体験中に360度の視界を持ち、前、後ろ、右、左、上、下のすべてを同時に認識し、処理することができました」とロング博士は語りました。
「実際、私はヴィッキーさんに、私たち地上に生きる人間は、目の位置の関係で視界が限られているんだと話しました。すると彼女は大笑いしました。というのも、彼女が臨死体験中に持った視覚は完全な360度、つまり球体のような視界だったからです」
また、ヴィッキーさんはもともと数学や科学に馴染みがありませんでしたが、臨死体験を経て直感的に微積分を理解し、惑星がどのように形成されるかについても把握できるようになりました。さらに、科学、数学、生命、惑星、そして神に関する疑問への答えが自然と湧き上がり、以前は知らなかった言語も理解できるようになるなど、知識を次々と得たといいます。
幻想から現実へ
過去、臨死体験を語る人々は、科学界からしばしば妄想や宗教的影響を受けたものとして片付けられていました。しかし、ここ数十年でその見方は大きく変わりました。
1978年、5人の医師や科学者が協力して「国際臨死体験学会(International Association for Near-Death Studies)」を設立しました。このメンバーには、科学修士号を持つジョン・オーデット氏、ブルース・グレイソン博士、レイモンド・ムーディ博士、社会心理学の博士号を持つケン・リング氏、そしてマイケル・セイボム博士が含まれていました。この学会の設立によって、臨死体験を科学的に研究する道が開けました。
「臨死体験について初めて聞いたのは、私が研修医だった何十年も前のことです」とロング博士は語ります。「その時、世界で最も権威のある医学雑誌の一つ、『Journal of the American Medical Association』に掲載された記事を偶然目にしました」
「私は癌に関する記事を探して雑誌をめくっていたのですが、偶然にも『臨死体験』という言葉が記事のタイトルに出てきたのです。その言葉に困惑しました。医大で学んだことでは、命は『生きている』か『死んでいる』かのどちらかでしかないと教えられていましたから」
その記事は心臓専門医のマイケル・セイボム博士によって書かれたもので、心停止や昏睡状態から生還した人々を研究した内容でした。患者の中には、意識が体を離れ、意識を失っている間に何が起こっているのかを見ていたと報告する人々がいたそうです。そして彼らが目撃したことは、細かい部分まで正確でした。
その数年後、ロング博士の大学時代の友人の妻が、自身の詳細で驚くべき臨死体験を彼に語りました。
「彼女は全身麻酔での手術中、アレルギー反応で心停止を起こしました」とロング博士は説明します。
「その瞬間、彼女は体外離脱を経験し、手術室の混乱を目撃し、心拍を監視していたEKGのアラーム音を聞きしました。そしてトンネルを通り抜けた後、地球とは異なる世界に行き、そこで何者かと出会いました。その場で、彼女は自分の人生に戻るかどうかを選択する機会を与えられました。彼女はその存在たちに助言を求め、話し合いの後、自分の体に戻ることを決めました。そして無事蘇生したのです」
ロング博士は、この不思議な現象についてもっと研究する人がなぜいないのか疑問に思い、臨死体験の事例収集を始めました。現在では4千件の臨死体験が記録されたデータベースを構築し、「世界で最も大規模で公開可能な臨死体験のコレクション」として管理しています。
さらに博士は、臨死体験者に直接アンケートを実施し、その体験の現実性について尋ねました。その結果、回答者の約95%が「自分の体験は間違いなく現実だった」と答えました。
30の否定的仮説
ロング博士によると、臨死体験に懐疑的な人々は、これまでに30以上の説明を提案してきました。
「懐疑的な説明がこれほど多い理由は非常にシンプルです」とロング博士はエポックタイムズに語ります。「それらの説明のどれも、臨死体験中に起こることを説明できていないからです。それどころか、体験の一部さえも説明できません」
臨死体験を否定するために、低酸素症(酸素レベルの低下)や高炭酸ガス症(二酸化炭素レベルの増加)による幻覚という仮説が提唱されました。しかし、この仮説が失敗する理由は明白です。「医学的に言えば、それは混乱や意識の低下を引き起こします。意識が鮮明になることはありません」とロング博士は述べています。
医学誌『ランセット』の研究では、心停止や臨床的な死から蘇生した数百人の患者を調査しました。そのうち18%の患者が臨死体験を報告しています。研究者は、もし脳の低酸素症が臨死体験の原因であるなら、臨床的に死亡状態になった全員が低酸素状態にあるはずなので、大多数の患者が臨死体験を持つはずだと指摘しました。しかし、実際にはそうではありませんでした。
また、脳が自然に生成する麻薬様物質であるエンドルフィンが臨死体験を説明できるという意見もあります。しかし、ロング博士はこれについて、「エンドルフィンはイベント後1時間以上にわたって痛みを和らげる効果を発揮しますが、これは臨死体験の特徴とは一致しません」と述べています。
「臨死体験では、体に戻った瞬間、痛みが完全に戻ってきます。痛みが和らぐことはありません」とロング博士は説明しています。
さらに、てんかん発作を原因とする説も提案されましたが、ロング博士はこう反論しています。「発作は一般的に意識の低下や大きな変化を引き起こしますが、臨死体験で見られる鮮明で一貫した体験とは全く異なります」
アメリカ臨床神経生理学会の元会長であるアーネスト・ロディン氏もこうコメントしています。「30年以上にわたる専門的なキャリアの中で、側頭葉てんかんの患者を何百人と診てきましたが、臨死体験のような症状を発作の一部として見たことは一度もありません」
さらに、『ランセット』の研究は、患者の薬物使用や死への恐怖が臨死体験に関連していないことを結論付けました。
「二重の不可能」
臨死体験は、全身麻酔下でも記録されています。
「全身麻酔下では、明晰で秩序だった意識的な体験が起こることは本来あり得ません」とロング博士は述べています。
全身麻酔中に心停止を起こした人々の中には、臨死体験を体験したと報告するケースがあります。この場合、ロング博士によれば、「意識的な体験が起こることは二重に不可能であるはずです」。それにもかかわらず、彼らは他の臨死体験者と同じように、非常に明晰で、鮮明で、極めて高い意識状態を経験しているのです。
「このことは、ほぼ単独で、臨死体験が脳の物理的な機能によるものである可能性を完全に否定します」とロング博士は付け加えました。
文化、宗教、年齢を超えて
臨死体験に関する仮説の一つに、心理的モデルがあります。これは、臨死体験が個人の宗教的、文化的背景や死に対する想像に基づくものだとする説です。しかし、多くの人々が自分の人生経験や死に関する信念と一致しない臨死体験を報告しています。
一部の人は、臨死体験が文化によって決定されると主張します。しかし、ロング博士はこう述べています
「世界中どこで起きても、臨死体験の内容は驚くほど似ています。それがエジプトのムスリムであれ、インドのヒンドゥー教徒であれ、アメリカのキリスト教徒であれ、あるいは世界のどこかの無神論者であれ、どんな信念体系を持っていようといまいと、臨死体験中に起こることは非常に似通っているのです」
1976年に中国で発生した唐山地震の後、中国の科学者たちは、西洋で記録された臨死体験と似たパターンを観察しました。81人の生存者のうち、65%が思考の明晰さの向上を報告し、43%が肉体からの分離感を体験し、40%が無重力感を感じたとされています。これらの体験は、年齢、性別、職業、地震前の健康状態に関係なく、共通していました。
また、ロング博士は、平均年齢が3.5歳という5歳以下の子供たちのグループを調査しました。彼はこれを「ほぼ文化的な白紙状態」と表現しています。「これらの非常に幼い子供たちの臨死体験の内容は、年長の子供や大人の体験内容と驚くほど似ています」と述べています。
神との出会い
半世紀以上前から臨死体験を研究しているレイモンド・ムーディ博士は、多くの体験者が「光の存在」と呼ばれる輝く存在と出会ったと語っていることを指摘しています。このことは、彼の著書『Life After Life: The Investigation of a Phenomenon—Survival of Bodily Death』(邦題:『かいま見た死後の世界』)にも詳しく記されています。
この「光」は、目に痛みを与えない非常に明るく、言葉では表現できない輝きとして描写されることが多いです。多くの人は、この光を愛と温かさに満ちた高次の存在、もしくは「神」として感じると言います。
ヴィッキーさんも、自身の臨死体験の中で、驚くほど輝く姿をした存在を見たと報告しており、それがイエス・キリストであると認識しました。
「神」の存在に関する真実をさらに探るため、ロング博士は2011~14年の間に、多様な職業や背景を持つ人々の420件の臨死体験を基に研究を行いました。臨死体験をする前には、39%の人々が「神の絶対的存在」を信じていましたが、臨死体験を経験した後にはその割合が72.6%に増加しました。この結果、神の絶対的存在を信じる人の数は86%増加し、神への信仰が大幅に強まったことがわかりました。これらの研究結果は、彼の著書『God and the Afterlife: The Groundbreaking New Evidence for God and Near-Death Experience』(邦題:『神と死後の世界』)にまとめられています。
ロング博士は、277件の「神との出会い」を慎重に分析し、記述には顕著な一貫性があることを発見しました。それは、愛と慈悲に満ちた至高の存在が放つ圧倒的な愛と恩寵の感覚です。
臨死体験において「神」との出会いでよく見られる特徴として、まず挙げられるのが「判断の欠如」、つまり無条件に受け入れられる感覚です。また、その人自身がありのままの姿で受け入れられているという感覚も共通しています。さらに、多くの体験者は神との一体感や統一感を強く感じると報告しています。
また、こうした体験での「神」とのコミュニケーションは、ほとんどの場合、言葉を用いずにテレパシーのような非物理的な方法で行われるとされています。
希望に満ちたメッセージ
ロング博士は、臨死体験の研究に取り組む前から、「私たちは何者なのか?」という問いに頭を悩ませていました。彼は、人間は単に脳の物理的な働きだけで成り立つ存在ではないと感じていたのです。
臨死体験の研究によると、意識は体を超えて存在し、より永続的なものだという圧倒的な証拠が示されています。ロング博士は、「私たちはただの制約された機械的な存在ではなく、今の理解を超えた無数の可能性を持つ生命体なのです」と述べています。
そして、これこそが「人類すべてにとって最も希望に満ちた力強いメッセージ」だと彼は強調しています。
この記事で述べられている意見は著者の意見であり、必ずしもエポックタイムズの意見を反映するものではありません。エポックヘルスは、専門的な議論や友好的な討論を歓迎します。












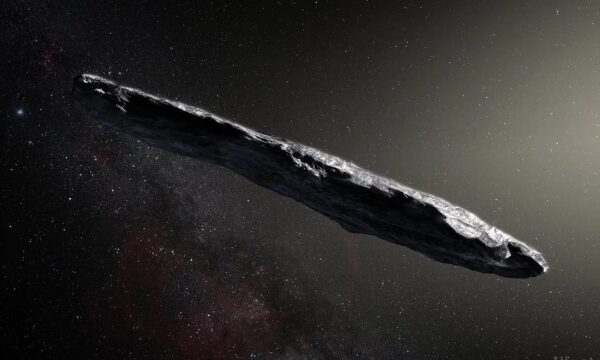







 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。