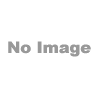KANA-BOON Jack in tour 2022 ゲスト:ストレイテナー @Zepp Haneda 10/22
- 2022/10/23
- 19:40
今年復活作と言っていいであろうアルバム「Honey & Darling」をリリースし、全国をツアーで回ったKANA-BOONの次なるアクションは対バンツアー。各地のZeppに盟友や先輩を招く今回のツアーの東京はZepp Hanedaにてストレイテナーを迎える。アジカンに影響を受けて始まったバンドであるだけに、ストレイテナーのシルエットを追ってきた部分も間違いなくあるだろう。
本来はファイナルがこの日だったが、名古屋が翌週に延期になったことによってこの日はセミファイナルに。すでに開催された大阪でのキュウソネコカミとの対バンが行った人のツイートを見るたびに行けば良かった…と悔いているだけにこの日がより楽しみである。
オールスタンディングの立ち位置指定もなしというライブハウス本来の姿に戻りつつある客席には開演前にKANA-BOONの小泉貴裕(ドラム)による影アナの前説が流れる。かつて小泉は学生時代にナカヤマシンペイに憧れてストレイテナーのカバーをやっていたらしいが、明らかにそのアナウンスが慣れていないというか、漢字がちゃんと読めないのがバレてしまうような感じすらあり、この影アナのやり取りはかつて映像作品で試みた「とにかくカッコいい小泉」の空回りっぷりを思い出させる。客席からもどこか失笑的な笑い声が漏れていた感じがする。
・ストレイテナー
そんなKANA-BOONに招かれた、大先輩のストレイテナー。4人がステージに登場すると、ドラムセットの椅子の上に立ち上がるナカヤマシンペイ(ドラム)がウインドチャイムを鳴らして始まるのはいきなりの「Melodic Storm」で、客席ではたくさんの腕が上がるというのはこのバンドを見るためにこの日こうして足を運んだ人もたくさんいるということがわかるのだが、その腕の振り上げ方がシンペイのリズムに対して裏で拍を取っている人はガチの普段からテナーのライブに行っている人だなということもわかる。かつては観客が合唱していたコーラスパートまでも全て自身で歌うホリエアツシ(ボーカル&ギター)の歌唱もさすがの安定感であるが、今年からマイクがヘッドセットではなくて通常のマイクに戻ったシンペイのコーラスがホリエのボーカルに重なることによって、我々が一緒に歌えなくても寂しいと感じることはない。
さらにはホリエがタイトルを口にした「From Noo Till Dawn」ではホリエは歌詞を変えることなく原曲のままで歌うのであるが、ひなっちこと日向秀和(ベース)の演奏している時の表情が実に楽しそうなのが、メンバー全員がこの日のライブを心から楽しみにしていたということが伝わってくる。
もうすっかり肌寒くもなってきつつある時期であるが、ライブハウスの中は季節が関係ないと言わんばかりにタンクトップ姿のシンペイがリズムを刻むのは実に久しぶりに聴く感じがする「KILLER TUNE」。そのサウンドは例えば「DISCOGRAPHY」が年月を経るごとにアレンジされて形を変えていくように、軽快なリズムの中にもどっしりとした安定感と重さを感じさせるようになっている。OJこと大山純(ギター)も間奏ではステージ前まで出てきてギターを弾きまくっているが、テナーの代表曲が今のバンドの状態によって今のバンドとしてのリアルな形にアレンジされてきていることがよくわかる。
「俺たちストレイテナーって言います!初めて見る人たちもたくさんいるだろうけど、今日来ているお客さんにわかりやすく言うと、アジカンの同期のバンドです!」
という、KANA-BOONファンにも実にわかりやすい自己紹介をすると、最新ミニアルバム収録の「宇宙の夜 二人の朝」で、過去の代表曲たちと変わることのないギターロックバンドとしてシーンの最前線に立ち続けているテナーの姿を示すと、「叫ぶ星」ではイントロからまさに星が泣き叫ぶようなギターを弾いていたOJが両腕を振って踊るような仕草を見せる。広いZepp Hanedaのステージを大きく動き回りながらギターを弾く仕草も含めて、OJも気合いが漲っていることが伝わってくる音とパフォーマンスである。
するとホリエがギターを下ろしてキーボードを弾きながら歌うのは「Braver」なのだが、ここまでのギターロック曲以上に力強くシンペイが腕を振り下ろすようにしてドラムを叩いていることによって、決して速くも激しくもないこの曲がそのタイトルにふさわしい力を獲得しているし、近年のシンペイのドラマーとしてのさらなる覚醒っぷりが最も顕著に感じられる曲がこの曲だと思える。テナーのリズムと言えばとかく超人ベーシストであり、リズムだけでなくメロディまでも兼ねているかのようなひなっちのベースが牽引してきたイメージが強いが、それも少しずつというかドラスティックに変わってきつつある。それはコロナ禍になってドラムの腕だけではなくてフィジカルそのものを見つめ直してきたシンペイの努力によるものと言っていいだろう。
かと思えばそのままホリエがキーボードを弾きながら歌う「さよならだけがおしえてくれた」では今のテナーのメロディが持つ包容力と優しさを感じさせてくれる。それは今やKANA-BOONをはじめとしていろんなバンドたちが背中を追うようなベテランバンドになったからこそ獲得できたものとも言えるのだが、ステージ背面に照明が当たることによって光の粒のように飛び散る演出が感じさせてくれることでもある。
そんなテナーの最新形と言える、「宇宙の夜 二人の朝」とともに昨年リリースのミニアルバム「Crank Up」に収録された「群像劇」ではやはりステージ上を軽やかに舞うように動き回りながらギターを弾くOJが曲終わりにもギターをジャラーンと鳴らすのであるが、ホリエはリハで鳴らしていたという終わり方が好きらしいのだがOJがそれを全くやってくれないということを語りながら、
「まだフェスモードみたいな感じが抜けきってないから、こうして2マンライブで持ち時間が長いと「もう10分短くてもいいのに」って思う(笑)」
と、むしろ持ち時間が長いとたくさん曲聴けるから嬉しいんですけど、とファンに思わせながら、
「今日、楽屋で鮪君が急に距離を縮めようとしてきて(笑)ソファで俺の隣に座ってたんだけど、他の3人が立ちっぱなしで「これでいいのかな?」って思いながら(笑)、鮪君が下ネタとかまで言ってくるんで、僕は下ネタNGなんでって伝えて(笑)」
と、初めてライブを見る人が多いからか、何故か清純なキャラを作りながら、季節関係なく夏フェスとかでも演奏されることもある「冬の太陽」がやはりこの時期に聴くことによって、冬晴れの日のカラッとした太陽の輝きを感じるような時期になってきたなと思わせながら、緩急で言うならば緩の部分を終えて急の部分に転じてきていることを感じさせる。それがハッキリとわかるくらいの流れを作ることができる持ち時間の長さを与えてくれたのはKANA-BOONのテナーへのリスペクトあってこそだろう。
そんなアッパーな流れはホリエがギターをかき鳴らしながら歌い始めた「シーグラス」で極まり、シンペイはその歌い出しで再びドラムセットの上に立ち上がって観客を煽るような仕草をする。その直後に座ってドラムを叩き始めると、ひなっちと顔を見合わせながら笑顔で演奏している姿が今のテナーがさらに最高な状況にいることを実感させてくれる。また来年の夏に全国各地のフェスでこの曲を聴いて、
「今年最後の海へ向かう」
というサビのフレーズを噛み締めたいなと思う。
そんなテナーはこの後には謎のBBQ好き新人バンドの633と一緒にツアーを回ることを告知する。ここでは敢えて突っ込むことはしないけれど、果たしてそのライブではどんな設定になってそれをこの演技とか全然出来なそうな4人が演じるのかというのも楽しみなところである。
そうした場所での再会を約束してからホリエがアコギに持ち替えて演奏された「彩雲」の穏やかなサウンドがこうしてテナーのライブを見ることができているということの幸せを噛み締めさせてくれると、最後に演奏されたのはKANA-BOONという自分たちに憧れてくれた後輩とそのファンたちに、ギターロックバンドとしてカッコいい背中を見せるかのような「REMINDER」。「記憶」をテーマにしたその曲がこうして最後に演奏されたからこそ、こうしてこのツアーの東京にテナーが出演して、これ以上ないくらいの横綱相撲的なライブを見せてくれたことを忘れることはないだろうなと思った。時には「丸くなった」「昔みたいな曲をやってほしい」とか言われることもあるだろうけれど、テナーは今でもずっとカッコいいギターロックバンドのままだ。それは演奏が終わった後にシンペイがドラムセットを乗り越えるようにしてステージ前まで出てきて4人で並んで肩を組むシルエットの美しさの変わらなさからも確かに感じることができる。
ホリエが口に出したアジカンのように、ずっとメンバーが変わることなく活動し続けるというのはKANA-BOONにとっても、他の後輩バンドからしても大きなランドマーク的な存在に映ると思う。でもテナーはメンバー脱退とかとは全く逆に、2人で始まったバンドが1人ずつメンバーが増えてこの4人になったという独特すぎる経緯で活動を続けてきたバンドである。つまりは変わってきたけれど、悲しい別れなどは全く経験してこなかったという特異なバンドである。
そんなバンドだからこそ、変わることは悪いことではない。むしろ変わることは進化であるということを、自分たちが活動を続けることによってその背中で示すことができる稀有なバンドである。アジカンやELLEGARDENほど時代を作ったという存在ではないけれど、その在り方はその同志たちに負けないくらいにたくさんのバンドに勇気を与えてきたはずだと、こうして憧れてきた後輩に呼ばれた立ち位置でのライブを見て思う。
・KANA-BOON
1.Melodic Storm
2.From Noon Till Dawn
3.KILLER TUNE
4.宇宙の夜 二人の朝
5.叫ぶ星
6.Braver
7.さよならだけがおしえてくれた
8.群像劇
9.冬の太陽
10.シーグラス
11.彩雲
12.REMINDER
・KANA-BOON
そんな先輩のストレイテナーがさすがと言えるライブを見せてくれた後のKANA-BOON。SEがやたら賑やかなパーティーチューンと言えるような曲になっている中でメンバー4人がステージに登場すると谷口鮪(ボーカル&ギター)が、
「今日はテナブーンです。よろしくお願いします!」
と挨拶すると、もうこのイントロを聴くだけで胸が熱くなるギターを、デビュー時から全く変わらない黒ずくめの衣装を身に纏って弾く古賀隼斗(ギター)が早くもステージ前に出てきて少しでも観客の近くに来る「シルエット」からスタートするという展開。パーマの当たり具合が強くなった鮪のハイトーンなボーカルも実に伸びやかに響くのであるが、マーシーこと遠藤昌巳(ベース)のコーラスが曲を彩るという意味では実に重要な役割を担っている。それによってこの大名曲がそのポテンシャルをフルに発揮することができているというか。うねるようなベースプレイも含めて、まだ加入したばかりであるがすでにKANA-BOONの音楽とライブを支える存在になっている。
さらに「フルドライブ」でも古賀と遠藤が前に出てきて観客を煽るように演奏し、その姿に反応した観客も踊りまくる。この飛ばしっぷりは完全にタイトル通りのフルドライブっぷりであるが、当時は4つ打ちロックとディスられることもあったりしたけれど、それでもこうして今聴いているとそんなことを飛び越えるくらいに圧倒的にKANA-BOONは曲が良い。それが今でもこうして広いステージに立てている理由だろう。
さらには「Torch of Liberty」と立ち上がりからバンドは完全にフルスロットル、観客をもそうさせるような、この日を最高なものにしてバンドもここにいる全員も楽しいと思わせるという意識が伝わってくる。観客が声を出せないからこそ、この曲での遠藤の勇壮なコーラスは本当に大事な役割を担っているし、古賀が前に出てきてギターを鳴らすと鮪が古賀の立ち位置にまで行ってギターを弾きまくる。憧れの先輩が自分たちのツアーに出てくれた後という気合いが入りまくっているのもよくわかるが、とにかくメンバーがこうして音を鳴らしているのが楽しそうで仕方がないし、その姿や表情が我々をさらに楽しくさせてくれる。
そのバンドのテンションの高さはライブ前からだったようで、テナーのリハーサルをずっと見ていてその機材の多さに驚きつつ、ホリエが楽屋に向かうドアを開けようとした時に全然開かなかった姿を見て、
「ホリエさん、それ押すんじゃなくて引くんです」
とツッコんだというホリエの天然エピソードを開陳すると、
鮪「もう俺は今日はホリエさんにべったりで。楽屋でもずっと隣にいた。LINEも聞いたし」
古賀「お前楽屋に入ってすぐに聞いてたよな(笑)初手でいくかそれっていう(笑)」
鮪「マーシーはいつも対バンの時には自分で挽いたコーヒーを差し入れて距離を詰めようとするんやけど、シンペイさんがコーヒーアレルギーやったり、OJさんに「今はいい」って言われたりして不発やったな(笑)
ひなっちさんには一緒に登山に誘われてたけど行くの?」
遠藤「…行きます!」
鮪「じゃあみんなで行く?足腰鍛えないと!」
というテナーを好きで仕方がない気持ちが溢れ出るMCが愉快なものになるのもKANA-BOONのメンバーの人間性によるものであるが、登山に向けて足腰を鍛えるべくリズムを足で取る「Dance to beat」はその通りに鮪も古賀も遠藤も足を踏み鳴らすようにして演奏するのであるが、「Honey & Darling」のアルバム曲がこうしてアンセム連打の流れの次に演奏されるというのがメンバーのアルバムへの自信を伺わせる。それはフェスなどでもセトリにアルバム曲を多数入れていたことからもわかることである。
そんな中で遠藤のうねるようなベースラインが紫を基調とした照明とともに妖しい空気を作り出すのは「talking」。かつてシナリオアートとのスプリット盤収録曲としてリリースされ、バンドの演奏力の向上に繋がったそれまでのKANA-BOONにはなかった曲であるが、こうして今のバンドの技術で演奏されることによってKANA-BOONの今の演奏技術の高さとこうした疾走感あるギターロックとは違うタイプのサウンドの曲における表現力を感じさせてくれる。
そんなKANA-BOONはやはり2000年代中期頃のアジカンやテナーが作ったギターロックシーンに強い影響を受けたバンドであり、自分たちが中堅と言っていい立ち位置になってきたことによって、そうした先輩たちから受け取ってきたバトンの欠片を次の世代にも渡していきたいということを話す。ルーツがハッキリと見えるKANA-BOONだからこそ、そうして音楽の継承に自覚的なのだろうし、そうやってバンドが、音楽が絶えず続いていくということをわかっているのだ。
そんなMCをしたからこそ、観客は一つの曲が頭に思い浮かんでいたと思うけれど、その想像通りにいかないことも多々あるバンドなのだが、この日はそのMCの流れ通りに久しぶりに「バトンロード」を演奏する。やはり古賀がステージ前に出てきてフック満載のギターを弾きまくるのだが、親から子へ物語が継承されていく「NARUTO」〜「BORUTO」というKANA-BOONの存在を広く知らしめたアニメの主人公と今のKANA-BOONは同じ位置にいると言える。NARUTOが成長して息子にバトンを渡したように、KANA-BOONもまた次の世代へとバトンを渡す存在になったからこそ、今こうしてこの曲を聴くのがより一層響くものがある。
それを本人たちもわかっているからこそ、
「俺たちってもう若手バンドじゃないの?って思ったりもするけど(笑)、ストレイテナーが俺たちに背中を見せてくれているように、俺たちも後輩バンドにカッコいい背中を見せられるように。俺たちの中で1番カッコいい曲をやります」
と言って演奏されたのは、ジャーンと鳴らされるイントロで逆光的な照明に照らされる姿だけでもカッコ良さを感じさせる「まっさら」なのであるが、後に本人も言っていたようにシンペイに影響されて小泉が思いっきり腕を振り下ろす力強いドラムを叩く。それはまさにこれまでのKANA-BOONを更新するようなカッコいいロックバンドの姿であるのだが、鮪の最後のコーラスフレーズでの圧巻の声量と伸びやかさも含めて、日々いろんなバンドのライブを見ている身としても、今のKANA-BOONほどロックバンドの、人間としての生命力を感じさせてくれるバンドはいないと思う。それくらいに人間の生きている力がその音から感じられる。それは今でもまだ無邪気な、幼く見えることばかりのKANA-BOONも今に至るまでに本当に様々なことを経験してきて、そうした人生が鳴らしている音に滲み出ているからだ。見ている側からしてもキツいこと、辛いこともたくさんあったバンドだけれど、その経験が間違いなく今のバンドの強さへと昇華されている。この「まっさら」には特にその強さが宿っている。真っ白な照明の光がそのまま人間の生命の光として感じられるかのように。
そんなKANA-BOONの新曲としてすでに「BORUTO」の新テーマソングとしてオンエアされているのが「きらりらり」であるのだが、そのアニメや原作を見ている、しっかりストーリーやキャラクターまで理解・把握しているからこそ描ける、使える歌詞やフレーズの数々はもちろん、今のKANA-BOONにとっての「シルエット」と言えるような、
「大事にしてたものを持って大人になった」
という歌詞は、BORUTOが成長するとともにKANA-BOON自身が成長した、大人になったことをタイトル通りにとびっきりの煌めくメロディで歌うのであるが、さらに
「目の前にあった」
というフレーズを歌う際に鮪はステージ袖を指差した。それはストレイテナーが自分たちの目の前で追うべき背中を見せてくれたからだ。「BORUTO」のテーマソングでもありながら、今のKANA-BOONにとってのテーマソングでもある。この曲は我々ファンが長く愛していける曲になっていくだろうと思うとともに、バンドにとっても大切な曲になっていくはずだ。それは「シルエット」がそうであるように。
そんな新曲を披露した後には鮪が次の曲に繋がるようなギターを鳴らすのであるが、そこに古賀もギターを被せてきたことによって鮪が
「俺のターンやんけ!被せてくるなよ!」
と言ってやり直すのだが、次は遠藤がベースを被せてまたやり直し、最後にも小泉がドラムを被せるがそれはもうそのまま曲のイントロへ…という形で始まったのは「ないものねだり」であり、客席からは完璧なリズムの大きな手拍子が起こり、それは観客が声を出すことができない近年は間奏部分でもコール&レスポンスではなくて観客の手拍子だけでリズムを支えるという展開も鮪が説明するまでもなく完璧に出来ているというあたりはやはりこの曲はもう完全にロックシーンのアンセムと言っていい曲になっているんだなと思える。
鮪と古賀が至近距離で向かい合ってギターを弾き合う姿もこの2人の絆を感じさせる。鮪が活動出来なかった時期にきっと1番バンドを背負ってメディアに出演したりしていたのはこの古賀だろうから。その古賀の思いを鮪もきっと理解しているはずだ。
そんなアンセム連発のライブの最後に演奏されたのは「ネリネ」という意外な選曲なのだが、それはかつてこの曲を収録したミニアルバムが「冬盤」としてリリースされたこと、ネリネ(彼岸花のこと)の咲く時期が秋から冬であることを踏まえての選曲だと思われるのだが、バンドの演奏も軽やかさを感じさせるものであるだけに観客も体を揺らしながら、
「歌いながら 踊りながら
進め 旅はまだまだこれから
単純な心のままに
鳴らし続けるよ 歩き続けるよ」
という最後のサビのフレーズはこれからもKANA-BOONが音を鳴らし、歩き続けていく意思を示すものでもあった。リリース時から名曲としてファンに親しまれてきた曲であるが、それが本当に大きな意味を持つような曲になったんだなと今にして思えるようなものになったのだ。
アンコールではメンバー全員がツアーTシャツに着替えて登場するのだが、古賀がツアータオルを忘れてしまったことによって遠藤のタオルを借りて物販紹介をする。その間にスタッフがさりげなく古賀のアンプの上にタオルを置いていたのをメンバーは気付いていなかったが観客は見ていたので古賀が
「え!?タオルあるやん!」
とビックリしていたのが実に古賀らしくて面白かった。
そうして物販を紹介するのも鮪は
「記憶は薄れていってしまうから、物として持っておくことで手にした時にこの日のことを思い出すことができる。それは俺も配信で音楽を聴くけど、CDも同じ」
と、来月リリースされる「きらりらり」をこのご時世でも今まで通りにCDとしてリリースすることを語るのだが、
「君たちが10年くらい経って結婚したとしよう。その時に棚にしまってある、ひび割れたり歌詞カードがぼろぼろになったCDを手に取ることによって…」
とやたら詳細な設定で話し始め、古賀に
「入り込みすぎやない?(笑)」
と突っ込まれるのだが、それは
「手に取れるものだからこそ愛することができる」
という鮪の一貫した姿勢によるものだ。それは自分自身もCDを今でも購入し続けているリスナーであるだけに本当によくわかる。そのCDを買った時の状況とその曲を聴いた時の記憶がそのまま結びつくことによって忘れられない記憶になるという経験を何度もしているからだ。実際にライブ後にはたくさんの人が物販列に並んでいたのは鮪のこのMCがその人たちに響いていたからだろう。もちろんそれはこのツアーのデザインの秀逸さあってこそである。
このアンコールで出てきた時は鮪はメガネをかけていたのだが、その鮪は高校生の時に小泉と後輩のベーシストとのスリーピース(つまり古賀抜き)でストレイテナーのコピバンをやっていたという過去を語り(当時のテナーはまだOJ加入前のスリーピースバンドだった)、
「先輩!カバーさせていただきます!」
と言っておよそ15年ぶりとなる(古賀と遠藤は初カバー)ストレイテナー「TRAIN」のカバーを披露するのであるが、もうイントロからして「うわ!テナーだ!」と思ってしまうくらいの完コピっぷり。それはKANA-BOONのテナーへの愛情の強さとともに演奏力の高さを改めて示すものでもあるのだが、やはり鮪の少年性を強く感じさせる歌声で歌うことによって、それくらいテナーそのものである演奏もKANA-BOONの曲になる。鮪の歌の上手さはこうしてライブを観に来ている人にはもう周知の事実であるが、上手さだけではなくてどんな曲でも自分のものに染め上げることができるボーカリストであることがよくわかる。実はKANA-BOONの音楽を最もKANA-BOONのものたらしめているのは4つ打ちのリズムよりギターサウンドより鮪の歌声であるということがよくわかるテナーカバーであった。
そんなこの日でないと見られないものすらも見せてくれた1日の最後に演奏されたのは、今やすっかりKANA-BOONのライブの締めを担う曲になった、フジファブリックの金澤ダイスケがプロデュースした「スターマーカー」。
金澤ダイスケだからこそのカラフルな鍵盤の同期の音に合わせて観客が腕を左右に振る光景もまたこの曲ならではのものであるが、古賀が間奏でステージ前に出てきて高速手拍子を煽るのも本当に楽しい。つまりそれは辛いこともたくさん経験してきたからこそ、こうして最高に楽しい時間をKANA-BOONが作ろうとしているということだ。というかそれはただ能天気に楽しいことだけをやるわけじゃない、乗り越えてきた人だからこそ、こうして人生にはキツいことを乗り越えた先に楽しいことがきっと待っているということを示してくれているかのようだった。
演奏が終わると鮪は
「来年KANA-BOONは10周年を迎えます!10周年を祝ってもらうために来年もたくさんライブをやります!」
と、10周年イヤーのキックオフとして4月に大阪、5月に東京の野音でワンマンを行うことを告げる。喜びの感情を爆発させる観客の姿や、
「KANA-BOONにとって初めての野音ワンマンです!」
と言う鮪の言葉を聴いて、今年のホールワンマンもそうだが、かつて1stアルバムリリース時点でもうライブハウスとしては最大規模の会場を回り、2ndアルバムでは武道館まで到達するくらいのスピード感だったからこそ、この規模でワンマンをやることがなかった。そう考えると今は状況的にはだいぶ落ち着いたと言えるけれど、こうしていろんな場所でKANA-BOONのライブを見ることができるのが本当に嬉しい。きっとこの日の観客たちもそう思っているから野音が発表された時にあんなにも嬉しそうにしていたんじゃないだろうか。メンバーがステージ前に出てきて揃って観客に頭を下げる姿を見て、そんなことを思っていた。
前述の通りにKANA-BOONのライブは今や他に類を見ないくらいの人間の生命力を感じさせてくれる。その生命力溢れるライブは見ている我々をこの上ないくらいに幸せな感情に導いてくれる。きっと10周年イヤーとなる来年にはもっとたくさん我々をそう思わせてくれるんだろうけれど、そうして我々を幸せにしてくれるKANA-BOONのメンバーも幸せだと感じられるような10周年イヤーになりますように。覚えてないこともたくさんある人生だけど、このバンドのライブの記憶は離さずに守り続けられるように。
1.シルエット
2.フルドライブ
3.Torch of Liberty
4.Dance to beat
5.talking
6.バトンロード
7.まっさら
8.きらりらり
9.ないものねだり
10.ネリネ
encore
11.TRAIN
12.スターマーカー
本来はファイナルがこの日だったが、名古屋が翌週に延期になったことによってこの日はセミファイナルに。すでに開催された大阪でのキュウソネコカミとの対バンが行った人のツイートを見るたびに行けば良かった…と悔いているだけにこの日がより楽しみである。
オールスタンディングの立ち位置指定もなしというライブハウス本来の姿に戻りつつある客席には開演前にKANA-BOONの小泉貴裕(ドラム)による影アナの前説が流れる。かつて小泉は学生時代にナカヤマシンペイに憧れてストレイテナーのカバーをやっていたらしいが、明らかにそのアナウンスが慣れていないというか、漢字がちゃんと読めないのがバレてしまうような感じすらあり、この影アナのやり取りはかつて映像作品で試みた「とにかくカッコいい小泉」の空回りっぷりを思い出させる。客席からもどこか失笑的な笑い声が漏れていた感じがする。
・ストレイテナー
そんなKANA-BOONに招かれた、大先輩のストレイテナー。4人がステージに登場すると、ドラムセットの椅子の上に立ち上がるナカヤマシンペイ(ドラム)がウインドチャイムを鳴らして始まるのはいきなりの「Melodic Storm」で、客席ではたくさんの腕が上がるというのはこのバンドを見るためにこの日こうして足を運んだ人もたくさんいるということがわかるのだが、その腕の振り上げ方がシンペイのリズムに対して裏で拍を取っている人はガチの普段からテナーのライブに行っている人だなということもわかる。かつては観客が合唱していたコーラスパートまでも全て自身で歌うホリエアツシ(ボーカル&ギター)の歌唱もさすがの安定感であるが、今年からマイクがヘッドセットではなくて通常のマイクに戻ったシンペイのコーラスがホリエのボーカルに重なることによって、我々が一緒に歌えなくても寂しいと感じることはない。
さらにはホリエがタイトルを口にした「From Noo Till Dawn」ではホリエは歌詞を変えることなく原曲のままで歌うのであるが、ひなっちこと日向秀和(ベース)の演奏している時の表情が実に楽しそうなのが、メンバー全員がこの日のライブを心から楽しみにしていたということが伝わってくる。
もうすっかり肌寒くもなってきつつある時期であるが、ライブハウスの中は季節が関係ないと言わんばかりにタンクトップ姿のシンペイがリズムを刻むのは実に久しぶりに聴く感じがする「KILLER TUNE」。そのサウンドは例えば「DISCOGRAPHY」が年月を経るごとにアレンジされて形を変えていくように、軽快なリズムの中にもどっしりとした安定感と重さを感じさせるようになっている。OJこと大山純(ギター)も間奏ではステージ前まで出てきてギターを弾きまくっているが、テナーの代表曲が今のバンドの状態によって今のバンドとしてのリアルな形にアレンジされてきていることがよくわかる。
「俺たちストレイテナーって言います!初めて見る人たちもたくさんいるだろうけど、今日来ているお客さんにわかりやすく言うと、アジカンの同期のバンドです!」
という、KANA-BOONファンにも実にわかりやすい自己紹介をすると、最新ミニアルバム収録の「宇宙の夜 二人の朝」で、過去の代表曲たちと変わることのないギターロックバンドとしてシーンの最前線に立ち続けているテナーの姿を示すと、「叫ぶ星」ではイントロからまさに星が泣き叫ぶようなギターを弾いていたOJが両腕を振って踊るような仕草を見せる。広いZepp Hanedaのステージを大きく動き回りながらギターを弾く仕草も含めて、OJも気合いが漲っていることが伝わってくる音とパフォーマンスである。
するとホリエがギターを下ろしてキーボードを弾きながら歌うのは「Braver」なのだが、ここまでのギターロック曲以上に力強くシンペイが腕を振り下ろすようにしてドラムを叩いていることによって、決して速くも激しくもないこの曲がそのタイトルにふさわしい力を獲得しているし、近年のシンペイのドラマーとしてのさらなる覚醒っぷりが最も顕著に感じられる曲がこの曲だと思える。テナーのリズムと言えばとかく超人ベーシストであり、リズムだけでなくメロディまでも兼ねているかのようなひなっちのベースが牽引してきたイメージが強いが、それも少しずつというかドラスティックに変わってきつつある。それはコロナ禍になってドラムの腕だけではなくてフィジカルそのものを見つめ直してきたシンペイの努力によるものと言っていいだろう。
かと思えばそのままホリエがキーボードを弾きながら歌う「さよならだけがおしえてくれた」では今のテナーのメロディが持つ包容力と優しさを感じさせてくれる。それは今やKANA-BOONをはじめとしていろんなバンドたちが背中を追うようなベテランバンドになったからこそ獲得できたものとも言えるのだが、ステージ背面に照明が当たることによって光の粒のように飛び散る演出が感じさせてくれることでもある。
そんなテナーの最新形と言える、「宇宙の夜 二人の朝」とともに昨年リリースのミニアルバム「Crank Up」に収録された「群像劇」ではやはりステージ上を軽やかに舞うように動き回りながらギターを弾くOJが曲終わりにもギターをジャラーンと鳴らすのであるが、ホリエはリハで鳴らしていたという終わり方が好きらしいのだがOJがそれを全くやってくれないということを語りながら、
「まだフェスモードみたいな感じが抜けきってないから、こうして2マンライブで持ち時間が長いと「もう10分短くてもいいのに」って思う(笑)」
と、むしろ持ち時間が長いとたくさん曲聴けるから嬉しいんですけど、とファンに思わせながら、
「今日、楽屋で鮪君が急に距離を縮めようとしてきて(笑)ソファで俺の隣に座ってたんだけど、他の3人が立ちっぱなしで「これでいいのかな?」って思いながら(笑)、鮪君が下ネタとかまで言ってくるんで、僕は下ネタNGなんでって伝えて(笑)」
と、初めてライブを見る人が多いからか、何故か清純なキャラを作りながら、季節関係なく夏フェスとかでも演奏されることもある「冬の太陽」がやはりこの時期に聴くことによって、冬晴れの日のカラッとした太陽の輝きを感じるような時期になってきたなと思わせながら、緩急で言うならば緩の部分を終えて急の部分に転じてきていることを感じさせる。それがハッキリとわかるくらいの流れを作ることができる持ち時間の長さを与えてくれたのはKANA-BOONのテナーへのリスペクトあってこそだろう。
そんなアッパーな流れはホリエがギターをかき鳴らしながら歌い始めた「シーグラス」で極まり、シンペイはその歌い出しで再びドラムセットの上に立ち上がって観客を煽るような仕草をする。その直後に座ってドラムを叩き始めると、ひなっちと顔を見合わせながら笑顔で演奏している姿が今のテナーがさらに最高な状況にいることを実感させてくれる。また来年の夏に全国各地のフェスでこの曲を聴いて、
「今年最後の海へ向かう」
というサビのフレーズを噛み締めたいなと思う。
そんなテナーはこの後には謎のBBQ好き新人バンドの633と一緒にツアーを回ることを告知する。ここでは敢えて突っ込むことはしないけれど、果たしてそのライブではどんな設定になってそれをこの演技とか全然出来なそうな4人が演じるのかというのも楽しみなところである。
そうした場所での再会を約束してからホリエがアコギに持ち替えて演奏された「彩雲」の穏やかなサウンドがこうしてテナーのライブを見ることができているということの幸せを噛み締めさせてくれると、最後に演奏されたのはKANA-BOONという自分たちに憧れてくれた後輩とそのファンたちに、ギターロックバンドとしてカッコいい背中を見せるかのような「REMINDER」。「記憶」をテーマにしたその曲がこうして最後に演奏されたからこそ、こうしてこのツアーの東京にテナーが出演して、これ以上ないくらいの横綱相撲的なライブを見せてくれたことを忘れることはないだろうなと思った。時には「丸くなった」「昔みたいな曲をやってほしい」とか言われることもあるだろうけれど、テナーは今でもずっとカッコいいギターロックバンドのままだ。それは演奏が終わった後にシンペイがドラムセットを乗り越えるようにしてステージ前まで出てきて4人で並んで肩を組むシルエットの美しさの変わらなさからも確かに感じることができる。
ホリエが口に出したアジカンのように、ずっとメンバーが変わることなく活動し続けるというのはKANA-BOONにとっても、他の後輩バンドからしても大きなランドマーク的な存在に映ると思う。でもテナーはメンバー脱退とかとは全く逆に、2人で始まったバンドが1人ずつメンバーが増えてこの4人になったという独特すぎる経緯で活動を続けてきたバンドである。つまりは変わってきたけれど、悲しい別れなどは全く経験してこなかったという特異なバンドである。
そんなバンドだからこそ、変わることは悪いことではない。むしろ変わることは進化であるということを、自分たちが活動を続けることによってその背中で示すことができる稀有なバンドである。アジカンやELLEGARDENほど時代を作ったという存在ではないけれど、その在り方はその同志たちに負けないくらいにたくさんのバンドに勇気を与えてきたはずだと、こうして憧れてきた後輩に呼ばれた立ち位置でのライブを見て思う。
・KANA-BOON
1.Melodic Storm
2.From Noon Till Dawn
3.KILLER TUNE
4.宇宙の夜 二人の朝
5.叫ぶ星
6.Braver
7.さよならだけがおしえてくれた
8.群像劇
9.冬の太陽
10.シーグラス
11.彩雲
12.REMINDER
・KANA-BOON
そんな先輩のストレイテナーがさすがと言えるライブを見せてくれた後のKANA-BOON。SEがやたら賑やかなパーティーチューンと言えるような曲になっている中でメンバー4人がステージに登場すると谷口鮪(ボーカル&ギター)が、
「今日はテナブーンです。よろしくお願いします!」
と挨拶すると、もうこのイントロを聴くだけで胸が熱くなるギターを、デビュー時から全く変わらない黒ずくめの衣装を身に纏って弾く古賀隼斗(ギター)が早くもステージ前に出てきて少しでも観客の近くに来る「シルエット」からスタートするという展開。パーマの当たり具合が強くなった鮪のハイトーンなボーカルも実に伸びやかに響くのであるが、マーシーこと遠藤昌巳(ベース)のコーラスが曲を彩るという意味では実に重要な役割を担っている。それによってこの大名曲がそのポテンシャルをフルに発揮することができているというか。うねるようなベースプレイも含めて、まだ加入したばかりであるがすでにKANA-BOONの音楽とライブを支える存在になっている。
さらに「フルドライブ」でも古賀と遠藤が前に出てきて観客を煽るように演奏し、その姿に反応した観客も踊りまくる。この飛ばしっぷりは完全にタイトル通りのフルドライブっぷりであるが、当時は4つ打ちロックとディスられることもあったりしたけれど、それでもこうして今聴いているとそんなことを飛び越えるくらいに圧倒的にKANA-BOONは曲が良い。それが今でもこうして広いステージに立てている理由だろう。
さらには「Torch of Liberty」と立ち上がりからバンドは完全にフルスロットル、観客をもそうさせるような、この日を最高なものにしてバンドもここにいる全員も楽しいと思わせるという意識が伝わってくる。観客が声を出せないからこそ、この曲での遠藤の勇壮なコーラスは本当に大事な役割を担っているし、古賀が前に出てきてギターを鳴らすと鮪が古賀の立ち位置にまで行ってギターを弾きまくる。憧れの先輩が自分たちのツアーに出てくれた後という気合いが入りまくっているのもよくわかるが、とにかくメンバーがこうして音を鳴らしているのが楽しそうで仕方がないし、その姿や表情が我々をさらに楽しくさせてくれる。
そのバンドのテンションの高さはライブ前からだったようで、テナーのリハーサルをずっと見ていてその機材の多さに驚きつつ、ホリエが楽屋に向かうドアを開けようとした時に全然開かなかった姿を見て、
「ホリエさん、それ押すんじゃなくて引くんです」
とツッコんだというホリエの天然エピソードを開陳すると、
鮪「もう俺は今日はホリエさんにべったりで。楽屋でもずっと隣にいた。LINEも聞いたし」
古賀「お前楽屋に入ってすぐに聞いてたよな(笑)初手でいくかそれっていう(笑)」
鮪「マーシーはいつも対バンの時には自分で挽いたコーヒーを差し入れて距離を詰めようとするんやけど、シンペイさんがコーヒーアレルギーやったり、OJさんに「今はいい」って言われたりして不発やったな(笑)
ひなっちさんには一緒に登山に誘われてたけど行くの?」
遠藤「…行きます!」
鮪「じゃあみんなで行く?足腰鍛えないと!」
というテナーを好きで仕方がない気持ちが溢れ出るMCが愉快なものになるのもKANA-BOONのメンバーの人間性によるものであるが、登山に向けて足腰を鍛えるべくリズムを足で取る「Dance to beat」はその通りに鮪も古賀も遠藤も足を踏み鳴らすようにして演奏するのであるが、「Honey & Darling」のアルバム曲がこうしてアンセム連打の流れの次に演奏されるというのがメンバーのアルバムへの自信を伺わせる。それはフェスなどでもセトリにアルバム曲を多数入れていたことからもわかることである。
そんな中で遠藤のうねるようなベースラインが紫を基調とした照明とともに妖しい空気を作り出すのは「talking」。かつてシナリオアートとのスプリット盤収録曲としてリリースされ、バンドの演奏力の向上に繋がったそれまでのKANA-BOONにはなかった曲であるが、こうして今のバンドの技術で演奏されることによってKANA-BOONの今の演奏技術の高さとこうした疾走感あるギターロックとは違うタイプのサウンドの曲における表現力を感じさせてくれる。
そんなKANA-BOONはやはり2000年代中期頃のアジカンやテナーが作ったギターロックシーンに強い影響を受けたバンドであり、自分たちが中堅と言っていい立ち位置になってきたことによって、そうした先輩たちから受け取ってきたバトンの欠片を次の世代にも渡していきたいということを話す。ルーツがハッキリと見えるKANA-BOONだからこそ、そうして音楽の継承に自覚的なのだろうし、そうやってバンドが、音楽が絶えず続いていくということをわかっているのだ。
そんなMCをしたからこそ、観客は一つの曲が頭に思い浮かんでいたと思うけれど、その想像通りにいかないことも多々あるバンドなのだが、この日はそのMCの流れ通りに久しぶりに「バトンロード」を演奏する。やはり古賀がステージ前に出てきてフック満載のギターを弾きまくるのだが、親から子へ物語が継承されていく「NARUTO」〜「BORUTO」というKANA-BOONの存在を広く知らしめたアニメの主人公と今のKANA-BOONは同じ位置にいると言える。NARUTOが成長して息子にバトンを渡したように、KANA-BOONもまた次の世代へとバトンを渡す存在になったからこそ、今こうしてこの曲を聴くのがより一層響くものがある。
それを本人たちもわかっているからこそ、
「俺たちってもう若手バンドじゃないの?って思ったりもするけど(笑)、ストレイテナーが俺たちに背中を見せてくれているように、俺たちも後輩バンドにカッコいい背中を見せられるように。俺たちの中で1番カッコいい曲をやります」
と言って演奏されたのは、ジャーンと鳴らされるイントロで逆光的な照明に照らされる姿だけでもカッコ良さを感じさせる「まっさら」なのであるが、後に本人も言っていたようにシンペイに影響されて小泉が思いっきり腕を振り下ろす力強いドラムを叩く。それはまさにこれまでのKANA-BOONを更新するようなカッコいいロックバンドの姿であるのだが、鮪の最後のコーラスフレーズでの圧巻の声量と伸びやかさも含めて、日々いろんなバンドのライブを見ている身としても、今のKANA-BOONほどロックバンドの、人間としての生命力を感じさせてくれるバンドはいないと思う。それくらいに人間の生きている力がその音から感じられる。それは今でもまだ無邪気な、幼く見えることばかりのKANA-BOONも今に至るまでに本当に様々なことを経験してきて、そうした人生が鳴らしている音に滲み出ているからだ。見ている側からしてもキツいこと、辛いこともたくさんあったバンドだけれど、その経験が間違いなく今のバンドの強さへと昇華されている。この「まっさら」には特にその強さが宿っている。真っ白な照明の光がそのまま人間の生命の光として感じられるかのように。
そんなKANA-BOONの新曲としてすでに「BORUTO」の新テーマソングとしてオンエアされているのが「きらりらり」であるのだが、そのアニメや原作を見ている、しっかりストーリーやキャラクターまで理解・把握しているからこそ描ける、使える歌詞やフレーズの数々はもちろん、今のKANA-BOONにとっての「シルエット」と言えるような、
「大事にしてたものを持って大人になった」
という歌詞は、BORUTOが成長するとともにKANA-BOON自身が成長した、大人になったことをタイトル通りにとびっきりの煌めくメロディで歌うのであるが、さらに
「目の前にあった」
というフレーズを歌う際に鮪はステージ袖を指差した。それはストレイテナーが自分たちの目の前で追うべき背中を見せてくれたからだ。「BORUTO」のテーマソングでもありながら、今のKANA-BOONにとってのテーマソングでもある。この曲は我々ファンが長く愛していける曲になっていくだろうと思うとともに、バンドにとっても大切な曲になっていくはずだ。それは「シルエット」がそうであるように。
そんな新曲を披露した後には鮪が次の曲に繋がるようなギターを鳴らすのであるが、そこに古賀もギターを被せてきたことによって鮪が
「俺のターンやんけ!被せてくるなよ!」
と言ってやり直すのだが、次は遠藤がベースを被せてまたやり直し、最後にも小泉がドラムを被せるがそれはもうそのまま曲のイントロへ…という形で始まったのは「ないものねだり」であり、客席からは完璧なリズムの大きな手拍子が起こり、それは観客が声を出すことができない近年は間奏部分でもコール&レスポンスではなくて観客の手拍子だけでリズムを支えるという展開も鮪が説明するまでもなく完璧に出来ているというあたりはやはりこの曲はもう完全にロックシーンのアンセムと言っていい曲になっているんだなと思える。
鮪と古賀が至近距離で向かい合ってギターを弾き合う姿もこの2人の絆を感じさせる。鮪が活動出来なかった時期にきっと1番バンドを背負ってメディアに出演したりしていたのはこの古賀だろうから。その古賀の思いを鮪もきっと理解しているはずだ。
そんなアンセム連発のライブの最後に演奏されたのは「ネリネ」という意外な選曲なのだが、それはかつてこの曲を収録したミニアルバムが「冬盤」としてリリースされたこと、ネリネ(彼岸花のこと)の咲く時期が秋から冬であることを踏まえての選曲だと思われるのだが、バンドの演奏も軽やかさを感じさせるものであるだけに観客も体を揺らしながら、
「歌いながら 踊りながら
進め 旅はまだまだこれから
単純な心のままに
鳴らし続けるよ 歩き続けるよ」
という最後のサビのフレーズはこれからもKANA-BOONが音を鳴らし、歩き続けていく意思を示すものでもあった。リリース時から名曲としてファンに親しまれてきた曲であるが、それが本当に大きな意味を持つような曲になったんだなと今にして思えるようなものになったのだ。
アンコールではメンバー全員がツアーTシャツに着替えて登場するのだが、古賀がツアータオルを忘れてしまったことによって遠藤のタオルを借りて物販紹介をする。その間にスタッフがさりげなく古賀のアンプの上にタオルを置いていたのをメンバーは気付いていなかったが観客は見ていたので古賀が
「え!?タオルあるやん!」
とビックリしていたのが実に古賀らしくて面白かった。
そうして物販を紹介するのも鮪は
「記憶は薄れていってしまうから、物として持っておくことで手にした時にこの日のことを思い出すことができる。それは俺も配信で音楽を聴くけど、CDも同じ」
と、来月リリースされる「きらりらり」をこのご時世でも今まで通りにCDとしてリリースすることを語るのだが、
「君たちが10年くらい経って結婚したとしよう。その時に棚にしまってある、ひび割れたり歌詞カードがぼろぼろになったCDを手に取ることによって…」
とやたら詳細な設定で話し始め、古賀に
「入り込みすぎやない?(笑)」
と突っ込まれるのだが、それは
「手に取れるものだからこそ愛することができる」
という鮪の一貫した姿勢によるものだ。それは自分自身もCDを今でも購入し続けているリスナーであるだけに本当によくわかる。そのCDを買った時の状況とその曲を聴いた時の記憶がそのまま結びつくことによって忘れられない記憶になるという経験を何度もしているからだ。実際にライブ後にはたくさんの人が物販列に並んでいたのは鮪のこのMCがその人たちに響いていたからだろう。もちろんそれはこのツアーのデザインの秀逸さあってこそである。
このアンコールで出てきた時は鮪はメガネをかけていたのだが、その鮪は高校生の時に小泉と後輩のベーシストとのスリーピース(つまり古賀抜き)でストレイテナーのコピバンをやっていたという過去を語り(当時のテナーはまだOJ加入前のスリーピースバンドだった)、
「先輩!カバーさせていただきます!」
と言っておよそ15年ぶりとなる(古賀と遠藤は初カバー)ストレイテナー「TRAIN」のカバーを披露するのであるが、もうイントロからして「うわ!テナーだ!」と思ってしまうくらいの完コピっぷり。それはKANA-BOONのテナーへの愛情の強さとともに演奏力の高さを改めて示すものでもあるのだが、やはり鮪の少年性を強く感じさせる歌声で歌うことによって、それくらいテナーそのものである演奏もKANA-BOONの曲になる。鮪の歌の上手さはこうしてライブを観に来ている人にはもう周知の事実であるが、上手さだけではなくてどんな曲でも自分のものに染め上げることができるボーカリストであることがよくわかる。実はKANA-BOONの音楽を最もKANA-BOONのものたらしめているのは4つ打ちのリズムよりギターサウンドより鮪の歌声であるということがよくわかるテナーカバーであった。
そんなこの日でないと見られないものすらも見せてくれた1日の最後に演奏されたのは、今やすっかりKANA-BOONのライブの締めを担う曲になった、フジファブリックの金澤ダイスケがプロデュースした「スターマーカー」。
金澤ダイスケだからこそのカラフルな鍵盤の同期の音に合わせて観客が腕を左右に振る光景もまたこの曲ならではのものであるが、古賀が間奏でステージ前に出てきて高速手拍子を煽るのも本当に楽しい。つまりそれは辛いこともたくさん経験してきたからこそ、こうして最高に楽しい時間をKANA-BOONが作ろうとしているということだ。というかそれはただ能天気に楽しいことだけをやるわけじゃない、乗り越えてきた人だからこそ、こうして人生にはキツいことを乗り越えた先に楽しいことがきっと待っているということを示してくれているかのようだった。
演奏が終わると鮪は
「来年KANA-BOONは10周年を迎えます!10周年を祝ってもらうために来年もたくさんライブをやります!」
と、10周年イヤーのキックオフとして4月に大阪、5月に東京の野音でワンマンを行うことを告げる。喜びの感情を爆発させる観客の姿や、
「KANA-BOONにとって初めての野音ワンマンです!」
と言う鮪の言葉を聴いて、今年のホールワンマンもそうだが、かつて1stアルバムリリース時点でもうライブハウスとしては最大規模の会場を回り、2ndアルバムでは武道館まで到達するくらいのスピード感だったからこそ、この規模でワンマンをやることがなかった。そう考えると今は状況的にはだいぶ落ち着いたと言えるけれど、こうしていろんな場所でKANA-BOONのライブを見ることができるのが本当に嬉しい。きっとこの日の観客たちもそう思っているから野音が発表された時にあんなにも嬉しそうにしていたんじゃないだろうか。メンバーがステージ前に出てきて揃って観客に頭を下げる姿を見て、そんなことを思っていた。
前述の通りにKANA-BOONのライブは今や他に類を見ないくらいの人間の生命力を感じさせてくれる。その生命力溢れるライブは見ている我々をこの上ないくらいに幸せな感情に導いてくれる。きっと10周年イヤーとなる来年にはもっとたくさん我々をそう思わせてくれるんだろうけれど、そうして我々を幸せにしてくれるKANA-BOONのメンバーも幸せだと感じられるような10周年イヤーになりますように。覚えてないこともたくさんある人生だけど、このバンドのライブの記憶は離さずに守り続けられるように。
1.シルエット
2.フルドライブ
3.Torch of Liberty
4.Dance to beat
5.talking
6.バトンロード
7.まっさら
8.きらりらり
9.ないものねだり
10.ネリネ
encore
11.TRAIN
12.スターマーカー
THE SUN ALSO RISES vol.162 - a flood of circle / cinema staff- @横浜F.A.D 10/26 ホーム
KOTORI 「DREAM MATCH 2022」 対バン:くるり @Zepp DiverCity 10/21