
コウディ・モウザ「他の動物種たちへの共感の起源について」(2023年2月27日)
わたしたちは,自分のエモノたちの目をとおして世界を見るすべを身につけている――ひとえに彼らを食すために
「感じるかい?」 「なにを?」 「いかに強欲な捕食者に我が身が変わっているのかをさ.まるでオオカミのようにね.もっと多く,さらにもっと仕留めてやろうっていう,この欲求があるんだ.家畜小屋が200棟あっても満足しない,だろ? まるで悪魔だ」――そう言って,彼は無言になった.少し経ってから,彼は言葉を継いだ.「どうだろう,ちょっと落ち着いて,1週間かそこらでも狩りをやめないか.」
食料が底をついたら,あなたは自分の飼い犬を食べるのをためらうだろうか? どこかの無人島に流れ着いたとして,家族の愛猫を切り分けて飢えを満たす方法を考えはしないだろうか?
飼い犬や飼い猫のような動物たちと,牧場にいる動物たちとを隔つものは,なんだろう? きっと,この問いかけになかなか答えられない人は,動物を殺したり食べたりすること全般に,落ち着かないものを感じているはずだ.では,どうして,あなたは肉を食べることを選んできたのだろう?
共感する心の仕組みについて,いま模索が進んでいる問いがある.「動物たちに愛情を抱いているというなら,いったいどうして,それにもかかわらず動物たちを殺して食べることを私たち人間は選ぶのだろう?」 この問いは「肉食パラドクス」といって,菜食主義者たちにも肉をふつうに食べている人たちにもひとしく見られる現代のさまざまな矛盾の多くは,肉食パラドクスへの答えが解決の助けになる.たとえば,肉食習慣の持ち主たちは,別の場面では人間以外の動物たちにも共感の輪を広げているように見えるのに,食事では動物の命を奪う意識的な意思決定ができる.このことは,倫理を理由に菜食主義をとっている人たちの多くにとってどうにも理解しがたい.
肉食習慣の持ち主たちから見ると,菜食主義者の立場はいかにも不自然な性質で理解しがたい――「進化によって私たちは肉を食べるようにできている.それでいて,近年になって社会で肉食が問題視されるようになった.かつての自然状態では狩りで生き物を仕留めて食料にするしかなかったのが,〔人類史の尺度で見て〕ごく最近になって現代のように自然状態から隔絶した生活を送るようになって,そのなかで動物への共感がつくりだされたのだ.かつては,そんな共感などなかったのに.」
だが,この肉食パラドクスは本当にパラドクスなのだろうか? 自分たちが食べるエモノに共感をもつのはどうしてだろう?
一案として,こんな説明が考えられる――「エモノとなる動物への共感は進化におけるスパンドレル,進化の副産物であって,これをもたらしたのは人間どうしで相手に共感する高度な能力だ.エモノの血肉で歯とツメを赤く染めたライオンやチンパンジーなどの捕食者たちと同じように,私たち人間も,どんなときでも冷血な捕食者としてエモノを食料としか思わない存在であって当然だった.だが,おそらくは家族や部族のきずなが進化で生じ,もちろん犬などの有用なペットたちとのきずなは言うにおよばず,やがては一国全体や国どうしの紐帯も生じるようになったとき,認知機構は完璧にそうした対象に限定的ではなく,より広く人間以外の能動的な生き物にも当てはめられてきたのだろう.」
私は,これに代わる主張を展開したい.もしも,エモノに共感を抱くことによって,エモノと同じように考え,エモノと同じように行動し,ひいてはエモノを殺せるようになるのだとしたら,どうだろう? タイムマシーンがあるわけでもないから,この問いに完全な決定打の答えを出すのは不可能だ.さいわい,民族誌やさまざまな文化をまたいだ記録があるおかげで,こんな問いが建てられる:私たち人間が進化したのと似た環境や生態学的な状況において,人間はどのようにしてエモノについて考えるのだろう? エモノと同じように考えるのだろうか,そして,自分が殺す動物たちを気の毒に思うのだろうか?
西洋の狩猟の手口に詳しい人たちなら,動物たちを欺くにはどうすればいいか,よく承知していることだろう.私の父は子供のころに曾祖父からウサギ狩りのやり方を教わった.ウサギが逃げようとしたら,ただ口笛を吹けばいい――ウサギは,鷹がいると思ってパタッと止まって動かなくなる.今日でも,ルアーやおとりが狩猟に使われているし,エモノをおびき寄せるのに動物の鳴き声をまねる手口も使われている.2010年代屈指の大ヒットTV番組『ダック・ダイナスティ』を見たことがあるなら,「あれか」とわかるだろう.ルイジアナの廃船小屋からカモ狩猟用品の製造で4億ドルの財をなした一家の実生活を追った番組だ.
こうした鳴き真似の手口が世界中で使われているという証拠がある.同僚のマイケル・オルヴァードが修士時代に,南米ペルーに暮らす狩猟採集民ピロ族とすごしたときの物語を語ってくれたことがある.
部族民の一人が,オルヴァードに訊ねた.「弓ひとつで鳥の群れをみんな射落とせるんだ,どうやればいいか知りたいか?」 まさかそんなことはできまいと思いつつも,オルヴァードはその狩人についていって,一部始終を観察した.狩人は鳥の群れにじりじりと寄っていって,狩猟用の短い矢をいちどだけ放ち,1羽を手負いにして射落とした.これに驚いた他の鳥たちは,いっせいに飛び去る.だが,森の地面に落ちた鳥は,仲間の群れに苦境を伝える鳴き声をあげはじめた.すると,傷ついた仲間を気にして鳥たちが戻ってきた.狩人がまた一羽仕留め,また鳥たちが逃げ去る.だが,またしても,仲間の泣き声に鳥たちは舞い戻ってくるのだ.狩人はえんえんとこれを繰り返して,群れをぜんぶ仕留めてしまった.
民族誌の記録をじっくり調べてみると,こういう物語は珍しくもない.同僚のウィル・バックナー,メリナ・セイリアン,ジェフ・ウィンキングと私がみずからの研究で見出しているように,世界各地で人間がエモノをあざむくのに用いている手法は多岐にわたり,およそ人間の想像力のおよぶかぎりの突飛な方法がとられている.
さまざまな文化のなかには,人間が動物そっくりのいでたちをする文化もある.隠蔽擬態(カモフラージュ)の一種としてそうする場合もあれば,動物の興味を引くためにそうする場合もある.シベリア東部の先住民チュクチを調べた民族誌の記録から一例を引こう.それによると,冬期に狩人たちはアザラシの頭を模した形状のシールスキンを隠蔽擬態に用いる.アザラシの動きをまねつつ彼はゆっくりと這いずって進んだ.その間ずっと,アザラシの爪を縛り付けた特製のスクレーパーで氷をこする.」 さらに,南アフリカのサン族の人々の事例も挙げておこう.2人の狩人がダチョウの出で立ちをしてシマウマの群れを追跡した方法が記録に残っている.2人一組で,片方はダチョウの胴体を担当し,もう片方は弓矢を携えて羽毛の中に潜むのだ.
記録に残っているものでいっそう目を見張るのが,音を使ったオトリだ.これには実にさまざまな種類がある.メラネシアでは,ココナッツや貝殻などの大きな音を立てるモノを紐で結わえ,これを海上で振ってカタカタという音を出す.この音は,肉食の鮫をおびきよせるオトリだ.海中の鮫は,なにかの生き物がもがいている音だと思って近寄ってくるのだ.世界各地に暮らす狩猟者集団のほぼすべてにおいて,エモノの声真似こそがエモノをおびき寄せる基本的な方法となっていることが記録にとどめられている.多くの鳴き声は,人がしゃべったり歌ったりするのと同じ方法で発声される.他方で,現存する人間言語の大半で用いられていない音響現象が,世界中の狩猟では用いられている.その音響とは,口笛だ.世界各地で,狩猟者たちは自分の口やリード楽器を使って高いピッチの笛音を鳴らし,鳥や霊長類の鳴き声をまねてエモノを欺いている.
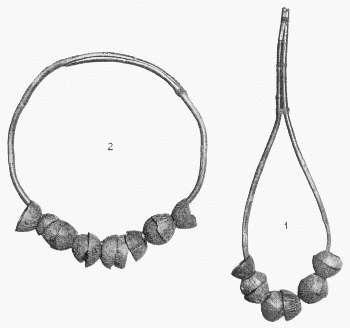
エモノを欺す方法は,視覚的・聴覚的な方法にとどまらない.他にも,さまざまなかたちで人間はエモノを欺いている.
捕まえた動物でその仲間をおびき寄せる狩猟の方法もある.トナカイの放牧者にはメスのトナカイを捕まえてオトリにする方法が見られるし,アマゾン流域の人々のあいだでは,求愛行動をとる動物の「配偶者」候補や「ライバル」をオトリにする方法が見られる.そうしたオトリにおびき寄せられるのは,なにも知らない単身のオスだ.パプアニューギニアのカイマン族では,狩猟者たちが「カンガルーの天性の好奇心につけいる」手口を用いている.「飛び跳ねるカンガルーの真似をしてたえず地面を飛び回りながらエモノに近寄っていく」のだ.セントローレンスの先住民ユピク族でも,同様の話がある.ユピク族の狩猟者たちは,捕鯨船の船底に〔ホッキョククジラに似せた〕彫刻を取りつける.すると,これに興味を引かれて,どうやら自らの意思で,クジラたちが船からモリでつきやすい位置に寄ってくる.
民族誌には実にさまざまな欺瞞の方法が記録されており,いま紹介したのはほんの一端にすぎない.人類学者たちが文化をまたいだ比較をするのに利用している標準化された膨大な民族誌データベースの Human Relations Area Files (HRAF) というものがある.私と共同研究者たちは,このデータベースを利用して,7つの大陸グループ(オセアニアを含む)と民族誌の記録から147の文化を検討し(HRAF の狩猟採集民の大半を代表するものが含まれる),数百の事例を集めてカタログにまとめた.
たしかに狩猟で物真似や欺瞞が用いられるのは直観的にわかりやすいものの,そうした方法が世界中に広く存在していることから考えると,物真似や欺瞞は人間の進化の歴史でいかほどか重要なものであった見込みが大きい.進化心理学や文化進化の研究分野では,認知機構が進化で構築されていまこうして人間の心に備わり,行為者どうし〔人間どうし〕のやりとりがなされているということについて大いに語られている.だが,他にも重要な要素があることが見過ごされている:私たちが相手をしなくてはならないのは,他の人間だけではないのだ.人間の進化史という舞台では,心をもつものどうしのやりとりが続いてきた.そこには,人間以外にも鳥やシカや魚や鯨など多種多様な動物の心も含まれる.
他の動物たちとのやりとりから,私たち人間の進化史について,どんなことがわかるだろう?
クリス・ナイトとジェローム・ルイスの論文「野生の声」('Wild Voices') では,人間言語の起源は,人間がエモノをまねる能力にあるのかもしれないという仮説を提示している.人間は,幼い頃から音の模倣に長けている.近縁種の大半から人間をわかつものは,さまざまな概念を理解する語彙的な能力ではなく,発声の可塑性であるように思える――つまり,精密かつ多種多様な音声を広く発せられる能力が,我らが親戚の種たちとちがうように思える.
言語と人間認知の起源を研究した霊長類学者たちが記しているように,「動物が発せられる鳴き声の種類は,数が非常に限られている.他方で,オウムやイルカやアシカやチンパンジーが特定の刺激や結果と結びつけるのを学習できる記号の数は,上限がなくはないにせよ,間違いなく数十から数百にのぼる.」 そこで,彼ら霊長類学者にとって問題となるのは,次の点だ――「他の個体の鳴き声からほぼ上限のない数の意味を推測できる個体が,みずから発せられる鳴き声はごく限られているのは,どうしてだろうか?」
つまり,あまたいる哺乳類のなかで,どうして私たち人間は,顔面や口をこれほど制御でき,無限に多くの組み合わせができる数え切れないほどたくさんの音素[n.1] を産出できるのは,どうしてだろうか? 言語進化に関して中核となる問いは,「その適応的な機能はなにか」でもなければ「なんのために言語機能が必要なのか」でもなく,もっと手近に,「どのようにして進化したのか」という点だ.(原註1: 音素とは,識別可能な最小単位の音声のことで,たとえば "cat" の T がこれに当たる.〔※訳註: 言語学での標準的な定義では,意味を区別する最小単位の音声を「音素」と呼ぶけれど,ここではもっとゆるい意味で使っているらしい.〕)
ひとつには,「さまざまな音声を発する私たちの能力は,プロト言語〔いまあるような言語の祖型〕と共進化した」という考え方がある――語彙を拡大し言語の深度を深めるために人間は発声をちゃくちゃくと上達させていった.プロト言語の使用に長けている個々人ほど,その言語のおかげでこの世界を切り抜けていく能力が高まったり,言語をたくみに操れることで社会的な敬意をえられたりしたことで,より多くの子孫を残した.
だが,この説にはいくつか問題点がある.第一に,言語は,模範的といっていいくらいのネットワーク財だ:言語をたくみに操れる個体がいたとして,その個体が暮らす共同体の面々が言語を理解しないのであれば,彼らからの敬意など得られるはずもない――それに,いったい誰を相手に言語を使うというのだろう? この説明がうまくいくには,言語使用に必要な基礎的身体能力をすでにもちあわせている集団であるほど,言語の進化が容易でないといけない.第二に,適応にもっぱら着目して言語〔の進化〕を説明する説では,柔軟にさまざまな発声ができる能力の初期の足がかりがどこで発達したのかが語られていない.Bjorn Lindbolm の言葉を借りれば,言語音声の諸説にとって大きな課題の一つは「言語ならざるものから言語を派生させ」うる方法なのだ.
プロト言語が先にあってそこから柔軟にさまざまな発声をする能力にいたったのでないとしたら,初期の足がかりのひとつは,他の音声をまねる能力だったのかもしれない.人間言語においては,動物の鳴き声をまねてオノマトペを用いる「鳴きまね言葉」("warblish") に顕著に表れているように,言語と音声の模倣はからみあっている.〔訳註: 用語の紹介に間違いがある."warblish" は Sarvasy (2016) が提案した造語で,オノマトペではない単語を使って人間が鳥の鳴き声を模倣することを言う.たとえば "Who cooks for you?" でアメリカフクロウの鳴き声をまねることがこれにあたる.(Hannah Sarvasy, "Warblish: verbal mimicry of birdsong," Journal of Ethnobiology 36(4), 2016.)〕
人間の発達においても,動物の音声・鳴き声が言語学習で重要な位置を占めている点は特筆に値する.英語を母語として育った読者のなかには,昔からある幼児用おもちゃの Fisher-Price’s Farmer Says wheel になじみがある人もいることだろう.ランダムに動物を選んで,その動物の名前を子供に伝えて,子供にその動物の鳴き声を教える玩具だ〔動画〕.英語圏にかぎらずこのパターンは他の地域にも見られる.たとえば,1800年代にコイサン族を調査したレオナード・シュルツが,こんな記録を残している:「仮説ではなく確認のとれた事実として,ナマ語では,特定の動物の声を言葉で模倣することに子供が喜びを覚えることが,リズムの発達の方法となっている.」
こうした進化の筋書きでは,言語に見られるような柔軟にさまざまな音声を発する能力がいかに重要かが強く際立つが,それだけではなく,世界中で人間に共通して見られる音響特性として口笛が存在していることも重要視される.紀元前1世紀に哲学者にして詩人のルクレティウスが著書『事物の本性について』(De Rerum Natura) で述べているように,「調べ豊かな歌をともに歌って耳をよろこばすことを覚えるよりずっと前から,人々は鳥たちの「クルルル」と鳴くさえずりを自らの口でまねるのを覚えるものだ.」 また,鳥たちや〔シカなどの〕有蹄類の声をまねるのに笛などのリード楽器を用いる事例が繰り返し現れたことで,音楽の文脈でそうした道具を用いるお膳立てができたのかもしれない.
動物の声をまねることと人間認知の発達とのあいだに見られるこうした関係は,おそらく,言語だけにとどまるものではないだろう.
民族誌研究者の Rane Willerslev は,著書 Soul Hunters で,遊牧民ユカギール族の狩猟者たちとそのエモノたちとの関係をくわしく検討している.彼の主張によれば,世界でもっとも多く見られる最古の宗教であるアニミズムの起源は,模倣にあるのだという.初期の人類学者 E・B・タイラーが19世紀に示した定義にあるように,アニミズムの核心部分には,「自然のいたるところに命と意思があるという考え」がある――人間以外の存在にも人間のような生命力があるという考えがある.Willerslev によれば,ダンス・歌唱・シャーマンの変身・エモノとなる動物の模倣は,人間のものの見方の切り替え (perspectivism)すなわち自分以外の視点をとれる能力の起源で動物たちが果たしていた役割を際立たせるものかもしれない.
民族誌研究者コリン・ターンブルの記すところによれば,西アフリカの先住民ムブティ族のあいだでは,さまざまな魔術の儀式で動物霊を呼び出し,「狩人がその動物の動きを先読みしたり欺いたりできるように,狩人の内にその動物の感覚を呼び起こす」のだという(強調は引用者によるもの).自分以外の人・動物の思考を我が身に引き寄せるこうした能力は,みずからの理解の土台にもなったのかもしれない(マルティン・ハイデガーにはじまる現象学の哲学者たちなら,これを「対立の境界」と呼称するところかもしれない.)
こうした欺きや物真似の事例の多くでは,動物と同じように考え,動物と同じように行動し,動物になりきる必要がはっきりと述べられているのが見出される.こうした物真似の形態には,エモノとなる動物の行動をまねることだけでなく,そのエモノを捕食する動物の行動をまねてよりよい狩猟者になることも含まれる.
北米のポーニー・インディアン先住民のあいだでは,「狩猟の斥候隊のかしらは,狼の動作をまねつつ,腹ばいで用心深く進んだ.群れに気取られないようにするためだ.斥候がしらは,満足いくまで状況を調べ上げると,斥候隊の仲間を呼び寄せた.呼ばれた仲間たちも,やはり狼のように這って進み,あたりの様子をうかがった.」 北米のトナカイ放牧者たちのあいだでも,こうした模倣が広く行われていた.これを調べた19世紀の民族誌研究者は,こう書き残している:「ある程度までであれば,あらゆる動物の模倣は原始的生活をおくる多くの人々のあいだで起こるものかもしれない.ここで,古アジア族の人々のあいだに見られるこの種の事例を少しだけぜひとも指摘しておきたい.(…)たとえば,トナカイ遊牧民コリャークにとって狼は,自分たちのトナカイの群れを脅かすもっとも危険な敵だが,冬期に彼らは狼の毛皮でできた帽子をかぶる.」

言語の場合には,さまざまな動物を欺くために〔その動物をはじめとする〕さまざまな相手の視点をとる術を多用することは,人間相手にも同じことをする私たちの能力の進化で役割を果たしたのかもしれない.
私たちが他人の「頭に入り込む」能力や,他人が物事について持ち合わせている知識の理論を発達させる能力を,「心の理論」という.
多くの霊長類はある程度の水準の心の理論ならもちあわせているが,私たちホモサピエンスと同等水準の心の理論をもつ霊長類はいない.ホモサピエンスでは,高等な認知能力として心の理論が機能していて,これが私たちを他の動物から隔てている.
こうしたアイディアは,認知進化のさまざまな理論で際立った意義をもっている.たとえば,ロビン・ダンバーの「社会脳」仮説がその一例だ.社会脳仮説によれば,人間の大きな脳が進化してきたのは,大きな社会集団のなかで世渡りするためだという.また,これと関連して,「マキャベリ的知性」仮説では,大きな脳が進化してきたのはそうした集団内部で競い合うためだと考える.このように社会から説明する各種の理論で中心となっている考えはこれだ――「人間の知性は,私たちが他人をあざむき,だしぬき,あやつるために登場した.」
模倣の利用や,自分以外の動物の視点をとる能力の利用を考慮に入れると,「肉食パラドクス」を直截簡明に解釈できる.他の生き物の思考をみずからに取り込めるようになることで,私たちはエモノへの共感を発達させる道筋をひらいたのだ.他の捕食者たちがそうしているように,人間も,エモノを殺して食べなくてはならない.だが,他の捕食者たちとはちがって,私たちは自分のエモノに共感する能力をもちあわせている.
西洋の文脈の外では,狩猟者の罪責感や動物の命を奪うことに覚える痛みをはっきりと言い表した事例が民族誌の記録には満ちている.本稿の冒頭に,Willerslev の著書 Soul Hunters から罠猟をなりわいとする人物の例を引用した.だが,Willerslev が民族誌研究をすすめるなかで経験した事例は多数にのぼる.たとえば,聞きとり調査に答えて,ある若い狩人がこう言っている.「エルクや熊を仕留めるときには,人間を殺してしまったような気持ちになることがある.だが,そんな思いは振り払わなきゃいけない.さもなきゃ,恥のあまりに頭がどうかしてしまうだろうよ.」
こうした事例は豊富にある.Robert Knox Dentan がマレーシアの先住民セマイについて著した本にこんな事例がある.ある狩人が,狩りの後におぼえた罪責感について論じて,こう語る:「自分が食うものを欺いて罠にかけないといけない.だが,これはわるいことだ.やるべきじゃない.」 著者の Dentan はさらにこう述べている.「罠猟を手がけている人々は,「スリンルー」(狩猟者の暴力)に関連したこういう儀式的な心構えをしておかないといけないのだ.(…)思い起こしてほしい.動物たちは,「それ独自の次元で」ひとびとなのだ.だから,動物というひとを罠にかけるのは,深いところで反社会的であり,暴力的かつ欺瞞的なのだ.」
さらに,東南アジアやオセアニアのさまざまな文化の多くで,生きた鳩をヒモや長い棒にくくりつけてオトリにに使い,他の鳩たちをおびきよせる手口が書きとどめられている――だが,そうした事例のいくつかで,オトリの鳩を殺すのをいましめる文化的規範があるとも民族誌研究者たちが書き記しているのだ.オトリの鳩には,そのつとめを果たした敬意が払われているのだという.
では,肉を食べることへの忌避感,あるいは,肉を食べるにいたる過程で引き起こされる痛みの認識は現代の環境で生じた異変なのだろうか?〔言い換えると,「人類史で圧倒的に長い期間を占めている狩猟採集生活ではそうした忌避感などはなかったのだろうか?」〕
世界中で,狩猟者たちがときおり狩人の罪責感に近いものを経験している事実を見るに,こうした奇妙な矛盾した感覚はかなり古いように思える.
人間による狩猟を示す最初期の古人類学の証拠は,古人類(ホミニン)がエモノを狩猟していた場所から得られる.そうした証拠からは,私たちの最古の祖先たちが待ち伏せ型の捕食者だったことがうかがえる.アフリカ各地にある古人類による狩猟の場所の分布を見ると,私たちの祖先は,姿を隠せる自然の地形を利用してエモノを仕留めることが多かったことが読み取れる.
速度・ツメ・刃・毒など,捕食者たちが典型的に備えている手段を欠いていたにもかかわらず,人間は地球上でもっとも腕利きの捕食者として君臨してきた――それを,私たちはみずからの脳だけで成し遂げてきた.
「こうした認知特性が動物に由来するかもしれない」という考えは挑発的で異論を呼びやすいが,人間の文脈に当てはめると,けしてそのようなものではない.これまで,発声の柔軟性が言語に果たした役割,模倣による学習が文化学習に果たした役割,共感が情動の調整に果たした役割については,大いに語られてきた.だが,他の行為者たちとのやりとりを重ねることで人間の心が改正されているという事実には大いに関心が向けられてきた一方で,人間以外の動物もまた行為者であるという点にはほとんど注意が払われてこなかった.
20世紀後半にナチュラリストとして活動したポール・シェパードが述べているように,「動物たちには,人間の人となりに見られるありとあらゆる性質が備わっている.人間の気質や性格は多種多様だが,そのどれひとつとして人間に固有なものではないし,他の種のなんらかの側面に見いだされないものはない.人間とは,そうした性質が見出される新たな場所なのだ.」
【著者情報】コウディ・モウザ (Cody Moser) は,カリフォルニア大学マーセド校の認知・情報科学学部の博士課程学生.Twitter アカウントはこちら.
このエントリのサムネイル画像は、英国を拠点に活動するイラストレーター、Qianhui Yu氏によるものです。彼女の作品はここでご覧いただけます。
[Cody Moser, "On the origins of empathy for other species," Works in Progress, Issue 10, February 27, 2023]
〔翻訳者:optical_frog〕
〔一般社団法人経済学101は皆様の寄付によって賄われています。活動方針にご賛同頂ける方がいましたら、以下の「気に入ったらサポート」タブからの温かい支援をお待ちしています。〕
